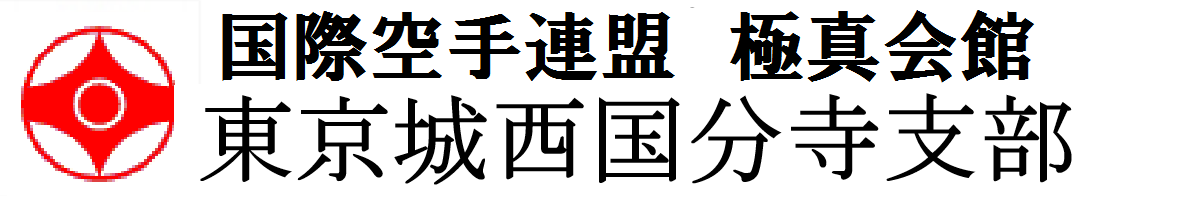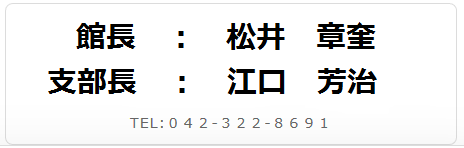もうひとつの独り言 2014年
2014.12.25第百四十回 ダメだ、こりゃ
国分寺北口の飲食店で、店から出た客を、店員が総出で見送っている光景に出会ったことがある。「ありがとうございました」と丁重にお辞儀をしており、とても誠意ある見送りのようであった。が、「いいことをしている」彼らはその時せまい道に広がっており、店の客ではない他の人々、通行人のさまたげになっていることには気づいていなかった。「ここの料理はマズいだろうな」と、そのとき思った。想像力の有無が仕事に通じないはずがないからだ。
筆者は、飲食店で出されたものが気に入らなくて、箸をつけずに店を出た経験が稀にある。というと、偏屈者だと言われそうだが、その基準はけっして高くはないと思う。
たとえば、チャーハンの飯がゴロゴロした塊になっていて、きちんとほぐれていないなど、プロの仕事とは思えない場合だ。できあがったラーメンを前に店長が長々と電話でしゃべっていた時も食べなかった。麺が伸びることや、料理に唾が飛び入ることに無頓着な人間の作ったものなど、口にする気になれなかっただけである。
味がどうのというより、仕事をする人の意識の問題で、そういうのが嫌なのだ。
筆者は厳しいのだろうか。自分としては、ごく当たり前のことだと思うのだが。
実名はあげずに、二、三軒、イケナイ店を紹介しよう。
国分寺から西武線で一駅の小さなラーメン屋。店長と、やや知的障害がありそうな女性が働いていて、筆者が麺類をたのんでから店長が出ていった。一人で作り始めた女性店員が、どうもモタモタしている。いかにも危なっかしくて、本当に大丈夫かな、ちゃんと作れるのかな、と心配になった(飯を食いに店に入ってなんでそんな心配をしなきゃいけないのか)。
そしたら店長が戻ってきて、その女性に一言。
「コラ、お客さんの料理には、清潔なお湯を使わないとダメじゃないか」
ああ、もう帰りたい! すぐに店を出たい! 往年の『ドリフの大爆笑』の恒例「もしものコーナー」だったら、いかりやが「ダメだ、こりゃ」と言うだろう。
次も同じ街の飲み屋。筆者もかつては一人でぶらりと飲みに行くことが多かった。
店員の対応は丁寧で、とても愛想がいい。ゆるゆる飲みだした時だった。筆者の位置から一直線で見えるトイレに、その愛想のいい女性店員が、わが子を入れてシモの世話を始めたのだ。ドアを開放しきっているので、乳幼児とはいえ、ケツも排便も丸見えだった。
そんなものを見せられながら飲食する気にはなれない。ほうほうの体で席を立った。公私混同にもほどがある。「ダメだ、こりゃ」
壁に値札が貼られていない飲み屋もあった。これは国分寺の南口。
割烹着姿の温厚そうなおばあちゃん二人がやっている、いかにも家庭の味という感じの店。
でも、値札がないのは気になった。けっこう飲んで、飲み代は5千円。
筆者は家を出るときに、一万円札だけを財布に入れてきた。その万札を渡したら、おばあちゃん、ただ平然とほほ笑んでいる。おつりを求めると、「ああ、五千円札だと思った」と、しれっとした顔で言った。こちらが泥酔して気づかないと思っているのだ。
油断も隙もあったもんじゃない。「ダメだ、こりゃ」
2014.12.19
第百三十九回 忘年会のシーズン
この時期、夜に街を歩けば、居酒屋の周囲で集まっている若者たちの喧噪を見かけることが多い。12月の忘年会と4月の新歓コンパの季節などにそれを目にすると、(おーおー、スネかじりが。……いっぱしに弾けおって)
と思う。学生時代は自分もそうだったくせに、社会人になると飲み方が変わるからだ。
筆者もサラリーマンの経験がある。某メーカーの広報室に勤務していた時期、たまに大学生が研究活動に使うために商品を借りたいと言って来社すると、その対応をすることもあった。
その時、筆者は入社二年目ぐらいだったが、上司に「学生を信用したらダメだ」と言われたことを覚えている。
「商品を貸したら、まず返さないから」
貸してもいいが、その場合は返ってこないと思っておけ、というのである。対面している時にどれだけ真面目そうに見えても、そういう点では学生を信用してはいけないのだと。
健さんやキャニオンが聞いたら怒るだろうか。しかし実際、貸した後は音沙汰がなく、商品はそのまま返ってこなかった。
ようするに、生活がかかっているかどうか、責任という負荷があるかどうか、という意識の差である。といった後で矛盾するようだが、無論、きちんと約束を守れる育ちのいい学生がいる一方、だらしない社会人も大勢いる。
今年、酔って駅のプラットホームから線路に落っこちたオッサンを初めて見た。立川駅だった。都市伝説のように思っていたのだが、そんなアホが本当にいるのだ。
また社会人になっても、学生時代のような飲み方をする場がある。
それは、ほかでもない極真の飲み会だ(本当に「ほかでもない」な)。
筆者は、職場の同僚と飲むのも好きである。とかく仕事の話というのは盛りあがる。とくに生徒の面白い行動などは、格好の肴になる。ただ、物足りなく感じるのは、普通の大人は酒を飲む時、あまりものを食べないこと。筆者は大いに食べ、大いに飲みたいのだ。
道場の飲み会では、みんなよく食べる。小食の空手家というのは、あまり見かけない。飲み過ぎて吐く人は世に多くいるが、道場には「食べ過ぎて吐く」人までいる(そういえばタケちゃんはどうしているだろう……と、ここで思い出す)。
学生のようなノリの理由は何だろうか。年齢関係なしで若者も多いから、というだけではないように思える。日ごろ叩き合っている間柄なので、かしこまる必要がないからだろうか。内部にいると身勝手なもので、悪い感じではなく盛りあがっている、と感じる。
この前、道場の大人四人で飲んだ帰り、一人の先輩が常夜灯の支柱に蹴りを入れていると、たまたま巡回していた警官に小言を言われた。筆者より年上で、会社の経営者(つまり社長)の立場にいる人である。なんとなく、微笑ましくも面白いエピソードだと思う。
夏合宿の宴会でも、ビールの空き缶でパンパンになったゴミ袋を残したり、窓から卑猥な言葉を叫ぶオッサンがいたりして、翌日からホテルの従業員の態度が変わったこともある。
そんなこんなで、28日は国分寺道場の忘年会である。
2014.12.12
第百三十八回 別れのワイン
必殺シリーズばかりがTVドラマじゃない。筆者にだって、ほかにもはまったドラマはある。海外のものだが、ピーター・フォーク主演『刑事コロンボ』である。旧シリーズの制作は70年代なのでかなり古く、筆者は80年代にテレビの『水曜ロードショー』で観た。
この作品、ジャンルでいえばミステリーなのだが、一般の推理ものとはあきらかに異なる趣向が施されている。推理小説に馴染んでいる人には「倒叙もの」で通じるだろう。
ミステリーには、誰がやったのかという犯人さがしに重点をおいたもの(フーダニット)や、不可能に見える犯行をどうやって実行したかというトリック(ハウダニット)、または動機を中心に描いたもの(ホワィダニット)など色々あるが、『刑事コロンボ』では、最初から犯人がわかっている。動機もたいてい明かされており、殺害の場面が映るので犯行方法やトリックも(たまに例外はあるが)視聴者の前にさらされているのだ。
そして死体発見となり、オンボロのプジョーに乗って、ロサンゼルス市警殺人課コロンボ警部の登場となるのである。
このドラマの面白さは、コロンボがどうやって緻密に計画された犯行を暴き、犯人を落としていくかという点にある。ようするに『古畑任三郎』のパターンといえば通じるだろうか。
犯人は毎回ちがう職業の人物だが、たいていは社会的地位が高かったり著名であったりして、エリート意識が強く、頭脳に自信を持っていることが多い。ときにはトリックにも自信を抱き、警察と勝負してやろうと意気込んでいる人物もいる。
一方で、ピーター・フォーク演じるコロンボといえば、実にもっさりとしている。よれよれのコートにやぶにらみで蓬髪という、一向に風采のあがらない外見をしており、あまり頭脳明晰には見えない。身体能力に劣り、警察官の義務でもある射撃の訓練もサボっている。
ところが、いざ捜査となれば、他の警官が見落としている不審点や犯人の言動の矛盾などに気づく鋭い洞察とあざやかな推理を見せるのである。そのギャップがいい。
「うちのカミさん」と毎回きまって家族の話題を出したり、帰りかけては引き返して「すみません、あともうひとつ」と思い出したように追加の質問をしたり、コートのポケットをさがしたあげく「すみません、エンピツを」と犯人に筆記具を借りたりもする。
こういった一見、愚鈍にさえ見えるコロンボに対し、犯人は油断をしたり舐めてかかったりするのだが、ラストには論理的に逃れられないところにまで追いつめられてしまう。
筆者は旧シリーズをすべて観たが、中でも好きなのは、『二枚のドガの絵』や犯人が蘭の収集家の『悪の温室』、イギリスが舞台の『ロンドンの傘』、なんとコロンボの上司が犯人という『権力の墓穴』(←この落とし方がいい)、暗い過去を持つ歌手の『白鳥の歌』、写真家のカメラによるトリック『逆転の構図』、陸軍学校長による犯罪『祝砲の挽歌』、豪華客船の中での殺人『歌声の消えた海』、マジシャンによる犯罪の『魔術師の幻想』、船舶会社の大物による『さらば提督』、推理作家の犯行『死者のメッセージ』などがある。はまったあげく、高校時代は学校でコロンボの真似をしまくっていたぐらいである。
あ。すみません、あともうひとつ。本文とはまったく関係ないのに今回のサブタイトルにした『別れのワイン』も。犯人に同情できる作品であり、ラストが印象的である。
2014.12.4
第百三十七回 必殺主題歌ベスト10(後編)
前回に引き続き、5位から1位までを。5位『旅愁』(暗闇仕留人)
シリーズの主題歌中、もっともヒットしたのがこの歌だという。そのため、いろんな歌手にカバーされている。なるほど一般受けするメロディーだと思う。歌っているのは最終回にゲスト出演している西崎みどり。彼女はこの後も何度かシリーズの主題歌を歌うことになる。
4位『負け犬の唄』(必殺からくり人・ほか)
江口師範による第1位。たしかに曲も歌詞もいい。酒を飲みながら聴きたくなる。イントロからして独特で、さびしげな舟人のエンディング映像に合っている。いきなり川谷拓三が起用されているのも斬新。必殺が次々に新しい試みを実践していたころの主題歌である。
3位『惜雪』(新必殺からくり人)
歌はみずきあい。せつなくなるようなブルース調の名曲で、もっとヒットしてもよかったのではないかと思う。本編にはブレイク直前のジュディ・オングがレギュラー出演している。
2位『さすらいの唄・夜空の慕情』(必殺必中仕事屋稼業)
主題歌と挿入歌だが、どちらもいい。大ヒットした『旅愁』の西崎みどりが14歳だったので、この歌手の小沢深雪も当時16歳の現役高校生。若いのに儚げな声と歌い方で翳りのある雰囲気を出していたが、なんと平尾昌晃氏と交際し、3年後に結婚して芸能活動を終えている。
1位『あかね雲・つむぎ唄』(新必殺仕置人)
2曲ともいい。ずばり歌唱力の勝利。声の伸び方がすごい。主題歌に小学生を起用するのは『熱中時代』の『ぼくの先生はフィーバー』に先んじること2年。川田ともこはこのままいけば天才だったが、現在活動していないのは残念至極である。演歌歌手の大御所になっていても不思議ではないが、才能だけではなく運の作用も強いのが芸能界の厳しいところか。
こうやってみると、意外なほど前期の作品が多いことに気づく。後期必殺の主題歌は『一瞬(ひととき)の愛』だけ。ということは、純粋に歌の評価というより、作品に対する好みも影響しているのかもしれない。1位と2位は、作品自体の順位も同じだし。
実際、『夢ん中』や『風の旅人』などすぐれた曲は他にも多々ある。後期の作品の主題歌も、三田村邦彦の『想い出の糸車』や『自惚れ』を「レコード」で持っていた筆者である。
それにしても、平尾昌晃が作曲の担当で本当によかった。『私の城下町』『瀬戸の花嫁』『カナダからの手紙』、アニメでも『銀河鉄道999』や『宇宙空母ブルーノア』などを作曲している平尾氏が、『必殺を斬る!』のインタビューで、必殺シリーズの作曲が自身のライフワークだと語っていたが、それもファンにとっては嬉しい話である。
2014.11.28
第百三十六回 必殺主題歌ベスト10(前編)
すべては平尾昌晃のおかげである。なにがって、必殺シリーズのBGMが充実している点だ。ファンはどれだけ、そのBGMに心を揺さぶられたことだろう。筆者などは高校生の頃からLPレコードでサントラを持っていたし、今でも必殺BGMのCDを全15タイトルそろえている。
今回は、その主題歌のベストテンを選出する。もちろん筆者の主観であり、独断であり、必殺を知らない人にとってはまったく興味のないネタであることは承知の上である。
まずは、10位から6位まで。
10位『荒野の果てに』(必殺仕掛人)
名曲であることは疑いない。にしては、なぜ10位なのかというと、やはり使い回されていることが影響しているように思う。後期のスペシャルでも映画でも、この曲のインストルメンタルがとにかく「殺しのテーマ」に使われすぎてしまった。が、やはり曲も歌詞もよくて、今でも新しく感じるほどだ。
9位『望郷の旅』(助け人走る)
アップテンポでメロディーラインの変化に富んだ、いかにも平尾昌晃らしい曲。必殺では主題歌のインストルメンタルが殺しのテーマになることが多いが、これなどはそのままアレンジなしで使える。
8位『一瞬の愛』(必殺渡し人) 鏡研ぎ師の惣太役でレギュラー出演している中村雅俊の歌。例によって唇をすぼませるように歌っている。せつない歌詞が、最終回での妻との結末を暗示するかのようである。ちなみに著作権の関係なのか、この歌だけサントラのCDに収録されていないのが残念。中村雅俊のCDを買うしかない。
7位『哀愁』(必殺仕置屋稼業)
演歌調なのに、どことなく洗練されていて斬新。歌唱力自体は他の歌手に比べてそれほど上回っているとは思えないが、エンディングの映像と合わせて聴くと、放映当時の世の中の空気のようなものを感じさせる。現在では、けっして制作されないメロディーである。
6位『西陽の当たる部屋』(必殺仕業人)
主題歌ではなく挿入歌。第一話の冒頭、小雪の舞い散る夜更けの路地裏で、中村主水と赤井剣之介(中村敦夫)が初めて出会う場面で流れる。ハードボイルド調の『仕業人』の作風に合った曲で、主題歌の『さざなみ』よりも渋く強力である。
というわけで、次回は5位から1位まで。
2014.11.21
第百三十五回 衝撃の訃報
芸能ネタが続いているが、今回ばかりは仕方がない。高倉健が亡くなったのだから。
公表されたのが18日。死去されたのは10日だったという。享年83歳とのことで、年齢的には不思議ではないにしても、今後も活動を続けそうな人だったから突然の死は意外だった。年齢不詳の面影があるが、80をこえていたとは驚きである。
出演した映画の本数、実に205本。これもびっくりだ。筆者は、健さんを一躍スターにしたという一連のヤクザ映画については、まったくといっていいほど知らないが、偏愛する作品としては、『駅 STATION』がある。ほかにも『八甲田山』や『海峡』といった骨太な作品が好みである。
『駅 STATION』はテレビで初めて見て以来、もう20回以上は見ている。テレビ用にカットされていたシーンまで見たくて、市販のDVDも買ったぐらいだ。何度見ても飽きない。
脚本は倉本聰。北海道を舞台にした不器用な刑事の物語なのである。
昔気質な面のある三上英次(高倉健)は、警察の先輩(大滝修治)が射殺される現場に居合わせてしまう。犯人(室田日出男)は指名手配中の凶悪犯であり、逃亡の車を検閲中、目の前で撃たれたのだ。
物語は三つのパートに分かれて進められるが、その三つ目の「1979年 桐子」の話で、北海道は増毛の小さな居酒屋を経営する女性・桐子(倍賞智恵子)との、つかの間の恋愛が描かれている。正月に故郷の雄冬に帰省する予定が、荒天で連絡船が欠航になり、たまたま立ち寄った居酒屋が桐子の店だったのである。
ここで、実生活では下戸の健さんが、実に美味そうにコップ酒を飲む。
その日の昼間、三上は駅で桐子を見かけていた。戻ってこない誰かを待っているようなそぶりが印象に残っていたのだ。急速に深い仲になる二人だったが、初詣の帰り、桐子の待っていた男が帰ってきた。
気を利かせて立ち去る三上。だが、その男は、かつて先輩を射殺し、いまだ逃亡中の指名手配犯だった。それを知った時、三上はある過激な行動に出る。
かつてオリンピックの代表に選ばれるほどの射撃の名手だった三上だが、警察官としての仕事に疲れ、辞職を決意し、故郷での仕事を求めて帰省していた。
だが、器用な男ではない三上は、自分が警察官以外の生き方ができないことを悟り、電車を待つあいだ、増毛駅の待合室のストーブで辞表を燃やす。そして流れる『舟唄』が泣かせる。
映像作品において、音楽の力は非常に大きい。倉本聰はおそらくそれを熟知し、この映画で紅白歌合戦まで用いて、八代亜紀の『舟唄』を流したのだろう。
ちなみに、この映画の音楽は宇崎竜童が担当し、作中でも健さんにからんでボコられるチンピラの役で出演している。それが本当に軽薄なチンピラそのもので、オープニングに流れる美しいテーマ曲を「こいつが作曲したなんて」と思ってしまうのも、音楽・演技ともに才能にあふれているゆえである。
2014.11.14
第百三十四回 「屋根の男」有用
ジョディ・フォスター、吉永小百合、ときて、次はどんな美しい女優が登場するのかと思えば、「マキ」である。マキって誰だ。後藤真希か、堀北真希か、あるいはカルメン・マキか。女子柔道の塚田真希選手か。はたまた梶原一騎氏の実弟・真樹日佐夫先生か。そもそも何マキなんだ。名字か名前か、どっちだ。
筆者も知らない。なぜなら、ただ「マキ」としか表示されていないから(ここまでの時点でピンとくるのは、江口師範だけだと思う)。
男性であることは間違いない。肥満体で、細目で、しかも服を着ているところを見たことがない。いつも赤ふんどしをしめて、往来の上に張り渡された板に腰かけ、なぜか釣り竿を垂らしている怪人。そう、『新必殺仕置人』に登場する謎のキャラクター「屋根の男」なのだ。
この男、なぜか中盤からレギュラー入りし、毎回ストーリーとは関係なしに、頓珍漢な一言を口にするギャグ担当なのである。
たとえば正八がガールフレンドに平手打ちされたタイミングで、なぜかこの男が「痛~い」。
雷鳴が轟き、豪雨が降る中、相変わらず釣り竿を握ったまま「暑い、冷たい、寒い~」。
なぜかチャボを抱いて池の縁に腰かけていて、たまたま殺人の現場を目撃してしまい、「死んだ~」とつぶやくと、なぜかそのまま前のめりになって、池にザブン(爆笑必至)。
それまでの経緯を知らないくせに「そして三年」と、ナレーション役を果たしたこともある。
極めつけは鉄(山崎努)とのブランコだ。懸想する女性(大関優子=今の佳那晃子)とのブランコを妄想する鉄が、現実には「屋根の男」と並び、同じ赤い腰巻き姿になって屋根に腰かけている。しかも意気投合している。
だが、最高に笑えるのは『幽霊無用』の回での全裸釣り竿である。幽霊が出たと慌てふためき、上から赤い布が落ちてきてさらに怖がりながら巳代松の長屋に駆け込んだ正八。巳代松が「おい。あれ」と上を指さすのを見れば、「屋根の男」が隣家の瓦屋根の上に立って一糸まとわぬ真っ裸(両手がちょうど股間を隠す位置に来ている)で釣り竿を上げ下げしているのである。正八も「あら~」と失笑。巳代松も素で笑っている。
屋根の男とのかけ合いがもっとも多いのが正八(火野正平)で、次が鉄、巳代松や中村主水はあまりこの男に関心がないらしい。
中盤あたりから登場した理由のひとつは、ふんどし一丁の裸ということもあるだろう。現に、秋口の放映となった回では、いつも関西弁なのに「寒いよ。もう耐えられないよ」となぜか標準語で言っている(今回「なぜか」が多いが、それほど謎の男なのである)。
でも、それ以上に、たぶんスタッフの思いつきだったのではないかと思う。というのは、このマキ、正規の俳優ではなく、火野正平のマネージャーらしいのだ。変な顔だし、キャラが立っているから「いっそ登場させるか」ということになったのではないか。遊び心が満載の作品なので、それくらいのノリは普通にあるように思える。
ちなみに、最終回のこの男の出演シーンも傑作である。「釣れた!」と言う。ハリのない竿でとうとう何かが釣れる。そして、長らく謎だった正体がついに判明するのである。
2014.11.6
第百三十三回 吉永小百合もすごい
驚くべし。一夜にして国分寺駅北口が様変わりしているではないか。ずいぶん前から中央部が遮蔽されたままだったので、このまま半永久的に、たとえば「ベルリンの壁」がそうだったように、来世紀まで変わらないだろうと思っていたので、意表を突かれた。すでに階段は存在感をなくし、幅の広い通路が、文字どおり「幅を利かして」いる。
そう。存在感がない、といえば、筆者だ。なんのことかって、その場にいてもあまり気づかれないことが、たまにあるのだ。道場でストレッチなどをしていても、後輩が挨拶もせず、目の前を素通りしていくことも珍しくないのである。
それが不満なのではなく、むしろ目立たないことを願っている。高校生のころ、授業中に「気配を消す」ことを志していた時期があったので、その名残りか。あるいは、外見に特徴がないからか。どっちにしろ目立たなくていいのである。
だが、俳優なら、この存在感が重要になってくる。顔がいい、スタイルがいい、というだけでは通じない世界だからして、アイドルやモデルにもいえるが、役者にとってはなおさら、演技力とならぶ絶対条件だろう。
女優に関して、「なにか演技しなくても、画面に出ているだけでいい」と言えば、世の一部の女性たちに叱責されるだろうか。
でも、さゆりすと(吉永小百合のファン)の立場で彼女の出演作を観ていると、そんなふうにも思えてくる。これも存在感の強さゆえである。
もとより、吉永小百合の出演作品は膨大な数にのぼっていて、若い時期は年間10本以上も映画に出ている。テレビ番組ではなく、映画での出演で、多い年では16本にもなっているから驚きだ。一カ月に一本以上だなんて、とんでもない。
それほどのハイペースだと、一作ごとに入魂の役作りはできないだろう(と、かばう)。結果として自然体の演技になるのは必然だと思う。
そして、その過密スケジュールのわりに、吉永小百合は痩せていない。太ってはいないが、顔などぽっちゃりしている。
それが新鮮なのは、最近の女優さんたちが、へんな痩せ方をしているように思えるからだ。自然に痩せているのならいいが、あごから首の辺りが筋張っていて、なんだか「無理なダイエットの結果」という感じがする。美しいという前に、どうも痛々しく見える。
いつも恋人役などで共演している浜田光夫も、さわやかで飾り気がなく、今はあまりいないタイプの俳優である。冷戦の真っ只中で世界情勢は緊迫していたころだが、日本の映画界はほのぼのした雰囲気だったようだ。
内容のほかに新鮮で興味深いのは、当時の東京の風景である。
チャップリンの映画、たぶん『キッド』か『ライムライト』などで、90年以上前のロンドンの風景を見たが、これがまた驚くほど汚いのだ。モノクロの印象や撮影した場所にもよるのだろうが、それにしても……と思った。
吉永小百合の初期の作品でも、50年以上前の東京の町並みを見ることができる。広くて、すっきりしていて、現在とはまったく異なっている。まるで去年と今年の国分寺北口のように。
2014.10.31
第百三十二回 ジョディ・フォスターはすごい
以前このブログで、ロバート・デ・ニーロのことを書いた。その神がかった演技力と鬼気迫る役づくりから、筆者のもっとも好きな俳優であると。ハリウッドは、やはり役者を生む土壌が肥えていいて、キラ星のごときスターが群れ集っている。女優でいえば、一流がひしめく中でもひときわ光る演技力の持ち主が、ジョディ・フォスターだろう。
筆者は、かつてジョディ・フォスターの出演作と聞けば映画館に足を運び、気に入った作品はDVDを買っていた。一種の追っかけだが、演技派が好きなのかもしれない。
演技の質の分類でいうなら、彼女は憑依型ではないように思える。
すなわち憑きもののごとく役になりきってしまうような、日本でいうなら大竹しのぶのようなタイプではなくて、どんな役を演じていても、ごく自然にジョディ・フォスターという強烈な「個」があって、そこから外れることがないように思えるのだ。ちなみに、デ・ニーロは憑依型かもしれない。
ただ、『パニック・ルーム』にしても、『ブレイブ・ワン』や『フライトプラン』にしても、果断な行動力をもつ女性の役が多く、それが彼女自身のキャラクターに合っているように見受けられる。
加えて、知性的である。来日したときの会見などでは、インタビューアーの質問が終わりきらないうちから返答することが多かったという。頭の回転が早いのだろう。
その両方の要素を合わせて演じたのが、一筋縄ではいかない女弁護士の役で出演した『インサイド・マン』だろうか。
初の監督作品『リトルマン・テイト』では、ウエイトレスをして一人息子を養っている母子家庭の母親役だった。いささか粗野で、天才児の母親ながら教養がない、という役柄だったが、どうしても知性が出てしまっていた。
ビジュアル的には、FBI候補生クラリスを演じた『羊たちの沈黙』のころが一番美しかったように思う。これは原作もすばらしく、映画もカンペキという作品で、アンソニー・ホプキンズ演じる天才心理学者にして食人犯罪者ハンニバル・レクターとのかけ合いが緊張感あふれていた。
その続編『ハンニバル』も、当然クラリスの役をジョディ・フォスターが演じるものと思いこんで映画を観に行ったのだが……まさかキャストが変わっていたとは! 映画自体はよかったが、クラリス=ジョディ・フォスター、レクター博士=アンソニー・ホプキンズという配役が見事だと思っていたので、キャスティングでこれほどガッカリしたことはない。
脚本(内容)があまりにえげつないので引き受けなかったというから、潔癖な一面もあるらしい。そんな理由で断られてしまう『ハンニバル』の原作も、筆者は傑作だと思うが、たしかに、まあグロテスクで、やりすぎ感はある。
それはともかく、ジョディ・フォスターは十四歳のころに、『タクシー・ドライバー』で、かのロバート・デ・ニーロと夢の共演を果たしている。でも、それっきりだ。もう一度実現しないだろうか、その黄金コンビの共演が。
2014.10.24
第百三十一回 日野日出志のあやしい世界
本やマンガは、現実の空間にぽっかりとあいた異世界への入口だ。ページを開けば、そこには日常とかけ離れた世界が、四角い枠の中に存在している。筆者は小学生のころ、友だちの部屋で、ときには書店の一隅で、地獄を見た。
日野日出志。この強烈な個性を放つホラー漫画家を、今はどれほどの人がご存じだろう。
いや~、強烈だった。いつの時代でも子どもは怖いマンガが好きで、筆者たちもいろんな作者のマンガ本を読んだが、日野日出志は別格だったといえる。
けた違いの破壊力。もう、ダントツで怖い。絵からして怖い。
絵柄は、たしかにグロテスクである。でも、それだけじゃない。気持ち悪さの中に、美しさと、そしてもの悲しさがある。不思議な作品なのだ。
いくつもの日野作品に、共通して描かれている光景。それは煙突の立ち並ぶ工場の街で、孤独な少年がドブ川をながめている場面である。
煤煙を吐きつづけるオバケのような煙突の群れ。暗くて赤い不吉な空。日々その色を変えるドブ川には、こわれたオモチャや木片や犬の死骸など、雑多なものが浮かび、ひしめき合っている。少年は川べりにしゃがみ、眼球が垂れてウジのたかった犬の死骸を、棒の先でもの憂げにつついている。
作者の原風景なのだろうか。不気味だが、もの淋しくて悲しい光景である。
そして始まる恐ろしい物語。日野日出志は、子どもの読者が相手でも、余計な配慮をしない。読んでいると、同い年ぐらいの小学生がバンバン死んでいく。梅図かずおの『漂流教室』もそうだが、これが怖かった。
大人から見れば、いたいけな子どもが犠牲になるマンガなんて有害図書だ、と思うものだが、なんせ読者は子どもである。子どもが読んだときに、大人しか死なないように配慮されたマンガなど、身近に迫ってくる恐怖がない。
実際、書店で『恐怖列車』という作品を立ち読みした時は、しばし呆然として、家に帰るのをためらう気持ちになっていた。冬で、外はもう暗くなっており、怖いことしきりだったことを今でも覚えている。
そして子どもの心理の面白いところは、日野作品にトラウマを覚えるほどの恐怖を感じていたくせに、一方でマイルドに配慮された作品を歯牙にもかけず、バカにしたところである。
媚びている、という作者や編集サイドの意図を見ぬき、鼻白んでしまうのだ。
今にして思えば、子どものころの筆者は、日野作品を通して「世の中の不条理」を眼前に突きつけられ、その救いのなさと悲しさにショックを受けていたのかもしれない。
マイルドに配慮された作品には、不条理による「真理」が描かれていなかった。だから、物語として弱かった。
と書いているうちに、また日野日出志のマンガを読みたくなってきた。
『地獄の子守歌』『蔵六の奇病』『赤い蛇』『毒虫小僧』といった作品は復刊されていて、今でも読むことができるが、『まだらの卵』や『幻色の孤島』が手に入らないのは淋しい。紙のマンガ本での復刊を願うばかりである。
2014.10.17
第百三十回 全日本を観戦する意味
今年も東京体育館で極真の全日本選手権が開催される季節となった。筆者は仕事と重ならないかぎり基本的に毎年観戦することにしている。「わざわざ会場まで行かなくても、テレビで放映するんだから、それを観ていれば十分」
とは思わない。まったく違うからだ。たとえて言うなら、音楽をCDで聴くのとコンサートで聴くほどの差である。収録され、編集されたもの、すなわち再生産されたものを部屋で鑑賞するのではなく、効果音もBGMもない観衆のざわめきの中で、選手たちと、時間と空間を共有することの迫真性がある。
ちなみに筆者の観戦歴は古く、(毎年かならず見続けたわけではないが)はるか前の大会も観たことがある。
たとえば、第五回世界大会。アンディ・フグも大山総裁もご存命だったことを思えば、もう大昔といえるかもしれない。
そのころの筆者は、東京体育館に向かう電車の中で、ほかの乗客に対して「この人たちは世界大会を観に行かないのだろうか。ほかに何を観るというんだろう」などと思っていた。今は筆者よりもアジアジのほうが熱心で、観戦中は飲食すら拒むほどだ。
第五回世界大会といえば、優勝候補だったアンディ・フグが、無名の選手を相手にやたらと苦戦していた。と思ったら、なんと、相手の上段廻し蹴りで一本負けしてしまった。
膝から崩れ落ちるように倒れ、起きあがらなかったのだ。
優勝候補がまさかのKO負け。もう会場は騒然である。筆者もいっしょに観ていたメンバーとパンフレットを繰って、相手の名前を確認した。
「誰だよ。聞いたことないなあ、フランシスコ・フィリォなんて」
格闘技の歴史のページが、ぱらりと音を立ててめくられた瞬間だろう。
この第五回世界大会というのは、記録的なまでに派手な大会で、岩崎達也選手とジャン・リビエール選手(カナダ)による、後ろ廻し蹴りのクロスカウンターという信じられないKO劇もあった。また、大山総裁の最後の演武も観ることができた。
とにかく、会場で観るということは、その現場に立ち会うということなのだ。
師範がおっしゃるように「最高の技術を見て勉強する」という効果に加えて、筆者などからすると、「人」を見るという意味もあるように思う。
ボクシングなどに関しても言えるかもしれないが、観客は試合展開よりも、選手が見たいのである。もっと言うなら、「人」というより、「生きざま」が見たいのだ。
筆者は江口師範の試合も生で観たことがある。目が釘付けになるほど壮絶な戦いぶりで、正直、心が震えたものだ。その結果、いま国分寺道場にいることを考えれば、テレビではなく会場で観戦したことは、運命的ですらある。
くり返すが、テレビ局の人の主観によってカットされ、編集された映像を観るのと、会場で観るのは同じではない。別物と言っていい。
新しく入門したばかりで、まだ一度も試合を観たことのない方は、この機会にぜひ会場に足を運ぶことをお勧めしたい。自分もその場にいて、日ごろ教わっている先輩や先生の試合を見とどけ、運命的な経験をしてほしいと思う。
2014.10.10
第百二十九回 晩飯と学力の関係
中学受験をすると決めたら、小学生の子どもだって大変だ。塾のある日は、家でゆっくりと晩ごはんを食べることができない。平日なら、みんな学校が終わってから塾に来る。授業が終わるまで何も食べないとお腹がすいてしまうから、コマとコマのあいだの休み時間に、お弁当を食べるのである。
最初は、それがかわいそうだと思った。
よそいたてのホカホカご飯じゃないし、温かいみそ汁もない。せま苦しく机を並べた教室で、固いイスに腰かけて、団欒もなく、短い休み時間のうちに食べておかないといけないのである。受験なんかしなけりゃ家でお母さんといっしょに食べられるのにな、と思っていた。
ところが、子どもたち自身は、それが別にイヤではないらしい。当たり前だと思っているので、平気で楽しそうに食べている。
ほとんどの子は、お母さんが届けてくれたお弁当を食べる。作りたてで、まだ温かさの残る愛情のこもったお弁当である。
でも、中には、そうでない子もいる。
「先生は今日の晩ごはん、なに?」
ときいてきた子がいた。小5の女子だった。
「先生は帰ってから食べるよ」
と言って見ると、その子の「お弁当」は、コンビニの袋に入ったロールパンだった。
ロールパンが一個……。
小5の女の子の晩ごはんとしては、あまりにわびしすぎないか。
本人は平気なのだろうか。平気なわけがない。わびしさを感じていなければ、「先生の晩ごはんは、なに?」と、きくはずがないと思う。
それほどひどくはなくても、コンビニの弁当やファーストフードの配達といった晩飯もある。カロリーが高いから、子どもにとっては、それなりに食べごたえがあるかもしれない。
でも、気づいたのは、お弁当の充実度と学力が意外に関係している、ということだ。
ロールパンの子は、性格はやさしくて素直だったが、やや素行にだらしないところがあり、成績といえば底辺だった。コンビニやファーストフードの子たちも似たような傾向にある。
学力にかぎったことではなく、行動や集中力にも差が見受けられる。ひと様の弁当を観察するのもなんだが、あらためて見てみると、きちんとしている子は、栄養のバランスが考えられた手の込んだオカズを作ってもらっているのだ。
これだけのデータで関係性を断定してしまうのは、いささか乱暴にすぎるだろう。関係があるとしても、栄養が脳に回っての結果というよりは、親の意識の問題ではないかと思う。
子どもを通して親の姿が見えるのである。それも、実によく見える。わが子の食に無頓着な親は、ほかのことにも鈍感なのだ。そういう親のもとで育っていれば、例外はあるにしても、子どもの言動だって影響を受けるにちがいない。
似たようなことが、キラキラネームを含む、どう読めばいいのかわからない名前の子にもいえるのだが、この話はまた別の機会に。
2014.10.3
第百二十八回 理科室のメロディ
学校の教室の中で、理科室は他の教室とは明らかに異なる怪しげな雰囲気を醸し出している。いわば異空間といおうか。骨格標本や人体模型、厚手のガラス瓶の中で、ホルマリンに漬けられて白っぽくなった不気味な生物たち。かすかに薬品のにおいが漂う静謐な空間に、沈黙をもって並ぶ試験管やビーカー、フラスコといったガラス製の実験器具は、その個性的な形状が魅惑的で、たとえばフラスコの底の形にどんな意味があるのだろうと思い、使ってみたくて仕方なかった。
筆者は子どものころ、学校の授業の中で理科と図工が好きだったが、理科が好きな理由は、もちろん実験できるからである。子どもの身で、科学者にでもなったかのように実験に必要な器具が使えるのだから、他の科目とはわけがちがう。
小学4年生の冬、理科の実験で、試験管を用いてアイスキャンディーを作った。試験管そのままの円筒形をしたオレンジ色のアイスキャンディーは、衛生面はともかく、できた喜びに加えて、授業中にそんなものを食べられるだけで感激だった。
だが実験の中には、解剖も入る。中2年の時には、班ごとに分かれてカエルの解剖をおこなった。方法は意外に原始的で、まずカエルの頭をクギで殴打して気絶させるという。
誰もがやりたがらないそのイヤな役を、筆者がさせられた。
が、叩くといってもどれぐらいの強さで打てばいいのかわからず、加減してしまった。性格の甘さとしか言いようがない。なんとなく、かわいそうになったのである。
これが災いして、なんと腹を割いている最中にカエルが暴れだした。叩くのが弱かったせいで気絶から覚めたのだ、と先生に言われ、なんとも後味の悪い解剖となった。
同じ中2の時の実験で、ヒトの口内の粘膜細胞を顕微鏡で観察する、というのもあった。
当然、班の中から、誰かが細胞を提供しなければならない。
筆者が選ばれた(いつもこうだ)。細胞を取るといっても、ガラス棒の先で頬の内側を軽くこするだけなので、痛くも何ともない。
顕微鏡をのぞいてみると、クラゲみたいなプヨプヨした○がいくつも見られた。
それを見た班の奴ら、とくに女子連中が「やだー、なにこれー」とか、「気持ちわるー」といった遠慮のない感想を、やたらと連発する。
「お前らにもあるやろがー!」「あんただけとちがうの」と不毛のやり取りを経て実験は終わったが、結局なんのための実験だったのかはよくわからない。
高校の時には硫酸も使った。これもどんな内容だったかは忘れたが、「硫酸」という言葉自体が刺激的で、緊張感をもたらすものだ。
「おお、硫酸だよぉ」と思いながら作業しつつ、「なんか指がベトベトする」と言ったら、となりの子に「それ、皮が溶けてるんじゃない?」と言われ、あわてて手を洗った。
アルコールランプを使っていて火炎が縦に伸びまくってしまったこともあるし、実験というのはどうやら失敗したもののほうが記憶に残っているようである。
ちなみに今回のサブタイトルは、アラン・ドロンとジャン・ギャバンの共演作『地下室のメロディ』をもじっただけで、それ以外の意味はまったくない。
2014.9.26
第百二十七回 破壊神復活
いささか時期をのがしたネタだが、今年の夏に公開された『GODZILLA』、つまりハリウッド版の『ゴジラ』の出来は、いかがなものだろう。まだ上映されているようだが、たぶんこのまま観に行けないと思う。でも気にはなっているのだ。今回の『GODZILLA』は重量感を感じさせる動きだが、ハリウッド版といえば、過去にもニワトリのように跳ね回る軽快なゴジラが製作されている。筆者はずっと前に、テレビの洋画劇場でクライマックスのあたりを観ただけだが、あれじゃ『ジュラシック・パーク』のTレックスと変わらないな、と思った。
スピーディーにすればいいわけじゃない。ゾンビだって、あの遅さが持ち味なのである。大勢でわらわら出現して、すき間をかいくぐって逃げなきゃいけない、あるいは油断しているといつのまにか間近に迫っている、というのが怖いのだ。
ちなみに、記念すべきシリーズ一作目、世界の映画監督に影響を与えた最初の『ゴジラ』を、筆者は市販のVHSでもっているが、これがまた、心が痛くなるというか、何度も観られないほど重い映画なのである。
1954年(昭和33年)の制作だから、フィルムは白黒だし、CGを駆使した現在の映像からくらべると、特撮技術はたしかに劣っている。ゴジラが吐く放射能光線も、後年の作品なら白みがかった鮮やかなブルーだが、1作目のは蒸気か煙の噴射といった感じで、それ自体の迫力は乏しい。
だが、怖いのだ。なにがって「炎」が。
ゴジラの放射能光線にふれて、めらめらと燃えあがっていく木造家屋。逃げまどう群衆。それが異様な迫力を帯びているのは、スタッフの中に、まだ空襲の記憶が生々しく残っていたからだろうか。モノクロのうえ特撮技術もすぐれているとは言えないのに、およそ「炎」がこれほど恐ろしくフィルムに投影されている映画を、筆者は他に観たことがない。
おそらくは父を戦争でなくしたのだろう、逃げまどう群衆の中で、「もうすぐお父さんのところへ行くのよ」と、幼い娘に語る母の姿もあり、「えっ、この母子も火炎の中で死んじゃうの?」とショックを受ける。
後年の、ゴジラが子どもの味方のようになった軟弱なシリーズを観なれていた立場からすると、ゴジラがひどく残酷に思えるのである。
しかし、ゴジラは「核兵器」の象徴なのだから、残酷なのは当然ともいえる。
水爆実験で眠りから覚まされ、びらびらの背中やゴワゴワの皮膚も、あれは被爆によるものというではないか。なるほど核兵器なら殺戮は無差別であり、小学生だろうが赤ん坊だろうが見境はないはずだ。
1作目は、そのゴジラ自身の最期も無惨だったし、一件落着した後も「人類が水爆実験をやめなければ、第二第三のゴジラが現れないと、どうして言いきれるんだ」と主要登場人物が苦悩し、あながちハッピーエンドとも言いきれない、苦い後味を残す終わり方だった。
さて、今回の新作『GODZILLA』だが……。シリーズの根幹をなす反核というテーマが、核保有国であるアメリカの製作でどう処理されているのか、気になるところである。
2014.9.19
第百二十六回 信用できる情報はどこに
まずは、訂正から。第116回「恐るべし、国分寺常連軍団!」で書いたカナイズム氏のことだが、先日ご本人から「師範のスパーリング・パートナーなんて務まりません」という旨の話があった。たしかに、これは筆者の筆が滑ったといえるかもしれない。身近に指導を受けていながら、江口師範の強さを正しく認識することなど、できないのだから。最近になって師範の身体能力に関するとんでもない事実を知ったのだが、それも一端にすぎないし、格闘の強さとなると我々が想像できるレベルの上限を超えているはずである。
たとえば、5階の加圧トレーニングの部屋で一本歯の下駄を見たことがあるが、ああいうものをいったい誰が履くのか、ということである。天狗さまの履き物ではないか……。
そんなわけで、116回の記述は筆者の筆の誤りだったとして訂正させていただきます。
出版物なら、校閲といって内容の真偽をチェックする専門の機関があり、編集者と校閲で赤ペンを入れ、もちろん著者自身も校正したうえで刊行されるのだが、それを経ていないウェブ上の情報など、かように心許ないもの。
筆者は、自分の生徒たちに「新聞やテレビの情報だって、なにが正しいかわからないんだから、鵜呑みにしちゃいけない」と話している。かの朝日新聞の社長だって、東電の吉田文書について先日謝罪したばかりである(従軍慰安婦に関してはどーなんだよ……?)。
朝日といえば不祥事続きだが、ずいぶん前も、サンゴに「K・Y」とイニシャルが彫られている写真とともに、「こんな非常識なことを誰がやったのか!」という旨の記事が掲載されたことがあった。後日、朝日の記者がその犯人だったことが判明。自分でネタ作りにやったのだ。
筆者もまだ若く、純粋に新聞やテレビの情報を信用していたころだったので、「なるほど、そういうものなのか」と軽度のカルチャーショックを受けたことを覚えている。
こうなると、流行語になった「空気読めない」の「K・Y」は、朝日が広めた造語ではないかと勘繰ってしまう。ようするに、検索しても、その恥さらしな事件が簡単に出てこないようにするための策略ではないか、とさえ思うのである(なんだか朝日新聞の悪口になってきた)。
また『朝まで生テレビ』という番組があり、これも一時期は見ていたのだが、湾岸戦争で地上戦が勃発した時の回で、女性のアシスタントがすごい迷言を吐いた。
冒頭、司会の田原総一郎が「とうとう地上戦が始まりましたね」と言ったのに対し、「ええ、面白くなってきましたね」と、思わず本音を口にしてしまったのである。
筆者はテレビの前で吹きだした。
ことは現実の戦争である。人が死んでいる。録画していないから記憶に頼るしかないが、田原氏はあわてて「そんなこと言っちゃいけませんよ」みたいなことを言っていたと思う。
もちろんフォローのしようがない。普通ならカットされるところだが、生放送だったから、それが全国に流れてしまった。この番組もテレビ朝日で、今でもやっているらしい。
必殺シリーズもテレ朝なので、あまり悪口は言いたくないが、「収録の現場なんて、こんなもんなんだな」ということはわかった。
天下の大新聞やテレビでも、こうなのだ。ましてや氏村の発信する情報なんて……。
2014.9.12
第百二十五回 エルトゥールル号事件とは
9月といえば台風の季節である。この時期は海難事故が多い。洞爺丸の沈没は1954年9月26日。津軽海峡など、地図の上ではわずかな距離にしか見えないのに、死者1000名をこす日本最大の海難事故となった。
洞爺丸は有名だが、エルトゥールル号事件となると、知っている読者は少数派だろうか。
時に、西暦1890年9月16日、トルコ(オスマン・トルコ)の軍艦エルトゥールル号が、和歌山県の串本で遭難したのである(また紀州ネタか)。
岸壁にたどり着いて助かった乗組員は70名近く。その際、地元の人々が、誰に命令されたわけでもなく衣類や食料を分け与え、台風の影響で自分たちの食べ物も十分ではなかったのに、非常時のために飼っていた鶏まで惜しまず提供するなどして、不眠不休で彼らを助けた。
寄付金も集まり、明治天皇の即断で、遭難者を二隻の軍艦に乗せてトルコまで送り届けたのだが、この時、日本人に手厚く救護されたことを、助かった人たちが話し、トルコの小学校の教科書などにも載せられて広まったという。
地理的にロシアに隣接するトルコは、帝政時代のロシアから圧迫されており、同じく南下を懸念する日本に、もともと親近感を抱いていた。
ところにエルトゥールル号事件。さらに1904年、日露戦争における日本の勝利である。
この時のトルコでの盛りあがりは空前絶後だったという。日本海軍提督、東郷平八郎の名をとって、生まれた赤ん坊を「トーゴ―」、道路も「トーゴー通り」と名づけられたほど。
筆者の知人で、よくトルコに旅行する人がいるのだが、現在でも日本人とわかるだけで優遇されるほどの親日ぶりであるらしい。教育の力は大きいと、つくづく思う。
さて、エルトゥールル号事件には、知る人ぞ知る後日談がある。
1985年、イラン・イラク戦争のおり、当時のフセイン大統領が、「今から48時間後にイランの上空を飛ぶものは、鳥でも撃ち落とす」と宣言。イランに駐在している各国の外国人は、ただちに自国の空軍機によって救出されたが、当時の日本は自衛隊の海外派遣が認められず、あーだこーだと例によって議論がまとまらないうちにタイムリミットは迫りつつあった。
その時、トルコ航空が動いたのである。200人以上の在留日本人を乗せて、トルコの航空機がイランを飛び立ったのは、フセインが宣告した時刻のわずか1時間ほど前だった。
イランからトルコまでは陸続きで行けるので、自国民の救出には車を使い、航空機での脱出は日本人を優先してくれたのである。
余談だが、エルトゥールル号事件の4年前にあたる1886年には、奇しくも和歌山の串本沖で、社会の教科書などにも載っている、あのノルマントン号事件が起こっている。イギリス人の船長をはじめ乗組員たちが我先にと脱出し、日本人の乗客が残されて全員死亡したという、日本にとっては憤懣やるかたない、イギリスにとってはこのうえなく恥さらしな事件である(それにしても、串本の沖って、海の難所なのだろうか)。
ちなみに今回のネタは、実は4月に書こうとしていたのだが、その矢先に韓国から悲劇的な海難事故のニュースが飛び込んできたため、自粛した。が、もう5ヶ月近くもたっているし、ちょうど台風の季節なので書いた。
2014.9.4
第百二十四回 もしもこんな江戸時代があったら
筆者の本棚には、ザ・テレビジョン文庫より発行の『必殺シリーズ完全豆知識』なる書籍が上下巻で並んでいるが、その下巻68、69ページの見開きに、「これが仕切人当時の江戸の街だ」と書かれて、異様な光景がふんだんに描かれている。どう見ても古代エジプトの遺跡としか思えない外観の「秘羅密度」「須府印玖須」、これらをどう読むかはお任せするとして、作中では、それが江戸郊外に普通に建っており、謎の女性「クレオバ・とら」まで出てくる(第3話『もしもお江戸にピラミッドがあったら』)。
つづく第4話では「狼男」。ハングライダーで空を飛ぶ「鳥人間大会」(第5話)。
第8話『もしも密林の王者が現れたら』では、ターザンならぬ「他左」が登場する。他左は、新仕置人で死神に抹殺された阿藤海(快)。そして頼み人は、彼が飼っていた猿だ!
第9話の「江戸城の菊」は、『ベルサイユのばら』をもじったものらしい。たしか当時『ベルばら』の作者のスキャンダルが話題になっていたはずだが、それを時事ネタを取り入れるというのも悪趣味な話である。
第10話の『もしも超能力でしゃもじが曲がったら」は、もちろんスプーン曲げのパロディで、第11話では勘平を演じる芦屋雁之助に、持ち歌の「娘よ」を歌わせている。
なんというか、時代劇なのに、もう何でもありなのだ。
もともと必殺シリーズには、こういった無茶苦茶な悪ノリのきらいがあったが、ここまでくると、ちょっと度が過ぎているようで「たいがいにおしっ」と思ってしまう。
そもそも各話のサブタイトルが、当時人気だったバラエティ番組『なるほど・ザ・ワールド』のエンディング「もしもタヌキが世界にいたら」のもじりであることは、第1話『もしも大奥に狸がいたら』の時点で明らかだ。
それが面白いと思ってるのか~、と言いたくなる(にもかかわらず全話観てしまったが)。
シリーズ第22作『必殺仕切人』とは、そういう作品なのだ。
殺しの担当は、なんと五人もいる。『必殺仕掛人』などは梅安と左内の二人だけなのに、えらいちがいである。もっとも殺し屋(仕切人)の数が多いだけ面白いとは限らない。
元締は、還暦を超えて、なお上品な色香を漂わす京マチ子(お国)、彼女を補佐するのが高橋悦史(龍之助)、この二人は『必殺仕舞人』以来のコンビである。
加えて、仕事人Ⅳから続投の三味線屋の勇次、小野寺昭、芦屋雁之助がいるのだが、芦屋雁之助の殺し技が最低なのだ。プロレスのリングのようにわざわざロープを張りめぐらせて、ボヨーンボヨーンと相手を吹っ飛ばせてやっつけるという、『仕置屋稼業』の印玄に勝るとも劣らぬ必殺史上の最低技を発揮してくれる。
ストーリー自体はけっこうシリアスな内容が多かったのに、白けるギャグが満載という、このギャップは何なのか、スタッフがどういう路線で制作したかったかわからない作品なのだ。
さて、筆者はこの作品を受け入れるべきなのか。必殺マニアで知られる作家の京極夏彦氏は、シリーズすべて清濁併せのむ姿勢のようだが……。剣劇人ほどではなくても、筆者はそこまで寛容になれない。おそらく江口師範の評価も低いのではないかと思う。
2014.8.28
第百二十三回 道成寺の伝説
読者には受けが悪いのではないかと思われる「紀州シリーズ」。前回は神社だったが、今回はお寺である。
地元では髪が伸びる日本人形で有名な淡嶋神社よりも、道成寺のほうが全国的には知られているかもしれない。安珍と清姫の伝説で。
美形の僧・安珍は修行のさまたげになると断って逃げているだけなのに、嫉妬に狂って彼を追いつめる清姫の執念がすさまじい。怒りのあまり蛇体と化し、日高川を自力で泳いでさかのぼり、道成寺で鐘の中に隠れた安珍を口から吐く炎で焼き殺してしまう。
筆者は高校生のころ、遠足で道成寺へ行ったが(和歌山の高校は、遠足の行き先がシブイのだ)、その時に見た絵巻物語では、安珍の顔がのっぺりとした細目の面長で、それが級友の一人にそっくりだったので、皆で大いにウケていた。また絵巻の最後には、鐘から出され、黒こげになって横たわる安珍の無惨な姿も描かれていたような記憶がある。
それにしても、安珍と清姫が逆の立場だったらどうだろう。男性の場合、それほどの行動に出るとは思えない。嫉妬の感情は、女性のほうが強いという傾向にあるのだろうか。
お寺の人の説明で、清姫が日高川をさかのぼっていく姿には、鬼気迫るものがあり、長い黒髪をくねらせて川を泳いでいく様子が、上から見ると巨大な蛇に似ていたのではないだろうか、という話を聞いて、なるほどと思ったものだ。
今では、日高川はホタルの見どころとして知られる平和な川である。お寺の境内も広々として、いかにものどかだった。701年に建てられたというから、とんでもなく古いお寺だが、山門につづく石段の前には土産物を売る屋台も並んでいて、安珍・清姫伝説は、観光の売りとなっているのであった。
余談だが、山田風太郎の小説『魔界転生』では、この道成寺で柳生十兵衛と柳生如雲斎が対決し、釣り鐘に閉じ込められた如雲斎が、鐘の内側から刀を突き出すという離れ業を見せたりもする。
さらに余談を述べると、筆者らはこの遠足の時、電車に乗って道成寺の最寄り駅まで移動したのだが、途中の停車駅で、向かいの座席に座っていた友人が窓から顔を出し、
「おい、少年隊が歩いてるぞ!」
と真剣な顔でささやいた。若い読者は知らないかもしれないが、「少年隊」とは、当時人気の東山紀之を中心とする三人組のアイドルグループだった。
「マジか」と筆者も車窓から顔を出すと、黄色いヘルメットをかぶった路線工事のおじさんが、三人並んでプラットホームを歩いているのが見えた。もちろん、こっちだって最初から本気にしていない。こんなところをアイドルが普通に歩いているわけなどないのである。
別の駅に停車した時、筆者もやり返した。
「おい、おにゃんこクラブが来てるぞ!」
期待せずに外をのぞき見た友人は、プラットホームにたむろする老婆の集団を目にしたはずである。
高校生のオスガキの会話など、しょせんこの程度なのだ。
2014.8.21
第百二十二回 淡嶋神社のミステリー
8月に入ってから、紀州ネタがつづいている。今回もしかり。淡嶋神社の紹介である。
仁徳天皇のころに始まるといわれる淡嶋神社は、和歌山市の北、加太の海べりにある。停車駅が八つばかり、和歌山市駅発なのに1時間に2本しか出ていないという、ローカル線もいいところの南海電鉄加太線の終着駅が加太である。
案内所のおばさんがくれる地図にしたがって、昔ながらの面影を残す町並みを歩いていく。駄菓子屋や旅館などが軒を連ね、古い街道筋なので道ばたには江戸時代の道しるべまで現存する。濁った川の潮のにおいが強くなり、海が見えてくると、その手前が淡嶋神社だ。
この神社、一風変わったことで有名である。
2月の針供養、3月の雛流し。そして、人形供養だ。
人形供養? 命あるものに対しておこなうからこそ供養なのに、人形という愛玩品を弔うというのも、考えてみれば奇妙な話ではないか。
だが人は、ときに人間以外のものにも「人格」を認めることがある。
動物の擬人化がそれだ。ネズミが出現すると、気持ち悪がったり怖がったりする女の子でも、それが人間らしい表情をして人語を解し、赤い吊りズボン姿で二本歩行をする、すなわちミッキーマウスなるものに変じれば、たちまち親しみが生じてくるというわけである。
女の子たちは、ぬいぐるみや人形といった無生物にも人格を与え、さらには「友だち」として接することもある。
それを笑うつもりはまったくない。豊かな想像力と感受性のなせる業だと思う。
だが、愛着をもってかわいがっていたぬいぐるみや人形も、やがては損傷していく。どれだけ大切に扱っても、経年による劣化はまぬがれない。かならず別れの時がくる。
その時、ほかのゴミを処分するのと同じように、ポイと捨てることができるだろうか。
雛人形などもそうだ。顔の造作まで精巧につくられた人形は、もはやただの玩具や装飾品の域を超えてしまう。文字どおり「人の形」をしているから人形なのである。そして、人の形をしたものを、ただのゴミとして捨てられない感受性は、とても繊細なものだと思う。
そのようにして人間扱いされた人形がやがて心を持つようになるというと、これはSFやホラーの領域だが、淡嶋神社は実際、ある心霊的な現象でも知られている。
ここには「髪が伸びる日本人形」が安置されているのだ。
地元の和歌山では有名な話だが、テレビでも紹介されたことがあるらしいので、ご存じの読者もいるかもしれない。
いかなる故なのか、まったくもってミステリーだが、とにかくそれは実在している。
ただし、そういうオカルト的な興味本位で淡嶋神社を訪れた人は、ガッカリするだろう。
古くなった人形や、招き猫や十二支の干支の置物などがおびただしく(2万体になるという)並べられているのは、たしかに圧倒的な迫力があり、異様な光景である。
が、不思議と暗い雰囲気はなかった。今年の5月、筆者が訪れた日は、明るい初夏の日ざしが満ちあふれ、境内の空気はあくまでも清明であった。
2014.8.14
第百二十一回 足の下に何かがいる!
前回と前々回の文章が改行なしになっていて、そのかわり改行した箇所が1マスあいているのだが、原因は不明。誰のせいでもなくウェブ上の不都合だと思うが、文責が自分にある以上、こういうことに過敏な氏村です。どうか、各文のあいだの1マスあきの部分で改行されているものと思っていただきたく存じます。さて、今回も「まんぷく」につづいての紀州ネタを。
和歌山市の西部に「片男波」という海岸がある。戦国時代、雑賀衆と呼ばれる鉄砲軍団が海運の港にしていたところで、現在では海水浴場になっている。
筆者は十代後半のある夏、その片男波の砂浜で釣りをし、数人で魚を食べていた。
釣った魚を網で焼く。または鍋に放り込む。鍋の味つけは味噌を溶かすぐらい。
ただそれだけの、原始的なまでに簡素な調理だが、なんせ空の下、釣りたての魚をその場で食べながらビールを飲むのだから、爽快さがちがう。
渚からやや離れたところで石を組み、網や鍋が揺れないように固定し、火を焚く。
魚は、もちろんそのまま投入しない。ちゃんと包丁でさばき、はらわたを抜いてから焼いたり煮たりするので、そのための俎板も用意している。
その時、筆者はさばいた魚から抜きとった内臓を、ポイポイと近くの砂浜に捨てていた。
ちょうど波打ちぎわで、ひたすら寄せては返す波が洗いつづけるあたりである。波が引くと、色の変わった砂に、すーっと海水が沁みていく。
ガラ空きの海岸だから、人の迷惑になるはずもない。魚の内臓など、海の生きものにとっては格好の餌なのだ。たちまち他の生物に食われて、処理されるに違いないと踏んでいた。
そのとおりだった。一瞬、目を疑ったのだが、捨てた内臓の周りの砂が動き出したのだ。
モゴモゴモゴ……と、下から押しだされるように盛りあがってきた。そして出てきたのが、小さな虫の群れだ。半透明の節足動物で、うじょうじょ動いて気色悪いったらない。
何なんだこいつらは……と思いながら、ふと考えた。はらわたが落ちてから、虫どもの出現がやけに早かったが、やつらは偶然、すぐ近くにいたのだろうか?
ためしに別の場所に放ったら、同じように周囲の砂が動き出し、虫が出てきた。
さらに反対の位置に捨てても、やはり結果は同じ。もぞもぞと現れてくる。どこに放ってもそれは変わらなかった。とうてい、離れた場所から砂の中を移動してきたとは思えない。
ということは、そこらじゅうにいるのだ。腐肉にたかるおぞましい虫どもは、この砂浜のいたるところに潜み、地表に落ちる血の臭いを待っているのである。
数年前に、テレビの洋画劇場で観た『血に飢えた白い砂浜』というホラー映画を思い出した。ナメクジの化け物みたいな怪物が砂浜の下にいて、アリジゴクさながら砂に漏斗状の凹みをうがち、海水浴にきた客を地下に落としては、片っぱしから食っていくのである。
自分が立っている地盤、そのさらに下に、飢えきった生物たちがひしめいている、という事実には、なにやら足もとが揺らぐようなゾッとする感覚をおぼえた。
だからどうしたって? どうもしません。夏だから思い出しただけで、120回以上も書いていれば、オチのない回だってザラにあります。
2014.8.6
第百二十回 「まんぷく」VS「梨花苑」
極真には焼肉好きの人が多いようである。そして焼肉屋さんというのは、ほかの飲食店に比べて、行きつけの客から「日本一」と評価されることが多いように思える。そんな「日本一」が全国にたくさんあるのは、なんだか微笑ましくていい。 筆者の友人にも、ここは「日本一の焼肉屋」だと太鼓判を押す店があった。連れていかれて、なるほど美味しいと思ったが、あくまでも筆者にとっては「日本で二番」だった。 宮内洋がクールに演じる往年のテレビ番組『快傑ズバット』のように、勝手に「日本で二番」などと評価されては、その店も心外だろうが、筆者の中では、すでに「まんぷく」という日本一が決定していたのだ。 「まんぷく」というのは、筆者の故郷の和歌山市で、50年以上も前から営業している老舗の焼肉屋である。店先に立つ巨大な信楽焼の狸が目印。タクシーに乗って「まんぷく」と告げれば通じるほどで、和歌山市民なら誰でも知っている。 現在の筆者は大食いのほうだが、小学校の低学年のころは、極端な小食だった。ゆえに体つきもガリガリだった。給食もなかなか進まない。最後まで食べられず、残してばかりいたので、給食の時間が苦痛だった。 それが、3年生の時に「まんぷく」に連れていかれ、あまりの美味しさにどんぶりでご飯を食べ、それ以来、大食いになったという、いわば少年時の筆者の食生活に革命を与えた店なのである。 なにより醤油ダレが最高にすばらしい。よくこれほど美味なタレが作られたものだと思うほど圧倒的。もう神レベル。 この店では、やや甘味のある味噌ダレも売りになっており、和歌山の友人や姪っ子たちは、その味噌ダレのほうが好きだと言うが、筆者はなんといっても醤油ダレだ。 だいたい、肉と甘味の組み合わせを受けつけない筆者は、スキヤキに砂糖を入れるのも反対だし、正直に言うと、ほかの焼肉のタレで完璧だと思った記憶がない。でも唯一、この「まんぷく」の醤油ダレには、まんぷく……いや感服つかまつるのだ。 一方、国分寺南口の「梨花苑」を知ってからは、友人に紹介された店は日本第3位に格下げされた。師範をはじめ、道場のメンバー御用達の「梨花苑」は、焼肉屋の多い国分寺の中でダントツなのはもちろん、全国的にも群を抜いていることはまちがいないと思う。とくに、ここの「○メニュー」は申し分なく極上である。 では、「まんぷく」と「梨花苑」は、どっちがいいのだ? と訊かれると困ってしまう。極上対決。これは筆者にとっては、焼肉屋の全日本、すなわち日本一決定戦である。 双方に共通しているのは、よその店に比べて値は張るが、品質のいい肉を使っているということだ。たまに信じられないほど格安の焼肉屋さんを見かけるが、数ヶ月も消費期限が切れた中国産ほどではなくても、怪しくて口に入れる気にはならない。 で、判定の結果は……。本戦では決着がつかず、延長で引き分け、再延長でも引き分け、体重判定でも10キロ以上の差がなく、試し割りの枚数も同じで、どちらかに必ず旗を揚げてくださいという最後の延長戦の結果、僅差で…………。2014.7.31
第百十九回 伝記を選ぶ理由
突然だが、エライ人の人生をまとめたいわゆる伝記というものを読む時、子どもたちはどういう理由で選んでいるのだろうか。 大人なら、多少はその人物に関する予備知識がある。たとえば、ノーベルならダイナマイトを発明したとか、ナポレオンなら軍人でフランスの皇帝になったとかいう、おおまかな知識だ。そういった業績から、もっと深く人物像を知りたいと思って手に取るならわかる。 でも、小学生にとっては、エジソンや徳川家康ほどの知名度がある人物をのぞけば、まったくの「初対面」であることが多い。となると、なにを基準に選ぶことになるのか。 筆者も小学3年生の時に、クラスみんなで図書室に連れていかれ、読みたい伝記を選びなさいと言われたが、そのとき初めて読んだのは『リンカーン』だった。 顔で選んだ。 どの本も、表紙はその人物の肖像画だったのだ。さて誰にしようかと手に取ると、ベートーベンは例のしかめっ面。「トリケラトプス」みたく恐竜の一種のように思えたコペルニクスは、意外にもビートルズのような長髪で、筆者はしばらく女性だと勘ちがいしていた。 ふとリンカーンを見ると、骨ばった輪郭に、頬からあごにかけて黒いひげで覆われている。 (この人は、なんだか面白そうだ) と思った。それに、「カーン」というあたりの冴えた響きが気に入った、ということもある。 我ながらレベルの低い理由だが、筆者の友だちのコソネ君などは、もっとひどかった。 彼が手に取ったのは『ライト兄弟』。 理由は、「はげているから」だという。 おそらくは、兄のウィルバー・ライトの肖像を見てのことだと思うが、初飛行という業績もなにもあったもんじゃない。そもそも、なぜ「はげている」ことで、その人物の生涯を読もうという気になるのか、つながりがわからない。もしかしたら、心の中で「ライト」という名前と「光」を結びつけていたのかもしれない。 名前といえば、ガリレオ・ガリレイなど、親が冗談でつけたとしか思えない名前もある。ガリレイ家の新生男児を、ガリレ「オ」と命名した理由は何だったのか。こういう名前の系譜は古今東西に見られ、剣術家なら伊東一刀斎、推理作家なら有栖川有栖、ちょっとちがうがロマン・ロラン、そして極真の選手にもゲオルギ・ゲオルギエフという人がいたのである。 もっとも、皆が名前や顔で選んでいるとは限らない。筆者が受け持っている生徒たちに訊いてみたところ、歴史の好きな子は源義経や武田信玄といった戦国武将を選んでいたし、野球をやっている子はベーブ・ルースやイチロー(今は在命の人物の伝記もあるのだ)といったように、ちゃんと興味の対象となる理由はあった。女の子たちは、たんに性別の一致だが、ナイチンゲールやアンネ・フランクやヘレン・ケラーなど、女性の偉人が多かった。 ということは、なんらかの形で自分との接点がある人物に、やはり興味をもつものとみえる。 筆者とリンカーンにはまったく接点がないので、一概に言えるものではないが、さて、こうなってくると、「はげているから」という理由で『ライト兄弟』を選んだコソネ君の「その後」が気になるところである。2014.7.25
第百十八回 『ベストキッド』はファンタジーである
いつだったか昼間部の稽古で、たまたま人が来ず、筆者とアジアジだけで練習したことがあった。その時のスパーリングで、誰もいないのをいいことに、アジアジがふざけて片足立ちになり、両手を翼のように左右にあげてはばたくような姿勢を取った。そう、映画『ベストキッド』に出てきた、あの構えである。
ここでいう『ベストキッド』というのは、ジャッキー・チェンが出ているリメイク版のほうではなく、ラルフ・マッチオとノリユキ・パット・モリタが出演しているオリジナル版をさす。
だいたい、新作は出来が悪かった。理由は多々あるが、まず引っこして環境が変わるといっても、国が変わったら意味がないのだ。生活習慣を同じくするアメリカのハイスクールの中でこそ、イジメというシチュエーションが生きてくる、というのが根幹にあるのに。
では、旧作はどうなのだ?
ワックス・オン、ワックス・オフ。そんなことで空手が身についたら世話がないって?
実際、主人公のダニエル・ラルーソも「ワックスがけやペンキぬりばかりやっていて、ほんとに空手の役に立つのか」と内心で疑問と不満をためている。
そんなある夜、ダニエルは、師匠のミヤギに、この場で「ワックスがけ」をやってみろと言われる。同時に、気合いとともに突きを繰り出すミヤギ。それをダニエルは「ワックスがけ」の動きで次々に防いでいく。思いもかけぬみずからの動きに、ダニエルはポカンとする。
我々も空手を学ぶ過程で「これにはどんな意味があるのだろう」と疑問を覚えることがあると思う。江口師範もいちいち説明はしない。いや、説明できるものではない。武道の本質とは、おそらくは言葉ではなく、修練によってしか伝えられないものであろうから。
だが、今の時点でわからなくても、先生を信じて言われたことをやっていれば自然と身についていく。『ベストキッド』はそういった真髄を暗示した「拳と魔法」のファンタジーなのだ。
「鶴の技」にしても同じ。身につければ誰も防げない、などといえば、秘伝中の秘伝、まるで究極奥義のようだ。でも、見たところただの上段前蹴りじゃないか……。
さて、旧大山道場の師範代だった安田英治先生は、「予告前蹴り」で有名だったという。
今から前蹴りを蹴る、と予告し、相手は前蹴りがくるとわかっているのに、それが防げなかったらしい。「半歩崩拳大陸を制す」と言われた中国拳法の郭雲深もしかり。ひとつの技を徹底的にくり返し、修練に修練を重ね、磨きぬくことで達する制御不可能の境地。
「身につければ誰も防げない」技とは、そういう意味ではないかと解釈すれば、『ベストキッド』は、意外にも奥が深い武道映画と見ることができる。
さて、冒頭に戻って、アジアジによる「鶴の技」だが……。
筆者は蹴倒されて転がったのだろうか。そして、「立派だよ。君の勝ちだ」と言って、どこからともなく取りだしたトロフィーをアジアジに渡したのだろうか。
否。中段廻しを蹴ったら、いとも呆気なくスポンと入ったのだ。
無理もないというか、当然だろう。完全に中段がノーガード。蹴ってくださいと言わんばかりに、みずから脇腹をガラ空きにしているのだから。
『ベストキッド』はやはり(別の意味で)ファンタジーだった。
2014.7.18
第百十七回 『空手バカ一代』は実話である
前々回の内容で、やはりグラップラーに怒られてしまった。今度ヤキを入れるとのことである。ちなみに、どの言葉に反応したかというと「キチガイ」だったが、この場合は差別表現ではなく、果敢な闘志に対する一種の評価だと受けとめるべきだろう。あるいは、『獄門島』の了然和尚が、花子の死体発見時に、梅の古木のそばでつぶやいたように、「き」が「ちがっている」だけと解釈していただきたい(といって煙に巻く)。
それから、第110回のカンニングの話で出てきた中2の生徒の名前が、リコと同じ「カトウ」だったのだが、これはまったく関係ない。筆者も気づかなかったが、偶然の一致である。
さて、「キチガイ」と同じように「バカ」もいけないらしいが、これも使い方次第で敬称にもなり得る言葉である。コバンザメが小判ではないように、修飾部が先にくるから、「バカ役者」といえばバカな役者にすぎないが、「役者バカ」といえば、演技のことしか頭にない生粋の役者という褒め言葉になるのである。
そこで出てくるのが、大山総裁の半生を描いた劇画『空手バカ一代』。 連載当時のことは筆者も知らないが、「これは事実談であり…この男は実在する」というオープニングの文句に衝撃を受けた読者は多かったことと思われる。
我々の世代でいえば『北斗の拳』のケンシロウが実在していると言われるようなものである。しかも劇画そのものの戦いが、絵空事ではなく、事実というのだから。
なに、まさか氏村は、あれが実話だと思っているのかって?
ええ、原作者の梶原一騎が「事実談」と言いきっているからには、やはり実話でしょう。
冒頭で、進駐軍の兵士に乱暴されかかった女性を空手技で助けた大山総裁、
「ずいぶんお強いんですのね」
と、その女性に言われ、
「ふふふ…たいしたことはありませんが、十四さいで空手をはじめ…十七さいで初段をとり…いまは二段です」
ずいぶんお強いんですのね、という社交辞令的なひと言に対し、何歳で空手を始め、何歳で初段をとって、今は何段なのか、という細かな履歴まで律儀に答えている。この女性がナニワ娘だったら「ちょっとちょっと、誰がそこまで言えゆうてん!」とツッコミを入れることだろう。
だが、事実なのだ。
若き日の大山総裁が、風になびくほどの長髪だったのも事実なら、
「すまんな、置八子。ついにフウトウはりの内職までやらせることになってしまった」
と奥さんに言いながら、庭で親指二本の逆立ちをしていたのも事実。太極拳の使い手が空中で静止し、頭を下にして突っこんできたのも事実。そう思ったほうが得をする。
こんにちの女子柔道の隆盛を招いた一因に『YAWARA!』があり、かつて女子バレーに人材が集まった背景には『アタックNO1』の存在があった。マンガの力、恐るべしである。
信仰からは、ときに奇跡が生じる。冷めて批判したところで何も生まれない。筆者が初めて『空手バカ一代』を読んだのは大学生のころだったが、これを小学生時代に、実話と信じて読んだ読者は、ずいぶん得をしたことだろうと思った。
2014.7.11
第百十六回 恐るべし、国分寺常連軍団!
国分寺道場には、いろんなタイプの戦い方をする人がいる。そして強い人が多い。筆者がよく顔を合わせる人をあげるなら、アジアジなどはガンガン打って出るファイター・タイプである。この人の強さは、ずばり「考えないこと」にあるように思える。というと、おバカさんみたいだが、余計なことをあれこれ考えていると、そこに恐怖心やためらいといったマイナスの要素を侵入させることになる。考えないアジアジにはその余地もなく、窮地にあっても、結果として死中に活を見出している。この人と筆者は飲み仲間でもあるが、空手を離れたところでも、そういった言動は散見できるのだ。
欠点は、顔面殴打が多いところか。まったく悪いと思っていない口調で「ああ、ゴメンゴメン。わざとわざと」と笑いながら言うのも、もう聞き飽きた気がする。
師範稽古に出席しているスガイズムは、身長187センチ、体重も100キロは超えているだろうか。そんな規格外の巨躯が放つパワーに加え、近年はスタミナも身につけて(しまい)、えんえんと動き回れるのだからスガイ、いや、すごい。
身長など、普段はたいして変わらないように見えても(!)、拳を交えるとその差ははっきりする。さながら「進撃の巨人」といった感じで、ガンガン前に出てくる。
おまけにこの男、よく叫ぶのである。ただでさえイースター島に並んでいそうなコワモテなのに、肉の質量も圧倒的で、さらに気合いが入りまくって雄叫びをあげる。これぞスガイズム(菅井主義)といったところか。試合にも出場しまくっているが、筆者が応援に行くと負けるので、行かないようにしている次第。今では関東チャンピオンである。
スガイズムといえば、カナイズム(仮名)の強さも特筆すべきだろう。どのくらい強いかというと、師範のスパーリング相手が務まるぐらいである。そんな人は、なかなかいない。
高身長で手や足などの末端が大きく、一撃の威力も強烈。才能に加えて、空手に向き合う姿勢が非常に真摯な人だが、スパーなどをしていると、やはりもって生まれた格闘センスを感じる。筆者など歯が立たず、この人には二回、肋にヒビを入れられたことがある。ちなみに、その二回目というのは、今現在である。カナイズムにスガイズム。二人の「イズム」に囲まれてタジタジといった有様なのだ。
常連組といえば、先日、還暦を迎えたカツイチ君も忘れてはいけない。
外見の相似から「総裁」の異名を取るカツイチ君は、出席回数が群を抜いている。仕事をこなしながら、なかなかできることではないと思う。それだけ出席しているのに怪我が少ないのは、ボディが打たれ強いからだろう。
いつだったか、掃除の後で手を洗おうとしたとき、直前に水道を使ったカツイチ君がそのまま立ち去らずに、通路でふり返って筆者の様子を見ていることに気づいた。挙動不審である。もしやと思って水道のレバーをあげてみると、熱湯が出てきた。
「いい大人が、リコの真似をすなーっ」と思ったが、もしかしたらカツイチ君も同じ被害にあったことがあるのかもしれない。
ああ、やはり規定の分量があっという間に尽きてしまった。ヤスオ君や健さんをはじめ、まだ紹介しきれていない個性的な人たちが、国分寺道場には多く在籍しているのだが。
2014.7.5
第百十五回 恐るべし、国分寺レディース軍団!
この春に入門されたメンバーには、女子が多いように思える。そこで今回は国分寺道場の女子部について書きたい。……のだが、たとえばKさんには、最近お目にかかっておらず、実名を出すことも書いていいかどうかも許可を得ていないので、残念なことに紹介することはできそうにない。空手を離れると人柄もよく、見た目も温厚そうなマドモアゼルなのだが、おそるべし、スパーリングでは人の「上げ足」を取る、つまり中段を絡め取って、平然と関節をきめにくる人である。
年少の部類には、「国分寺ブログ」で「リコは強いぞ」と書かれている、あのリコがいる。中学2年生といっても高身長で打撃力もあり、加えて熱心な子である。熱心なのは、もちろん空手に対してであって、学業についてはさだかではない。現に先週も、期末テストの最中なのに道場に来て、かかり稽古をしていた。
通常の稽古では、江口師範が型の意味を説明されるが、その実験台として、よくN氏や健さんが相手をさせられる。技が決まり、ものの見事にひっくり返ったN氏を見て、リコは実に楽しそうに笑う。「箸が転んでもおかしい年ごろ」なのはわかるが、N氏が転がってもやはりおかしいらしい。師範がリコに「もう一回見たい?」ときくと、ためらいなく「見たい!」と答える。気の毒なのはN氏で、そのたびにひっくり返ることになるのである。
ある日、稽古が終わって、掃除も終わって、雑巾をしぼった手を洗いに流しへ行った時、筆者はたまたまリコの次だった。なにげなく水道のレバーを上にあげると、蛇口から熱湯が出てきて「熱っ!」と声をあげた。リコの仕業だった。「立つ鳥あとを濁さず」どころではない。あとに熱湯を残して、「ひっかかったぁ」と言っている。
美内すずえ『ガラスの仮面』の名ゼリフをもじるなら、この場合はさしずめ、
「リコ……おそろしい子!」といったところか。
さて、国分寺の女子部といえば、その突貫ぶりから一部で「キチガイ」と呼ばれている彼女を忘れてはならない。ほんとに空手を始める前は何に時間を使っていたのだろうと思えてくるほど熱心な人である。ちなみに、先の異名は本人の耳にも入っているようなので、名づけた人は用心したほうがいいだろう。
誰のことか、おわかりだろうか。筆者はご本人からここに書く許可は得たが、日ごろの凶暴な振るまいに自覚があるのか、本名をあかすことについては渋られたままままなので、人気格闘マンガから取って「グラップラーめぐ」としておく。偶然だが、「刃牙」の「牙」と、ちょっと似た形の漢字「芽」が使われている名前の人である。
筆者が「グラップラー」と呼べば、「だから、つかんでないって」と、この人は言う。たしかに空手だから打撃のやり取りなのだが、まさにつかみ合いのような戦いぶりなのだ。
そんなグラップラーめぐには、なんと自宅のバスマットを切って「受け棒」まで自作したという空手バカの一面もある。つくづく熱心なことである。だが、受け棒の練習は一人ではできない。となると、誰がその相手を務めているのか、ということになるのだが……。
おっと、もう枚数が尽きてしまった。人物の紹介をしようとすると、どれだけ削ろうとしても、あっという間に進んでしまう。次回は男子部について触れようかと思う。
2014.6.27
第百十四回 あんた、このドラマをどう思う
江口師範のお話では、現在TVKテレビで『必殺仕業人』が放映されているらしい。必殺シリーズの第7作だから、かなり古い作品である。そして、ファンのあいだでは、シリーズ中もっとも陰気な作品としても知られている。たとえば、筆者が持っている必殺サントラCD⑦『必殺仕業人・新必殺からくり人』に付属のブックレットには、
「……愛犬のために身を売る娘、近親相姦スレスレの母子愛、社会からのはみだし者の集落「隠れ里」、生き別れの息子を知らずに殺めてしまう父親、不義を成した妻を斬らんと旅する盲目の侍と幼い娘……」とシチュエーションを列挙しつつ、その暗さが強調されている。
中村主水は、牢の管理や罪人の死体の検分などを役目する牢屋見回りといった閑職に回され、減俸されて、髪はほつれ無精髭を生やし、風貌まで貧乏くさくなっている始末。
2014.6.20
第百十三回 1円玉を拾いますか?
雷鳴が轟き、雹が降りそそいだ13日の金曜日。『稼ぐ人は、なぜ1円玉を大事にするのか?』という本が発売された。版元は、サンマーク出版である。著者の亀田氏は……って、なんか言いづらい。普段の呼び方と違うから。
実は、筆者の友人なのである。その亀田潤一郎「君」は。
彼の著作を当ブログで紹介するのは、初めてではない。
さかのぼって確認してみると、第18回『金がない』という題で、前作『稼ぐ人は、なぜ長財布を使うのか?』のことを書いてあった。2年ほど前だから、かなり早い段階だ。
おいおい、道場のブログを友人の著作の宣伝ツールとして使っているのか、まさかそれで金をもらってるんじゃないだろうな、などと勘繰らないでいただきたい。
このブログのことは、道場の知り合い以外には、いっさい誰にも話していない。よって亀ちゃん(と呼んでいる)にも、いまだに知らせていないのである。
2014.6.12
第百十二回 作文の「型」
街を歩いていると、被災地の動物を支援するための呼びかけを目にすることがある。「被災地の、ワンちゃんや、猫ちゃんに」
という、あのボランティアの方々である。近くを歩いていた男子高校生のグループが、「あのお兄さん、必死なんだよな」と言って、声の張りあげかたを真似していた。
筆者は、そもそも「ワンちゃんや猫ちゃん」とはいかがなものか、と別のことを思った。
鳴き声の擬声語に基づく愛称として「ワンちゃん」とくれば、次に続くのは「ニャンちゃん」であり、普通名詞で統一するなら「犬ちゃんや、猫ちゃん」と並べるべきではないか。
……などと突っこめば、ボランティアの人も大きなお世話だと思うだろう。筆者も、重箱の隅をつつくように「添削」した自分に忸怩たるものを覚えるのだが、これというのも作文のクラスなどを受け持っているせいである。
2014.6.5
第百十一回 最下位クラスの学習(逆襲)
たいていの進学塾では、合理的に学習を進めるため、生徒の学力に応じてクラス分けがなされている。そのレベルは地域によって差があり、校舎の規模によっても顕著に現れてくる。あまり教育熱心でない地域の、さらにマンモス校舎の最下位クラスともなると、あたかも濾過水槽に沈殿した不純物のような様相を呈してくるのだ。
幕末に黒船四隻をしたがえて浦賀に来航したのが「プーチン」だとか、発電の方法に「電力発電」があるとか、それはもう異世界に迷い込んだかのような解答が頻出するのである。
いや、かりに幾多のパラレルワールドが存在していたとしても、プーチンが黒船で開港を求めてきたり、電力によって電力を生じさせているような不条理な世界はないだろう。
言葉だけなら、まだいい。演習中に突然、「痛ッ」と声があがることもある。問題を解きながら、どうして「痛い」ことがあるのか、よくわからない。
平然と鼻クソをほじくっているやつもいる。なぜか、女子に多い。
2014.5.29
第百十回 カンニング110番
テストや問題演習の最中に、生徒のカンニングを発見することがある。社会なら知識の小テスト、国語なら授業内でおこなう漢字テストの時が多い。となりの子の解答を見る、または教材を隠していて正解のページをこっそり見る、という2パターンが主流だが、どういうわけか、ともに女子生徒に多く見受けられるような気がする。
顔は前に向けたまま、黒目だけ限界まではしに寄せて、となりの子の答を懸命に盗み見ていたりする。バレバレなのがおかしい。
むろん男子にもいる。答え合わせの段階で、まちがえた答を消して書き直すという不正行為の常習犯がいたが、彼の場合、無自覚にそうしており、叱っても本人がピンときていないような反応をしていた。
盗みや万引きでも見られるケースだが、病的というか、そういう性癖というか、ごく自然にやっているようなのだ。もちろん中学入試などできる子ではなく、ほどなく辞めていった。
2014.5.22
第百九回 墜ちてゆく人たち ~『ナニワ金融道』
人の不幸は蜜より甘い、というのは本当だろうか。少なくとも、知り合いの場合はそうではない。まったく見知らぬ人でも、あまりに悲惨なケースだと、痛ましさが先にたって面白がる気にはなれない。べつに真面目ぶるつもりはないが、筆者は火事なども見物したいとは思わないのである。
そういえば、筆者の高校時代の同級生に、「火事の見物が三度のメシよりも好き」という女の子がいた。
体重が三十キロ台という痩せっぽっちの子だったから、もともと小食なのだろうが、彼女の場合、「メシより好き」というのは比喩ではなかった。夕食の途中でも、外を消防車が通ったら反射的に席を立って、そのまま家を飛び出していくほどの火事マニアだったのだ。
2014.5.15
第百八回 植芝盛平をご存知ですか
今回も「紀州ネタ」シリーズである。筆者が高校時代をすごした和歌山県南部の田辺市は、合併によって面積こそ広いが、人口8万に満たないのどかな地方の小都市である。
そのJR田辺駅前にある石碑には、「田辺の三人」として、3人の人物画が刻まれていた。
1人は武蔵坊弁慶。生まれ故郷ということで、駅前には僧兵姿で薙刀を構えた弁慶の銅像もあった。もう1人は、かなり前にこのブログでも紹介した南方熊楠。そして残る1人が植芝盛平である。その中で、当時の筆者が知っていたのは、武蔵坊弁慶だけだった。
植芝盛平については、石碑に合気道創始者と書いてあり、筆者はその事実を初めて知った。
ひとつの流儀を開いたということは、それだけでも凄いが、植芝翁が体に触れただけで相手が吹っ飛んでしまうという神技を知ったのは後年のこと。手を使わなくても、接触するだけで人が撥ね飛ぶのだから、筆者などには理解できない境地である。
2014.5.8
第百七回 テレビを見るという非日常
今回の提出が5月8日。ゴールデンウイークが終わった直後だが、読者の方はこの連休をどう過ごされていたのだろうか。筆者はわけあって実家に帰っていた。実家ではテレビがつけられており、新聞も毎日届けられる。日ごろテレビも見なければ新聞もとっていない筆者にとって、それらに接することは、一種、非日常の体験といえた。
テレビといえば、うちの父がNHKの職員だったので、今でもよくNHKの番組にチャンネルが合わせられている。たとえば、日曜日の昼にやっているのが「NHKのど自慢」。
2014.5.1
第百六回 八代将軍吉宗
久々の「紀州ネタ」シリーズである。徳川幕府の八代将軍であり、享保の改革の立役者である吉宗公のことだ(前回に比べて、なんと無難なネタであることよ)。
時代劇ファンにとっては、松平健ふんする『暴れん坊将軍』シリーズや、NHK大河ドラマ『八代将軍吉宗』などでお馴染みかもしれない。
筆者はどちらもきちんと観たことはないが、亡くなった祖母が『暴れん坊将軍』の大ファンだった。祖母が夢中で観ていたのは、同じ紀州人の親しみもあったのだろうか。いや、紀州どころか、うちの本家(実家)の氏神様にあたる神社が、刺田比古神社といって、その昔、徳川吉宗が赤ん坊のころに捨てられていた神社なのである。
2014.4.24
第百五回 あるこ~る警報
書いていいものかどうか……。と若干の迷いを覚えながらも、書く。かつての国分寺道場の飲み会のもようである。
ご存じない方も多いだろう。酔いが回れば脱ぐのが当たり前という、そんな時代もあったのだ。
もちろん特定の人物に限られている。今はもう道場を去った人だし、かりにA先輩として本名は伏せておくが、その人は指導員でありながら、飲み会の「いじられ役」になっていた。
「泣き上戸」や「笑い上戸」という言葉があるが、さしずめこれは「脱ぎ上戸」とでも言うべきか。とにもかくにも、飲んだら脱がずにはおさまらないのである。
それも上着やシャツの一枚や二枚といったかわいらしいものではない。
2014.4.18
第百四回 あるこ~る注意報
ずいぶん前のことだが、小田急線沿いの遊園地のポスターに、「もうこりごりだ また乗ろう」というキャッチコピーがあった。写真では、若い男女がジェットコースターに乗った後らしく、髪が逆立ち、引きつった表情で立っている。とんでもない迫力だったのでこりごりだが、また乗りたいと思うほど楽しかった、ということらしい。
そのポスターに向かって、酔っぱらいのオヤジがツッコミを入れているのを、筆者は見たことがある。へべれけになってふらつきながら、ポスターを指さし、
「なぁにぃ(ヒック)……もうこりごりなのに、また乗ろうって……なんだぁ!」
と説教をしているのである。
ポスターと人間との区別がつかないほど酔いつぶれているくせに、論理的な矛盾を指摘しているのがおかしかった。
2014.4.10
第百三回 廃校の夜
お遍路で四国を歩いていた時のことである。歩き始めて3日目、88箇所の数ある難所のひとつ、その名も恐ろしき「遍路ころがし」を通過し、12番札所の焼山寺にたどりついたのは、お寺が閉まるぎりぎりの5時直前。
それから山をくだって、とりあえず寝場所を探さなければならなかった。
もちろん旅館やホテルなどではない。資金は限られているので、できるだけ倹約する必要がある。寝袋とテントを背負って歩いているのは、野宿するためだ。
この日は、なんと廃校に泊まった。天候が荒れてきたからである。いきなりザーッと雨が降り出し、雷まで鳴っているので、雨宿りをする必要があった。でも民家すらまばらな一帯で、建物らしい建物がなく、とにかく最初に見つけた屋根のあるところが廃校だったのだ。
2014.4.4
第百二回 読んでから観た
『ワールド空手』最新号の表紙が、いつもより洗練されている。ということでメディアの話。70年代のことだから大昔だが、角川書店が書籍と映画のタイアップをはじめたころ、「読んでから観るか、観てから読むか」というキャッチコピーがあった。
読者の方は、小説が映画化された場合、原作を先に読むか、映画を先に鑑賞するか、どっちだろうか。筆者は前者だが、この場合、映画がイメージ通りでないことを覚悟しなければならない。
でも、中には原作をきちんと理解した上での、見事なまでの映画化作品もある。たとえば『ゴッドファーザー』、たとえば『ジャッカルの日』、たとえば『羊たちの沈黙』など。
新しい映画では『永遠の0』もそうである。筆者は、ずっと放置してあった原作をようやく読むと、12月公開の映画がまだ上映されているのを知って、ソッコーで観にいった。
2014.3.27
第百一回 第一歩
かつてミュージシャン志望の友人Mが、ことあるごとに「俺はサラリーマンじゃない」と語っていた。大学を卒業して、某企業に入社したころのことである。筆者とMは新卒採用された新入社員、つまりお互いにサラリーマンであり、それ以外の何者でもない立場だったが、Mは会社勤めをしながら、その事実を認めていなかった。
「サラリーマンじゃないとして、では何なんだ?」と訊いても、答は返ってこない。さすがに社会人になったばかりの身で、夢見る中学生のような言葉は口に出せなかったのだろう。
高校時代からジョン・レノンにあこがれ、大学時代はビートルズのコピーバンドを組んでいたMの過去を考えれば、そう言いたくなる気持ちも察することはできるが、あろうことか彼はミュージシャンになるための具体的な行動を起こしていなかった。
2014.3.21
第百回 100物語
「ごじゅうに……ごじゅうさん……ごじゅうし……ごじゅうご」50をこえた。
「ごじゅうろく……ごじゅうしち……ごじゅうはち……ごじゅうきゅう」
なにをしてるのかって? ママがお風呂の中で、数をかぞえているんだ。
ぼくも、今年で五歳になったからね。かぞえる数は100にのびた。
船のオモチャで遊んで、体を洗ってもらいながらお話しして、最後に100をかぞえるまで湯船につかる。そんで、ママがいいって言ったら、お風呂から出る。
2014.3.13
第九十九回 『もうひとつの独り言』99もない謎
江口師範の最新ブログを読んで驚いた。走り方ひとつを取って、これだけの説明ができる師範って、よその道場ではなかなか見当たらないんじゃないか。春の入会キャンペーン期間だが、入門を考えている方は、その道場の指導内容が気になるところだろう。国分寺道場のクオリティはご覧の通りである。
さて、話は思いきり変わって、我が家の本棚には『アガサ・クリスティー99の謎』といった本があるけれど、『もうひとつの独り言』も今回で99回を迎えたことで、初めて当ブログについて語ってみたい。
もちろん99も謎はない。せいぜい筆者の氏村って誰なのか、とか、たまに出てくるアジアジというのは何者なのか、ランランとかカンカンとか(古い)ホワンホワンとかいたからアジアジもやはりパンダの仲間なのだろうか、といったことぐらいだろう。
2014.3.7
第九十八回 このブログは仕事なのか
何年か前、タクシーで税務署に行こうとしたら、新米の運転手さんが税務署の場所を知らず、結果として別の建物まで連れて行かれた経験がある。確定申告の時期である。おおかた脱サラでタクシードライバーに転向した人なのだろうが、「この時期に税務署の場所を把握していないなんてな」と閉口したものだ。
お金を払っている側としては、当然、それなりの商品価値を要求するものだから、プロの運転手としては不甲斐なく、勉強不足だとそしられても致し方ない。
仕事に対する責任感にズレがあったのだろう。そしてこういったズレは、職業として道場にたずさわっている先生と門下生の間にも生じることがある。
2014.2.27
第九十七回 おととい来やがれ、剣劇人
「なんだ、また必殺ネタか」と、お嘆きの貴兄に。申し訳ない。また必殺ネタです。だが、今回は「この作品はすばらしい」という内容ではなく、その反対である。
取りあげるのは第29作『必殺剣劇人』。シリーズの長い歴史の中には『必殺渡し人』や『必殺商売人』といった、タイトルからして観る気の起こらない作品もたまにあるが、『剣劇人』など、その最たるものであろう。
2014.2.21
第九十六回 つわものどもが夢のあと……
毎年、2月の初旬がすぎると、2、3日は「つわものどもが夢のあと」といった、一種の虚脱感まじりの醒めた感傷に囚われる。進学塾の講師をしている筆者にとって、中学受験の本番となる2月1日~6日あたりは、一年間の仕事の山場であり、教え子たちの決戦の時である。合否の結果が出て、難関校などの実績も出て、てんやわんやして、それが過ぎると、なにやら祭りの後のような深閑とした状態に陥るのだ。
受験が一段落すると、生徒が校舎に集まり、先生らがジュースやお菓子を用意して歓談する合格祝勝会というものがある。中には受験に惨敗した子もいるのだが、その子に、
「や~い、落ちたのに来てやんの!」
2014.2.13
第九十五回 寒波襲来
スティーブン・キング原作、スタンリー・キューブリック監督の映画『シャイニング』のような生活がしたい、と思ったことがある。といっても、斧をもって追いかけたり、はたまた追いかけられたりしたいわけじゃ、もちろんない。雪に閉ざされた館に引きこもっていたいのだ。
本格ミステリでは、このシチュエーションは定番である。雪に閉ざされ、陸の孤島と化した山荘で、連続殺人事件が起こる。犯人はこの中にいる、というやつ。
2014.2.6
第九十四回 「急増中」が急増中
テレビも観なければ新聞も取っていない筆者は、もっぱらネットニュースを通して世の中の出来事を認識している。ネットニュースでは、大勢に影響力のある重大事件でも些末な出来事でも見出しの大きさが変わらないので、興味のあるネタを選んでクリックする。そんな記事の中で、いつ頃からか「急増」もしくは「急増中」という見出しが、それこそ急増して目を引くようになった。
ようするに「急増中」と書けば、その見出しをクリックする人が多い、ということだ。なるほど、「急増」という言葉には、いかにもこれまでの流れとは異なる新たな現象が発生しているようで、興味の喚起力がありそうに思える。でも、読んでみるとたいしたことはない。たいていは営利目的の記事に終始していることが多い。
2014.1.31
第九十三回 帝国の崩壊
肩がゴリゴリに凝っているのは疲労のせいだろうか。満足に読書時間がとれない中、毎日、ほんの10ページ程度のかたつむりペースで読んできた小島一志氏の著作『大山倍達の遺言』を、先日ついに読了した。言うまでもないことだが、大山総裁亡き後の極真の分裂状態は、惨憺たるありさまである。いったい何があったのか、どういう経緯で現在のようになったのかということを、内部にいる者として知りたくなるのは当然のこと。
その要望に応えるのに、綿密な取材と資料に裏づけされたこの作品は十分な一冊だった。極真と関係のない人が、ワイドショー的な興味本位で読んだとしても面白く感じると思う。
2014.1.23
第九十二回 一筆啓上、後編が見えた
引きつづき『仕置屋稼業』のネタを。第一話『一筆啓上、地獄が見えた』の冒頭、夜店の雑踏の中で、市松がヤクザの親分を暗殺するところを、たまたま中村主水が目撃してしまう。扇子で手元を隠して竹串でズブリ。同時に市松も、主水に見られたことを知る。殺しの腕を買って、市松を仲間にスカウトしようとする主水だが、市松はそんな主水をも闇に葬ろうとする。自分の仕置(殺し)を見た者は、生かしておけないのだ。
しかし、紆余曲折あって主水と手を組むというのが第一話だが、そのラストシーンがまた秀逸だ。船宿で、市松が近江屋・利兵衛をあざやかに殺す。が、その庭先で、一人の少女がそれを見ていたのだ。
殺しを見られた!
2014.1.17
第九十一回 一筆啓上、前編が見えた
必殺シリーズのマニアの中には、当時の放映日に合わせて、毎週その回の作品を視聴するという物好きがいるそうな。などと他人事のように書いているが、かくいう筆者もその一人である。必殺シリーズさえあれば、ほかのテレビドラマがなくても一生観るものに困らないくらいのファンなのである。
今回取りあげるのは、シリーズ第6作『必殺仕置屋稼業』。
必殺の中でもベストにあげるのが、いつか書いた『新・仕置人』だとするなら、二番目が『必殺必中仕事屋稼業』と争うこの作品である。そんなわけで、DVDを全話買ってしまい、去年の7月4日から毎週観つづけて、この1月に最終回を迎えたわけだ。
2014.1.9
第九十回 朝イチで朝市
和歌山市の西部に築港があり、12月30日の早朝にそこの朝市へ買い出しに行くのが、我が家では、年末の恒例となっている。早朝4時に起きて車に乗り、ガラすきの道路を飛ばして行く。まだ夜明け前だから、真っ暗で、寒い。でも市場では、すでに賑やかな声が飛びかい、熱気に満ちあふれている。
買うのは、正月用の料理に使う魚介類である。伊勢エビやアワビ、サザエ、モンゴウイカ、鯛、マグロ、カニ……などなど、豪勢この上ない。
これは、帰省した筆者をもてなしてくれているのではなく、大晦日から3日までいる妹の家族、もっといえば筆者の姪にあたる三姉妹のためである。ようするに、両親は孫が可愛くて仕方ないのだ。ふだんは質素に暮らしていて、ここぞとばかりに大盤振る舞いをし、筆者はそのご相伴にあずかっているわけだ。