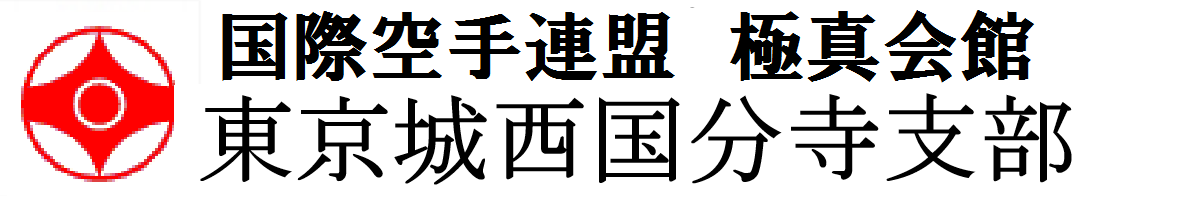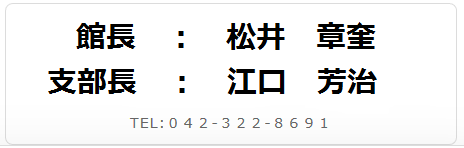もうひとつの独り言 2015年
2015.12.24第百九十一回 あと10回?
「毎回、よくネタがつづくよね」とアジアジに言われるこのブログだが、筆者の引き出しだって、もちろん無尽蔵というわけじゃなく、ネタもいつかは尽きる。
つまり最終回が来る。では、どのタイミングで終わればいいのか、となると、やはりキリのいい数字の回にしたほうがすっきりしていいと思うんだがな、筆者としては。
たとえば200回とか。
ということは、おお、この回を含めてあと10回だ。次の木曜日は大みそかなので、一回とんで更新は年明けになるでしょう。
江口師範のひと言で始まったこのブログも、なんだかんだで200回もコンスタントに書いたとなると、さすがにもういいのではないかな、筆収め(筆じゃないけど)しても許されるのではないかな、と思ったりしつつ、2015年も暮れようとしている。
2015年といえば、録画してあった『必殺仕事人2015』をようやく観たのだが、江口師範はご覧になったのだろうか。
またその話題かよ、と当ブログの読者諸兄には思われそうだが。
ジャニーズで固められた仕事人なんか観る気もしない、と思って拒んでいた筆者だが、思いきって観てみると、意外によかった。
たしかに映像から骨太さは失われていたが、平尾昌晃のBGMが健在で、随所に『新仕置人』や『仕舞人』、『新仕事人』など過去のサントラが「新作」の中に流れると、それだけで嬉しくなる。
それに、エンドクレジットに出ていたが、監督が石原興だったのだ。
この人は撮影を担当し、照明の中嶋利男と共に、ずっと必殺シリーズを支えてこられた人なのだ。テレビドラマなのに、映画用の16ミリを惜しげもなく使ったあの光と闇の映像美を演出された(それこそ)仕掛人なのである。当然、往年のシリーズのいいところを知り尽くしているわけだ。
ちなみにミニ特番『必殺を斬る』のインタビューで、「必殺についてひと言」と言われた石原氏が、ぽつんと「青春を返せ」と口にされていたのがやけに面白かった。
でも、そんな名職人の石原氏だけに、昨今の時代劇の軽薄なデジタルクリアビジョン画面についてはどうお考えなのだろう、とも思った。なにもかもクリアな画像は、深みのある時代劇には合わないと筆者などは思うのだが。
……と、こんなふうに必殺をネタにするのもいいが、残された作品も限られている。話題を元に戻すと、このブログはいつになったら終わるのだろう。
本音を言うと、ネタはつづくと思う。たぶんだけど。元々たいした内容を書いてるわけじゃないし。……となると、別の要因で終了することになるかもしれない。たとえば氏村が誰であるか、正体がバレてしまうとか。……それじゃ、まるで必殺の最終回だ。
そんなこんなで今年も終わります。
よいお年を。(大谷先生ふうに言うなら)201回目がないことを祈りつつ……。
2015.12.17
第百九十回 終わりにて候
必殺シリーズの魅力の半分は個性的なキャラクターにあるといっていい。直情径行の熱血漢、クール、向こう見ず、軟派、硬派、人情家、主水のようなすれっからし……まで、多様である。その中でも随一の異色の殺し屋といえば、第4作『暗闇仕留人』の糸井貢(いとい・みつぐ)ではないかと、筆者などは思う。どのように異色かというと、インテリなのである。秀才の蘭学者。こういうタイプはシリーズ中でもごく数人しかいない。その中でも、もっとも知性を押し出したキャラクターなのだ。
糸井貢を演じるのは、石坂浩二。高野長英の門下生だったという設定で、師匠の逃亡を手助けした罪で追われる身でもあり、今は芝居小屋で三味線を引いて表の生計を立てている。
前髪を額に垂らし、書生風の着流し姿で、いかにも線が細い。知的で繊細な風貌からして殺し屋(仕留人)には見えず、貢という名前からして現代的である。なるほど、石坂浩二はこの役にうってつけの俳優だと思える。
作品の背景は幕末であり、海上には居並ぶ黒船が遠望できる。
「どうも世の中の動きってのは、俺たちが考えてるよりずいぶん早いらしいな」と主水さえ言っているのだから、この『暗闇仕留人』自体がシリーズ中の異色作であろう。
最終回「別れにて候」で、貢は内面の葛藤を仲間たちに吐露する。
「何のために生きてるのか。何のために、今まで人殺しをしてきたのか」
「けっ。ちょっとばかり学があるからって、訳の話からねえことぬかしやがって。何のために生きてる? 決まってるじゃねえか、食うためだよ」
と、怪力坊主の大吉などは、こんな悩みをはなから受けつけない。
「前から考えていたことなんだ。俺たちは今まで何をしてきたんだ。世の中は動いている。少しでも世の中良くなったか? 俺たちに殺られたやつらにだって、妻や子がいたかもしれないし、好きなやつがあったかもしれないんだ」
蘭学を学んだ身であり、激動する日本の未来を案じる貢は、ここにいたって自分たちがやってきた仕留人稼業に疑問を抱き、幕府の要人を標的とする次の仕事にためらいを見せる。
「今度殺ろうという相手、松平玄蕃守、その身辺はたしかに清廉潔白とはいえないかもしれない。しかしな、彼の幕閣における見識、国を開こうという勇気は、今の幕府にはなくてはならぬものなんだ」
気乗りしないながらも「これで最後にさせてもらう」という条件で引き受けた貢。だが、最終回のクライマックス、寝込みを襲った殺しの現場で、松平玄蕃守が土壇場で言い放つ。
「わしを殺せば、日本の夜明けが遅れるぞ!」
この言葉に、貢は思わず手を止める。そして、その一瞬の隙を突かれ、返り討ちに斬られてしまうのだ。必殺シリーズ初となるレギュラー殺し屋の殉職である(島帰りの竜は生死不明)。
リアルタイムで観ていた視聴者はショックだっただろう。松平玄蕃守はその後すぐ中村主水に斬られ、父をなくした娘(西崎みどり)は、雪の降りしきる江戸の街を旅立っていく。
玄蕃守の娘である彼女は、貢が絵を教えていた生徒でもあり、演じる西崎みどりが歌う主題歌『旅愁』がここで鎮魂歌のごとく流れる。西崎はこの回がゲスト出演だった。
2015.12.10
第百八十九回 マクドナルドの老婆
マクドナルドの凋落がとまらない。ファーストフード店の代名詞のような存在だったのに、今年のうちに190店舗も閉鎖してしまうというから驚きだ(ちなみに、このブログは次回で190回である。関係ないけど)。
筆者が知っている店も二つ潰れた。国分寺でも北口にあった店が再開発の流れで取り壊され、それ以降も復活する見通しがないのだから、ちょっと淋しい。
もっとも、中国産の鶏肉の事件は、食品産業としては致命的だったと言える。信用とは一回きりのもの。あんなことが発覚しては、誰もチキンタツタなど食う気にならないし、鶏肉以外の食材にも杜撰な管理が類推できるというものだ。
それと「職業体験」とやらで小学生を厨房に立たせるマックアドベンチャーという企画。最初聞いたときはびっくりした。まさか一般の客に出すんじゃないだろうな、自分なら絶対に嫌だけど、と思ったら、さすがに親が責任を持って食べるらしい。それにしてもママゴトじゃあるまいし、みずから価値を下げているとしか思えないのだが。
と言いつつ、筆者も年に七、八回ほどの割合でマック(関西では「マクド」という)を利用している。筆者の年齢だと、神戸でマクドを初体験したころの、あこがれと感激の記憶があるのだ。今では、ハンバーガーもポテトも、あの大ざっぱな塩分の加減がいい、チープさが売りだ、と思っているのだが、これじゃけなしているのか褒めているのかわからないか。
今はなき国分寺店で、ずっと前にお婆さんの店員さんを見かけた。バイトといえば若い女性のイメージがあるせいか、制服を着たお婆さんとマックの組み合わせが珍しかったので覚えている。彼女の、パート先にあえてマクドナルドを選んだという、その心理が面白かった。
(仕事のほうは大丈夫かな。ちゃんと運んでくれるだろうか)
と思って待っていたら、案の定、運んできたのはいいが、番号札をおいたテーブルの横をヨロヨロと素通りしていった。やっぱり大丈夫じゃなかったみたい(笑)。
これは別の店だが、筆者が席に着こうとしたとき、となりの席に座っていた上品なお婆さんが、ニコリと微笑んで会釈したことがあった。0円のスマイルは店員のものだけではなかったのだ。
筆者も会釈を返した。それから食事して、席を立つとき、ふと気づいた。
となりのお婆さんは、依然として姿勢よく座っている。狭いテーブルの上には何もない。ハンバーガーやドリンクも。番号札も。トレーや食べ終えたものすらない。ただ座っているだけ。
これはどういうことなのだろう? 店を出てから、やや気になった。
もしかすると、あのお婆さんは、生まれて初めてマクドナルドに入ったのではないだろうか。そうして普通のレストランのように「店員が注文を取りに来る」のを、ただ待っていたのかもしれない。それなら、筆者は声をかけて教えてあげるべきだったのではないか。
ファーストフード店を利用するには、彼女は育ちが良すぎたのだ。隣席の見知らぬ客にも会釈するほどに。
中学校の国語の教科書にも載っている吉野弘の詩『夕焼け』の「娘はどこまでいっただろう」ではないが、お婆さんはあのままいつまで待っていただろう。
2015.12.3
第百八十八回 言葉が通じないのは何故か
前回の文章が途中で切れていたことにお気づきだっただろうか。最初「他山の石」のところで終わっていたので、変だと思われたかもしれない。その後訂正していただき、今アップされているのは完全稿になっている。前回といえば、かつてのタケルのような「言葉が通じない」人は大人にもいる。むしろ大人のほうが多いようにも思われる。もちろん外国人のことではない。音声を認識でき、母国語である日本語の意味を理解できるのに、話す内容が通じない人のことだ。
ひとつ思い出すのは、筆者が昔、友人に紹介された居酒屋でのことである。
ある時、カウンターで飲んでいると、そこのマスターが、「となりの人に話しかけろ」と言う。
フレンドリーな雰囲気で、常連客同士が気楽に語り合う店だったが、筆者はべつに見知らぬ人との触れ合いを求めているわけではなかった。
一人で飲むのが好きなだけで、もちろん淋しくもない。むしろ触れ合いなど、わずらわしいと思うほうだ。
「考えごとをしながら飲んでるから、人と話さなくていい」
と言っても、それがマスターには通じない。
「いい人だから」
と、何度も言う。厚意のつもりで提言してくれているらしい。
いい人だから話しかけろと言うのは、しかし理解できない論理である。正直言って、アホじゃないかと思った。
くり返すが、筆者は一人で飲んでいても淋しくはなかった。むしろ孤独を楽しんでいた。基本的に自己完結できてしまう人間なのである。ほかの人に話しかけないのは、単にその欲求がないからであり、また失礼にならないよう遠慮しているだけだった。逆に自分が見知らぬ人に気安く声をかけられたら不快に思うタイプだから、というのもある。
そのことを、言葉を尽くして説明したのだが、まったく通じなかった。
うっとうしくて、もうその店には行かなくなったが、見方を変えれば、そこは「触れ合いの場」かもしれず、だとすると筆者のほうが異物であり、場違いだったとも言える。
言葉が通じない理由は、独りよがりな思いこみのせいだろう。
マスターは筆者のことを「この人は、人と話したいのに、話しかけられないのだ」と思いこんでいたのだ。そしていったんそう思いこんだら、もう論理は通じない。
よく言われるように、人は「自分の信じたいことを信じる」らしい。
この例でいうと、マスターが信じたかったのは「自分の親切」、すなわち「いいことをしている自分」であろう。だから言葉による筆者の主張は耳を素通りし、真実をさしおいても、孤独な客に仲立ちしてあげているという「善意」で頭がいっぱいになっていたのだと思う。
そう、善意の勘違いである。悪気はない。が、こういう人が真の味方にはなりえることは、まずない。尊重がないからだ。噛み合わないのは、相性が合わないからである。
ただし、若い人にとって親は例外だ。親の思いこみはむしろ当然で、若いころはわずらわしくても、結局、余程のことがないかぎり見捨てることは(たぶん)ない(と思う)。
2015.11.27
第百八十七回 こんなやつがいた3
もう7、8年ほど前の話だ。手に包帯を巻いている生徒がいたので、どうしたのかと理由を聞いてみると、「空手のスパーリングで怪我をした」と言うではないか。塾の近くに極真(別派)の道場があり、彼・タケル(小6・男子)はそこに通っているという。なんていう先生に教わっているのか聞いたら、筆者の知っている人だった。
その指導員の先生は、江口師範の後輩に当たる方で、たまに近くで顔を合わせたときには、しばし立ち話をして「江口先輩はお元気ですか」などと聞かれることもあった。
思わず懐かしくなり、「その先生、知ってるよ」とタケルに話した。もちろん休み時間、個人的にである。でも筆者が空手をつづけていることは、生徒から見ると専任の先生じゃないように思われそうなので、仕事に支障が出ぬよう、もう辞めていることにしておいた。
ところが、このタケルには通じないのである。人の話をまったく聞いていない。
筆者はその当時、緑帯だったが、タケルは勝手に黒帯だと思いこんでいた。人前で授業などをしていると、立派なように見えるのかもしれない。人間の思いこみの力というのはえらいもので、ちがうと言っても通じない。
「そんで、どこの道場に通ってるの?」と、また平気な顔で聞いてくる。
「だから今はやってないって言ってんだろうがあ!」
と思わず大声を出しそうになった。もう訂正せずに黙っていたが。
こちらの話す言葉が、ことごとく聞き流されるのである。もちろん授業内容もだ。こんなにイライラさせられることはない。
得意技は何か、と聞いたら、「ナントカナントカナントカ蹴り」と、まったく聞いたことのない複雑で長い蹴りの名称を、真顔で答えた。そんな子である。
だが、このタケルのお父さんは、とある大企業の重役であり、なんでも「統括部長」という役職に就いているそうで、タケルはそれが自慢だった。
で、みんなの前で誇らしげに語ったのだが、やはり本人は正しく認識しておらず、
「僕のお父さんはね、トンカツ部長なんだよ」
と言って、みんなの爆笑を買ったのだ。マンガのような話だが、実話である。
タケルは、それこそトンカツのように丸々と肥えた顔で、きょとんとしていた。笑いものにしちゃダメだ、とみんなを責めることはできない。誰だって笑いたくもなるわ。
感心されるはずが、爆笑されて意味不明のタケルは、なぜ笑われてしまったのか理解できなかったのだろう。家に帰って、お母さんにそのことを話した。
そしたら、お母さん、どうしたと思いますか?
なんと、会社の組織図を書いて、息子に持たせたのである。プライドのより所である統括部長がどれほどエライ立場なのかを、皆に知らしめずにはいられなかったものと思われる。
さて、このトンカツ部長の息子からも、我々はなにか学べることがあるだろうか。「我以外皆師」であり、「他山の石」という言葉もある。
なにか学べることが……………………どこかに………………………………………………………えーっと ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………。
2015.11.19
第百八十六回 こんなやつがいた2
「2」があるということは、当然「1」もあったわけで、このブログをさかのぼってみると、2年前のちょうど今ごろ、第84回に書いていた。そのシリーズの2年ぶりの第2弾。念のためにいうと、リアルタイムの出来事は避けている。個人情報保護のため、もちろん本名は伏せているし、5年から10年を経た賞味期限切れのネタである。
といっても、たいした内容じゃない。名前は、ひさの(仮名)。小5のくせに茶髪の女子。そして鋼の神経の持ち主である。
筆者が廊下を歩いていて、出会うと、なぜか後をついてくる。歩きながら話しかけてくるのだが、それが他の教室に入ってもつづく。平気な顔でよそのクラスにまで入って話しつづけるのである。よくこんなことができるものだと思う。
授業中も、一番前の席から話してくる。学校でこんなことがあったとか、私はこういうことが好きだとか、授業内容とまったく関係のないことをだ。
授業後に生徒が教室に残って、話を聞いてほしがることはよくあるが、この子の場合、授業中に、ほかの生徒をまったく無視して、自分と筆者しか見えていないような話しかたをする。
手紙のやり取りはもちろん厳禁だが、この子はどういう神経をしているのか、筆者に渡したことがある。問題演習の最中、一番前の席から、下を向いて問題を解いているふりをしたまま、パッと教卓に折りたたんだ手紙をおいた。あけてみると「今日は私の誕生日です」……云々といった他愛のない内容だ。
注意しても、まったく聞かない。授業前に「今日やったら島流しだから」とあらかじめ宣告したこともあった。島流しというのは、ほかの子の迷惑になるような場合、一番うしろのポツンと離れた席に移動させて反省を促す、という措置である。
神妙にうなずいていたのに、授業になると、やっぱり話しかけてきた。すぐ忘れてしまうというより、自分をコントロールできないらしい。で、予告どおり「島流し」にした。 普通ならこれだけでも消沈し、反省するのだが、ひさのはうしろの席で、いっぱしのお姉ちゃんのように足を組んで、手の甲をこちらに向け、指をくねらせていた。
まったくこたえていないのだ。というか、全然平気。「島流し」にされている自分の立場がわかっていないようである。これには呆れを通りこして、失笑するしかない。
したたかで、ふてぶてしいという言い方もできるが、このワイヤーのような神経の持ち主であるひさのからも、なにか学べることがあるかもしれない。「我以外皆師」であり、「他山の石」という言葉もある。
人は苦境にあるとき、落ち込みがちになる。かりに運命に人格をもたせたとき、人はその運命の神を呪うだろう。だが、落ち込めば好転からは遠ざかる。
これはいじめっ子の心理を考えてもわかる。余計にイジメはエスカレートする。格闘技でも効いたそぶりを見せれば、さらに攻められることを我々は知っている。
皮肉なことに、悪いことをした子でも、萎縮するより、カラッとして悪びれない子のほうが印象がいいのである。ならば「運命」に対してもそうできたら……とはいっても、ひさののように強靱なハートで世の中を渡っていくことは、普通、なかなか難しいのだが。
2015.11.12
第百八十五回 華岡青州の家
去年は、和歌山市出身の作家・有吉佐和子の没後30年とかで、彼女の作品がいろいろ売り出されていた。筆者は同郷なのに、いまだ読んでいなかったので、この機会に何冊か買い、そのうちの一冊『華岡青州の妻』(新潮文庫)を今月になって読んだ。華岡青州は、和歌山(紀州藩)出身の医者だが、なにをしたかというと、江戸時代に、世界で初めて全身麻酔による手術を成功させた人物である。
だが、この本は名医・華岡青州の伝記ではない。
題名からもわかるように、青州の妻・加恵が主人公である。その加恵はなにをしたのかというと、封建時代のことだから、ほかの多くの女性のように、ただ夫の仕事を支えたのだった。
が、その支え方がすごい。華岡青州が開発した麻酔薬「通仙散」(劇薬成分を含む)の効果を確かめるため、なんと、みずから人体実験の試験体になったのだ。
さらに、加恵には強大なライバルがいた。青州の母であり、加恵にとっては姑にあたる於継である。於継もまた実験体を希望する。こんな形で、嫁と姑の戦いが展開するのだ。
かつて『2時のワイドショー』で、よく「スイカをぶつける鬼嫁」ふうのサブタイトルが(今でもやってるのだろうか)あったが、それどころの話ではない。加恵は八日間も意識を失って寝たきりになる。そこまでして、自分のほうが夫(もしくは息子)の役に立とうとするという、すさまじくも風変わりな意地の張り合いなのである(この意味でラストは象徴的である)。
有吉佐和子は、一作書くごとに倒れて入院するほど入魂のエネルギーをつぎ込んで執筆した作家だが、読んでみると、意外に一般ウケしそうなメロドラマ風の展開だった。メロドラマでなければ、少女マンガだ。天才外科医・華岡青州をめぐる妻と姑との「女の戦い」が、緻密な心情描写たっぷりに描かれていて面白い。一般受けといえば、市川雷蔵(青州)、若尾文子(加恵)、高峰秀子(於継)という豪華キャストで映画にもなっているらしい。
世界初の全身麻酔手術の成功で、華岡青州の名声は不動のものとなった。ラスト近くでは、杉田玄白からの手紙も紹介されている。すでに80歳になっていた大家の先達が、53歳の青州に対して「教えを乞いたい、交流を持ちたい」という旨の内容を丁寧に書いており、有吉佐和子は「謙虚」という言葉で評しているが、筆者には、この向上心と研究欲こそ杉田玄白の凄味であろうと思われる。青州も感激したようで、玄白からの手紙は華岡家の家宝のように保存されたらしい。ちなみに筆者は、この手紙の実物を見たことがある。
ええッ、どこでだ? と思われるかもしれないが、なんのことはない、和歌山市の郊外にある「華岡青州の里」に、愛用していた日用品の数々とともに展示されているのである。資料館の近くには、青州の自宅(および診療所)もあり、これも見学することができた。 広くて、驚くほど機能的な家であった。仕事のため合理的に活かせるよう、あらゆるところに独創的な工夫が見られる。やはり、ただ者ではないのだ(当たり前か)。
それにしても、もし手術のときに麻酔がなければ……と考えただけでもゾッとする。筆者が知っている人の中で、麻酔なしの手術をみずから希望したのは、江口師範だけである。そんなことができない普通の人のために、世界に先駆けてやってのけた華岡青州の研究と仕事は、あらためて偉業であると思う。
2015.11.5
第百八十四回 世界大会を2倍楽しむ方法
本家ブログの江口師範の文章に触発されて、ここでも世界大会ネタを。試合そのものはもちろんだが、世界大会にはもうひとつの楽しみ方がある。
出場選手の名前である。なんせ、世界中から集まるのだから、日本人にとっては「変!」と感じるような響きの名前を目にすることも珍しくない。
ずいぶん前で、どこの国の人かも忘れたが、「ジャッキー・チョン」という選手がいた。
「ゼッケン○○番、ジャッキー」
と、声高々にその名が呼ばれ、つづけて、「チョン」とアナウンスされた瞬間、会場がいっせいに笑いに包まれたことを、筆者は覚えている。
失礼じゃないか、人の名前で笑うなんて。
かのアクション・スターをちょっともじったような名前が、そんなに可笑しいのか。日本まで海をこえてやって来て、いざ試合場にあがるというその時に、自分の名前で観客に爆笑された人の気持ちにもなってみなさい……とは言えない。筆者もつられて笑ってしまったから。
失礼といえば、「ビル・ポリクロノプロス」の名前をアナウンサーがなめらかに読めず、舌をもつれさせてしまったことである。
「ビル・ポリクロノプロス」……たしかに、トリケラトプス(恐竜)かロプロス(バビル二世のしもべ)みたいで、日本人には馴染みのない人名だが……。舌を噛んだことを「ご愛敬」と感じる反面、プロが事前に練習していなくてどうする、とも言いたくなる。
そういうあんたは言えるのか、と問われれば、ええ、筆者は言えます。会場でひそかにつぶやいていたから。
変な名前をみると、なぜか口ずさんでしまいたくなるのである。よって前回出場した「イウヌソフ・スルタナメトカン」の名前もそらんじられる。今回のネタで、過去の大会に出場した選手の名前は、何も見ずに書けるほどで、こうなるともう「変な名前マニア」である。
人の名前を笑いのネタにすることが上品な行為ではないことを承知の上で、さらにつづけると、ほかにも「ゲオルギ・ゲオルギエフ」という選手がいた。このブログの伝記の回(第119回)でも触れたが、ガリレオ・ガリレイみたいな名前である。
「ユーゲウズ・ダディズダグ」も忘れがたい。舌を噛みそうな名前だけでなく、スキンヘッドにぼうぼうたる顎髭という風貌も個性的だっが、黒澤浩樹(先生)との戦いを前にみずから「戦意喪失」を表明し、棄権してしまった。
今回のトーナメント表を見ると、「アイルトン・マルティンコレニャ(14番)」「バツシグ・ムンクエルディン(22番)」「ファルーク・トゥルグンボエフ(32番)」「モハマド・ベジャティアルデカニ(39番)」「クリスティアン・ヴァレリウラドゥ(64番)」「キザケダトゥ・モハナンサナル(122番)」あたりが、アナウンサー泣かせの名前であろう。()内はゼッケン番号である。
ほかにも個人的に面白いのは、「アミン・アジミ(130番)」。「アジアジ」ならぬ「アミアジ」である。それと、また出た「ガリレオ・ガリレイ」風の「マクシム・マクシマウ(135番)」。
このように、世界大会は、試合のほかにも出場選手の名前で楽しめるのだ。
観戦に行かれる方は、彼らの活躍と名前をお楽しみください。
2015.10.29
第百八十三回 10月の最後の日
10月も終わろうとしている。ブラッドベリが愛した「たそがれの国」。その晦日は万聖節前夜、すなわちハロウィンである。この時期、街を歩けばショッピングモールはカボチャをくりぬいた異様なデザインの装飾であふれている。
ここで話は映画の『ハロウィン』にうつる。1978年製作。ジョン・カーペンター監督のホラー映画だ。
これは、不死身の殺人鬼を登場させた最初のホラー映画ではなかろうか。
もしかしたら、もっと前にもあるかもしれないが、とにかく初めて見たときは新鮮だった。映画館ではなく、テレビの洋画劇場で見たのだが、ラストでゾクゾクした記憶がある。
思えば、80年代というのは、ホラー映画の円熟期でもあった。70年代に『エクソシスト』や『オーメン』や『サスペリア』や『ゾンビ』といった新境地が開拓され、さらに不死身の殺人鬼を扱ったシリーズ物が制作され始めたのが80年代だった(ように思う)。
不死身の殺人鬼といえば、『13日の金曜日』シリーズのジェイソン・ボーヒーズ。『エルム街の悪夢』シリーズのフレディ・クルーガーと並んで、この『ハロウィン』シリーズの「ブギーマン」ことマイケル・マイヤーズが有名だが、筆者はブギーマンが一番好きだ。
なんといっても、あの不気味なマスクがいい。目の穴がぽっかりとあいた白いハロウィンマスク。凶器はシンプルに長大刃のナイフ。ジェイソンが何作目からアイスホッケーのマスクをかぶるようになったかは知らないが、『13金』は、やはり1作目がダントツだと思う。大部分の流れは平凡だが、どこが秀逸かは、ご覧になった人ならおわかりだろう。
『ハロウィン』の1作目も、ほとんどは平坦に進んでいく。10月の末日が近づくと、街角に白いマスクをかぶったマイケルの姿がちらつき、それがブキミで徐々に緊張は高まっていくが、大きく展開するのは終盤、ハロウィンの夜になってからである。
家に侵入したブギーマン(マイケル)を、主人公の姉弟はかろうじて倒すが、もう大丈夫だという姉に、幼い弟がひと言「ブギーマンは死なないんだよ」と言う。伝承の怪人としてそうなっているだけで、なぜ不死身であるかの説明は一切ない。それが、かえって怖い。
そして、抱き合って恐怖の余韻に耐える二人の背後で、倒れていたはずのブギーマンが、むくりと上体を起こし、白いマスクをかぶった顔をこちらに向けるのだ。
もうひとつ特筆すべきは、音楽である。印象的な曲が多いホラー映画のサントラの中でも、筆者にとってはこれがベスト。『ハロウィン』が魅力的なのも、この音楽の力によるところが大きいのではないか。しかも、この曲、なんとジョン・カーペンター監督がみずから作曲しているという。
ところで、『ハロウィン』は周知の通り、子供たちがお菓子をもらいに近所の家庭を回るという西洋の行事をモチーフにした作品だが、日本ではそれをもじって、秋田県の伝統行事を題材にした『なまはげ』という映画を作ったらどうだろうか。
大みそかの夜、赤いなまはげ仮面をかぶった怪人が各家庭を回り、悪い子を食べていく。……ヒットしないこと請け合いである。
2015.10.22
第百八十二回 どこまでがイジメか
筆者が中学二年生のとき、クラスで「画鋲おき」が流行った。「画鋲おき」というのは、席を外しているクラスメイトの椅子の上に、さっと画鋲をおいておく悪戯である。画鋲は、教室の後ろの掲示板からぬき取って使う。
流行ったといっても、ほんの一時期だけ、男子のうち何人かが、はしかにかかったようにこの遊びに熱中していただけで、ほとんどの者はくだらないと思って見ていたはずだ。
遊び、というには、しかし語弊があろう。椅子に画鋲をおかれ、それに気づかずに座れば、とがった先が尻に刺さってしまう。当然、痛いし、わずかだが傷を負う。
そう考えると、悪戯と呼ぶには、悪質すぎる。実際、普通なら、れっきとしたイジメにちがいない。少女漫画の世界でも、「シューズに画鋲」は嫌がらせとして描かれる。笑いごとではすまされないのである。
不思議なのは、同じことをやっていても、その場の空気、互いの心的距離、そして相手の受け取りかた次第で、冗談にもイジメにもなるという点だ。
なんだか「セクハラ」に通じるものがある。それじゃ、やらないにこしたことはないのだが、そこは中学生のオスガキたちである。異様に盛りあがっていた。
たとえば、Aという男子が、ある生徒Bの椅子に画鋲をおいている。Aはバカだから、Bの反応が気になって仕方がない。気づかずに座るかな、とニヤニヤしながらBを眺め続けているが、そのAの席には、すでに誰かが画鋲をおいているのだ。Bのほうに気を取られながら、後ずさりして自分の席に座ったAは、飛びあがっていた。それを見ていた皆は爆笑。
重ねていうが、画鋲おきは本来イジメである。このような愚行がブームになっていた教室は、例外的なパターンだと思っていただきたい。
こんな状況だから、当然、椅子に座るときは気をぬけない。 休憩時間ばかりではなく、授業が始まる直前、「起立」「礼」のタイミングで、うしろからサッと画鋲をおかれることもあるので、座るたびに確認しなければならない。まさに生き馬の目をぬく教室であった。
といいながら、筆者もやった。標的は前の席の女子だった。「あんたはこんなことをしてるけど、こうしなさい」というように、なにかにつけていつも説教してくる憎たらしい子なので、この際だから報復のターゲットに選んだ。となりの席の友だちが「おまえ、それはヤバイだろ」と言っていたが、「起立・礼」のタイミングで、パッと椅子においたのである。
さて、前の席の女子はどうなったか?
実は、どうにもならなかった。彼女が腰を下ろす瞬間、筆者もヒヤヒヤしたが、いったいどういうわけか、何事も起こらなかった。つまりまったくの無反応だった。
理由はわからない。授業中ずっと考え続けたが、答えは出ず。 もしや無痛症だったとか。それとも、座る拍子に、スカートで画鋲が弾き飛ばされたのだろうか。でも床にも見当たらなかった。遠くまで転がった可能性も否定できない。あるいは、ものすごい確率で、ちょうどケツの穴に収まっていたのだろうか。
真相は藪の中。いまだに謎のままである。
2015.10.16
第百八十一回 文学の秋
天高く、氏村肥ゆる秋。……というのは、ただの稽古不足か。とにかく秋が深まっている。
芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、という言い方は、もう死語かもしれないが、今回のネタは、読書の秋ということで、有名な文学作品の書き出しに触れてみることにする。学生時代に、文学史の授業などで紹介されたやつである。
「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」(夏目漱石『草枕』)
普通、山道を登りながら考えることといえば、「腹減ったなあ」とか「頂上はまだかいな」とか「おっ、やばい。蜂だ」……といったところだが、さすがに明治の高等遊民はちがう。山登りしながら、こんな哲学的な、難しいことを考えている。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」(川端康成『雪国』)
あまりにも有名な一節。筆者の妹はこの冒頭を読んで、「なんで『そこは雪国であった』にしないのかな」と言っていたが、冗談じゃない、そんなことをしたらブチコワシである。
「永いあいだ、私は自分が生まれたときの光景を見たことがあると言い張っていた。それを言い出すたびに大人たちは笑い……(略)」(三島由紀夫『仮面の告白』)
三島なら実際にあり得そうに思える。ちなみに筆者の学生時代、往年の三島と東大で同級生だった教授が聞かせてくれたエピソードによると、ナントカという難しい講義のノートを平岡(三島の本名)に借りたところ、なんと、その講義内容を古文に直して書いてあったという。
「私は、その男の写真を三葉、見たことがある。」(太宰治『人間失格』)
若い頃の三島に「僕は太宰さんの文学が嫌いなんです」と面と向かって言われた太宰だが、なるほど、ともに自伝的要素の強い作品でありながら、誕生の瞬間によって世界が開ける三島とは対照的に、写真の描写から人物の内面に向かうという導入を取っている。
同じく太宰の『走れメロス』では、
「メロスは激怒した。」
と、のっけから短いセンテンスの中でまともに心情語を用いるという大胆さだ。「なんで激怒したんだ?」と読者の興味を引く手法であろう。ちなみに、似たような書き出しに、
「山椒魚は悲しんだ。」(井伏鱒二『山椒魚』)がある。
だが、とにもかくにも、もっとも強烈なインパクトを与える冒頭は、これである。
「山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした。」(志賀直哉『城の崎にて』)
さらりと書いている。……超人だ!
2015.10.1
第百八十回 CD大量投棄の謎
これは自分の生活圏内で遭遇したミステリーである。かなり前の話だ。一年はたっていないが、今年の2、3月のことだったと思う。
その日、筆者はマンションの一階にあるゴミ集積場で、CDが大量に捨てられているのを見つけた。手提げの紙袋に入れて「燃えないゴミ」のコーナーに置かれている。
聴かなくなったCDを整理し、まとめて処分することなら、べつに不思議ではない。
だが、それらは新品だった。どれもパッケージングされたままの、つまり封もあけていない状態。しかも、すべて同じアルバムで、数えてみると100枚以上ある。
これはどういうことだろう。業者なら専用のルートで処分するはずだ。
新品のCDを100枚以上買い、一度も聴かないまま開封もせずにごっそり捨てるとは、いったいどんな事情があってのことなのか、筆者は考え込んでしまった。
読者には、この謎が解けるだろうか。ちなみに、このCDは、AKB48のアルバムだった。と書けば、「なるほど」と納得する方もいらっしゃるかもしれない。
筆者は、なんとかこの真相を解明しようと考えていたのだが、どうしてもわからずじまいだった。一枚持って帰って聴いてみようかとも思ったが、なんとなく薄気味悪かったし、日ごろから歌謡曲を聴く習慣もないので、結局そのまま放置しておいた。
ところが、この話を道場ですると、スガイズムとキャニオンがたちどころに答を出したのである。
筆者がどれだけ推理してもわからなかった謎を、聞いた瞬間に当たり前のように解かれては甚だ面白くなかったが、「握手会」の知識がなかったのだから無理もない(と自分を弁護)。
いや、握手会というものがあることは知っていたが、そのシステムについては疎かったのだ。
ご存じない人のためにいうと、AKB48の握手会に参加すれば、メンバーと握手ができるのだが、それには参加券というものが必要になる。その参加券がCDについている。パッケージが破られていなかったので、たぶん包装の外側にあるのだろう。
AKB48といえば、筆者でも知っているほどの国民的アイドルグループだから、ファンの数を考えると、CDについている参加券だけでは足らず、抽選が行われるはずだ。それで選ばれる可能性を高めるために、熱心なファンは100枚でも買うのだ。
うーん、なんとボロい商法だろう。CDは、よほどの高額所得者でなければ、安い買い物ではない。そして普通は(聴くだけなら)2枚もいらない。それを100枚も購入する人がいれば利益も跳ねあがる。
ファンにしてみれば、願ってもないイベントだと思う。あこがれのアイドルと至近距離で会い、握手して、ちょっと言葉も交わせるのだ。人は満足のためには金を惜しまない。
企画した側は、コスト的には無料にも等しい参加券を封入しておけばいい。労働するのはメンバーの女の子たちだ。たかが握手といっても、相手は何百人もいるし、いわば長時間の接客である。対人の労働は消耗するもの。心身ともに大変な仕事にちがいない。
これは筆者たちが、石川秀美がどうだ菊池桃子がどうだ、と言っていた頃にはなかったシステムである。アイドルの形態も変わったものだ。……って今ごろ思うのは遅いか。
2015.9.24
第百七十九回 好きなアニメキャラは?
筆者が高校生のときである。英語のグラマーの授業で、「○○ほど、○○なものはない」という構文が取り扱われたとき、担当の教師が、「○○ほど可愛いものはない」という例文を作ってみるように言った。その○○のところに、自分が一番可愛いと思う女の子の名前を入れろ、というのである。
共学校だったが、ほとんど男子生徒向けのウケ狙いであり、今ならクレームスレスレの出題かもしれない。
筆者は、ふと隣の席でせっせと鉛筆を動かしているF君のノートをチラ見した。
(なに? N…A……U…)
誰のことだろう、と思った。
NAUSICAA。
F君が書いていたのは「ナウシカ」だった。
宮崎駿のアニメ『風の谷のナウシカ』の主人公(ヒロイン)である。
同じクラスでありながら、ほとんど会話らしい会話を交わしたことがないF君だったが、英語教師の気まぐれな出題に「ナウシカほど可愛い女の子はいない」と答えた彼は、おそらく「本気」だったのではないかと推測する。なにしろスペルを知っているぐらいなのだ(筆者はこれを書くにあたって調べた)。
この世に実在する異性など眼中にない。二次元の美少女キャラクターこそ恋の対象。……という、このF君の感覚は、今でいう「萌え」の走りだったのかもしれない。
アニメのキャラクターで誰が好きか、というような話題は、若いころなら酒の席で持ち出されることもあるだろう。
こういう場合、筆者は「どう答えたらウケるか」という観点から答えるので、いささか本音とは異なる結果になる。
たとえば、男性キャラクターなら、「タラン」と口にしてしまうのである。
しかし「タラン」と聞いて、いったい誰がピンとくるだろう。『宇宙戦艦ヤマト』に登場するデスラー総統の側近なのだが、デスラーの横に立っているだけでほとんど個別の出番がなく、忠実さが売りの人物なので個性を発揮する場面も皆無に近い。だが、同じ脇役でも「シュルツ(ガミラス冥王星前線基地司令官)」とか「ミル(白色彗星帝国監視艦隊司令)」といっては「狙いすぎ」であり、あくまでも「タラン」というあたりが絶妙な匙加減なのである。
女性キャラクターも、やはりウケ狙いで答えてしまう。
たとえば「スターシア」はどうか。ほとんど出てこないではないか。最終回近くでようやく本編に登場するが、大半は宇宙空間に浮かぶ正面からとらえたバストアップの静止画なのである。これも「テレサ」と言っては駄目で、やはり「スターシア」でないと面白くない。
あと、「003」という手もある。『サイボーグ009』のヒロインだが、固有名詞で「フランソワーズ・アルヌール」と答えるよりも「003」というほうが面白い。なにしろ「数字」だからな。……などとバカなことを書いているうちに今回も枚数が尽きた。
読者の方なら、同じ質問にどうお答えになるだろうか。
2015.9.17
第百七十八回 漫画のキャラクターの年齢は!?
このブログを書いている筆者(氏村)は、いったい何歳なのかと、たまに年齢を訊かれることがある。前回のネタは昭和の遊びであり、話題に出てくる漫画やアニメも古いものばかりなので、ある程度は推測できるだろう。筆者が漫画・アニメの『ちびまる子ちゃん』より年下だといえば、子どもたちは驚くが、これは主人公のまるちゃん(小学3年生)より年少という意味ではもちろんなく、作者であるさくらももこ氏の3年生当時として明確に設定されている時代背景から割り出したものであることは言うまでもない。
もっとも、漫画・アニメの登場人物は基本的に年を取らないので、見始めたころは年上だった『サザエさん』の磯野カツオや、それとほぼ同い年と思われる『ドラえもん』の野比のび太などは、たちまち追い抜いてしまった。
だいたい、漫画やアニメのキャラクターは、みんな若すぎる。
以前、天野ミチヒロさんと飲んでいて『ガッチャマン』の話題になり、主要登場人物たちの年齢を聞いて、その若さに驚いたものだ。
皆、十代後半なのである。高校生(ジュンペイをのぞく)にあたる年齢の「少年少女」たちが、学校にも通わず世界の平和を守っているのだった。
『ヤッターマン』のガンちゃんとアイちゃんなら中学生というのもわかる。ああいう絵柄だから(それでもボヤッキーは二十代半ばらしい……)。
だが、『ガッチャマン』のような渋い劇画タッチでは、ケンはともかく、コンドルのジョーなどは、小学生のころに見ていると、ひどくダンディーでオジサンじみていた。
あんな高校生がいるのか、と思う。ましてやミミズクのリュウなど、完全に中年だと思っていたのだが……。
『宇宙戦艦ヤマト』の古代進や島大介も、宇宙戦士訓練学校の学生という設定上、十八歳であるらしい。筆者が小学生だった当時は、大任を背負いながら成長していく若者として見ていたが、彼らの年齢をとっくに追いこした今になってみると、相当に違和感がある。
かの『ルパン三世』に登場する銭形警部は29歳とのことだが、あの貫禄で二十代とは驚きである。だいたい29歳で警部に昇進していることからしてすごい。 『カリオストロの城』では、銭形をさして「さっすが昭和一ケタ」というルパンのセリフがあったが、現実世界に照らし合わせると、銭形警部の年齢は、今年で80歳から89歳までのあいだということになる。
『マカロニほうれん荘』のトシちゃん25歳も、連載当時はかなり大人に思えたが、これも通りこした。その次の目標(?)となると、同じく『マカロニ~』のきんどーさんと後藤熊男(苦悩する40歳)であり、そのまた次はエンディングで41歳の春を歌われた『天才バカボン』のパパが浮上してきたのであるが、さらに先となると、もう見つからないのである。
と思っていたところ、筆者は見たことがないのだが、子どもたちに人気の『妖怪ウォッチ』に出てくる「コマさん」というキャラクターが、なんと300歳をこえているらしい。
これはさすがに追いこせそうにないな……。
2015.9.10
第百七十七回 昭和の遊びアレコレ
意外なことに、今どきの小学生も「メンコ」を知っているらしい。といっても、駄菓子屋で売られているのを買って、路上や公園で日常的にバシバシやり合うというのではなく、「体験学習」を通して知るらしいから、感覚としては、遊びというより「教養」に近いのだろう。どこそこの施設から借りるとなると、メンコを二枚重ねて張りつけ、より強化するズルい工夫など、知らないにちがいない。
筆者は昭和の当時、再放送をくり返されていた『ドロロン閻魔くん』を持っていた記憶があるが、今のメンコにはどんな絵柄が描かれているのか興味がある。
一方、爆竹を知っている子どもは少ないので、これは禁止されたらしい。小さなダイナマイトをつなぎ合わせたような形状が男児には魅力的だと思うが、たしかに近所迷惑にはちがいない。
使用例といえば、無情にもこれをカエルの口もしくはケツに挿入して「爆殺」する同級生もいたが、筆者はそれが嫌だったので、いらなくなったプラモデルを吹っ飛ばすぐらいが関の山だった。
禁止されたといえば、ローセキも今の子は知らないようだ。漢字では「蝋石」と書くのだろうか、地面に書く白い棒状の石(のようなもの)である。
ようするに、女の子が地面にマルを書いて「ケンケンパッ」をして遊ぶのに使ったやつだ。落書き自体を見かけなくなったので、これも禁止になったものと思われる。
筆者は小学3年生の時、家の前からスタートして、近隣のブロックをローセキの絵で一巡するという「大作」を完成させた。何を描いたかというと、人体の消化器官だった。
すなわち、口から入って、しばらくは食道を下り、大きなスペース(胃)に入ると溶けないうちに早く脱出し、ぐねぐねと曲がりくねった小腸、少し太めの大腸を通って、最後はみんなでウンコになってキャーキャー言いながら肛門から出てくるという遊びである。
我ながら、ろくなことを思いつかない。子どもの遊びとはいえ、門前に胃や腸などを描かれて、ご近所の方はさぞ迷惑だっただろうと反省する。ローセキも禁止になるわけだ。
スーパーカー消しゴムも流行った。あれは誰が最初に発見し、始めたのか、シンナーの瓶につけて、一晩寝かせておくと、どういう理屈か知らないが、キュッと二回りほども縮んでしまうのである。しかもカチカチに固くなっている。
その変化がフシギで面白かった。この固く縮んだスーパーカー消しゴムを、スイッチ操作で飛び出すボールペンの尻で弾き、机の上から落とし合うのだ。シンナーはすぐ子どもに売られなくなったから、つかの間の流行だった。
ガチャガチャのカプセルも昔からあった。汚い話で恐縮だが、これにおしっこを詰め、空に向かって放り投げる。どこに落ちてくるかわからないので、みんなでワーッと言って逃げる。地面に落ちて炸裂し、運悪く足にかかってしまう子もいて、このスリルがたまらなかった。
こうやって思い返してみると、昭和の子どもたちは、遊びの道具をそのまま使うのではなく、自分たちでなんらかの工夫をほどこして遊んでいたことがわかる。
まあ、ろくな工夫じゃないにしても。
2015.9.3
第百七十六回 まぼろしのブルートレイン
いつのまにか、ブルートレインがなくなっている。正確にいつ廃止されたのか知らないが、これでひとつ、子どものころに抱いていた「ブルートレインに乗る」という夢がなくなった。
もっとも、その夢自体ずっと忘れていたぐらいなので、今さら悔しがることでもないのだが、そんなささやかな夢ぐらい、大人になってから実現させておくべきだったとも思う。
筆者には小学生のころ、ブルートレインの追っかけをしていた期間がある。友だちに誘われて始めたのだが、自分の中では珍しくまともな趣味だった。
ご存じない方のために言うと、ブルートレインというのは「寝台特急」のことで、青い車体に白いラインが引かれ、長距離間の移動に使われる寝台つきの列車である。
その当時、筆者は兵庫県の西宮に住んでいた。最寄りは阪急の夙川駅だが、線路でいえばJRのほうが近い。駅はないが、マンションからJR山陽本線の線路が見えるのである。
そして一カ所、今はもう無理だと思うが、そのころは線路内に立ち入れる穴場があった。
「あさかぜ」や「さくら」、「はやぶさ」「みずほ」といった東京から九州に向かう列車は、かならず兵庫県(山陽本線)を通る。よって、筆者と友だちは、草木も眠る深夜の一時すぎ、カメラをもって、線路の脇に待機することになるのである。
通過する時刻の見当は、時刻表をもとに算出した。
「大阪をこの時刻に発車すると、西宮のこの地点を通るのは何時何分ぐらいかな」
その計算は当たっていた。くり返すが、あたりが寝静まった深夜。一時をこえていたことは記憶している。二人して固唾を呑んでスーパースターの到来を待っていると、はるか彼方まで見通せる線路のずーっと向こうに、ぽつんと輝くヘッドライトが見えてくるのだ。
「来た! あれは、何時何分に大阪を出た『はやぶさ』や!」
この時のドキドキ感は今でも覚えている。
我々は興奮しきって撮影したが、後から考えると、フラッシュをたいているので、運転士さんには迷惑だったことと思う。プワァン、と音を鳴らされたが、あれは子どものファンに対するサービスだったのか、それとも警告だったのか。
そのころは全国的にブルートレインのブームで、撮影に躍起になるファンの行動が社会問題にもなっていたそうだ。筆者たちの学校でも、線路に置き石をするバカがいて、それが問題になり、危険だということもあって電車の撮影は禁止された。
近づかなければいいだろうと思って、線路に近い友だちの家の窓辺に腰かけ、夕方に通る『明星』や『彗星』といった特急列車を撮影していると、たまたま下の通りを歩いていた校長先生と目が合ってしまい、気まずくなったこともあった。
そんなこんなで情熱が冷めかけた九月の朝、大型の台風が接近しているとかで学校が休みになって、筆者は友だちと、線路わきの公園で遊んでいた。
すると、いきなり『さくら』が通っていったのである。いつもなら学校にいる時間なので、午前に通るとは知らなかった。予期せぬ出現によるサプライズと、ヘッドマークをまともに近くで見た興奮もあって、大感激した。これが、筆者の最後に見たブルートレインとなった。
2015.8.27
第百七十五回 ひと夏だけの別荘
最近の子どもは「蚊帳」を知らない。「トトロで見た」などと言うので、宮崎アニメを通してどういうものかは知っているようだが、現物を見たり、触れたり、中で寝たりした経験はないらしい。
蚊帳で思い出すのは、前に書いた湯浅の祖父母がもっていた別荘である。
母方の祖父母はとくに裕福ではなかった。定年まで缶詰工場で日々働き、贅沢とはほど遠い暮らしをつづけていた二人だった。その祖父母が別荘を持ったのである。
場所は湯浅のやや南方、由良か戸津井と呼ばれるあたり。見あげると、山沿いの大きな道路が通り、展望台のような円形のドライブインがあって、夜はハワイアンが流れていた。当時の田舎の道路には、こういうトロピカル風のドライブインがよくあった。
ある年の夏、筆者は妹と、そして最近たびたびこのブログに登場する神戸のイトコ姉妹といっしょに、保護者である祖母に付き添われて、その別荘で一泊したのだ。
別荘、と聞いてどんな建物を想像されるか知らないが、おそらくその想像は外れている。
いやもう、ボロッボロの、二分後に倒壊してしまいそうな家屋だった。
平屋の木造で、築年数は見当もつかない。戦火をくぐり抜けてきた可能性すらある。ガスはもちろんプロパンで、電気や水道も果たして通っていたかどうか……というレベルの「別荘」なのだ。おそらくは知り合いから、タダ同然に譲り受けたのではないかと思う。
それでも楽しかった。やさしいお婆ちゃんがいて、子ども四人で泊まるのだから。
田舎で思いきり遊んで、スイカを井戸で冷やして、蚊取り線香をたいて、蚊帳の中に並んで寝て……という「昔ながらのニッポンの夏」そのものの過ごし方である。
井戸の水はキンキンに冷たくて、スイカはよく冷えた。そんなに冷たいのに、上からのぞき込むと、イモリが何匹も赤い腹を見せて泳いでいたのを覚えている。
それにしても、子ども心に、蚊帳はなぜあんなに楽しかったのだろう。家の中でテントのように張られ、中に蚊が入らないよう、すばやく滑りこむ。それだけで盛りあがった。一種の基地遊びやママゴトに近い感覚だったのかもしれない。
夏を存分に楽しめた一泊だったが、この別荘にはひとつ、重大な問題があった。
トイレがなかったのだ。
ほんとに、いったいどういう了見で建築された家屋なのか、今さらながら知りたくなる。
で、どうするのかといえば、外でするしかない。片手にトイレットペーパー、片手に小さなスコップを持ち、夏草の生い茂るすき間の土に自ら穴を掘り、用を足し終えると、土をかぶせて埋める。自分の始末は自分でつける、というわけだ。
筆者は男だし、小学校低学年だから平気だったが、従姉妹たちはけっこう育ちがよく、とくに姉のほうは高学年だったから、これにはかなり抵抗があったようだ。
無理もない。ハワイアンの流れる円形のドライブインの客に見下ろされていては、落ち着いていられないだろう。
ちなみに、この別荘、利用したのは一回だけで、翌年の夏には話題にものぼらなかった。
早くも祖父母が手放したのか、それとも…………やはり倒壊してしまったのか。
2015.8.20
第百七十四回 今年の夏も甲子園
実家に帰省していたので、久々にテレビを見た。夏の甲子園をやっていた。
高校野球100年目に当たるとかいう今年、大物ルーキーとしてひときわ話題にのぼり、注目されていたのが、早稲田実業の清宮幸太郎選手である。
早実といえば国分寺の学校だから、街中でたまに野球部員を見かけることもある。それもあって、今年の夏は高校野球を観戦した。
夏の甲子園といえば、筆者が小学生のころは、和歌山県の強豪校として箕島高校が有名だった。
そのころのは、野球のルールや用語をよく知らなかったし、ピッチャーのマウンド上での動作が不可解だったので、さほど熱心に見ることはなかった。
ピッチャーが、ベンチやキャッチャーのサインに対し、首をふったりうなずいたりするやり取りを見ると、小学生ながら不遜にも「早く投げろ」と思っていたのだ。
今では、前述の清宮などが打席に入ると、相手のピッチャーの表情から心理をさぐる楽しみまで心得ているのだが、当時は野球というスポーツの面白さを、よくわかっていなかったのである。
だから、野球を見るより、釣りに行くほうが好きだった。
ある年の夏休み。叔父さんの車で釣りに向かう時、ラジオで高校野球の中継をやっていた。地元・箕島高校の試合だった。
海について、さんざん釣りを楽しんだ。
で、帰りの車の中でラジオをつけると、まだ箕島が試合をしている。
とんでもない長丁場のシーソーゲームになっているらしい。
祖父母の家についてもまだ終わっていなかった。9回はとっくにこえているのに、片方が打ったとなると、また打ち返すという粘りに粘る展開で、なかなか終わらない。食事に入りながら、延長18回でようやく決着がついた。
これが甲子園史上の伝説になっている、石川県の星陵高校との試合である。野球に無知な筆者でも、これはすさまじいと思った。延長18回って、2試合分ではないか。
箕島の試合は、西宮に住んでいた頃に、甲子園球場で見たこともある。
夏休みで、母と妹と三人で行った。あれが球場に足を運んで野球の試合を生で見た初めての機会だった。
阪急の夙川という街に住んでいたので、甲子園は阪神電車に乗ってすぐなのだ。開会式の日など、風に流されて飛んできた風船が、マンションのベランダから見えたことを、今でも覚えている。
東京に戻ってくると、仕事にあけくれているし、またテレビを見なくなったが、早実は準決勝まで進んだそうな。
このブログを提出する今日、20日は、決勝戦がおこなわれる日でもある。筆者はこれから出勤する。まだ試合は始まっていない。
2015.8.12
第百七十三回 70年目の夏
戦後70周年ということで、山岡荘八の『小説太平洋戦争』という本の改訂版が講談社文庫から刊行されている。分厚いやつで、全6巻。それをやっと読了した。山岡荘八といえば時代小説の書き手で、筆者はそれほど好きな作家ではない。代表作と言われる『徳川家康』が未読だから何とも言えないが、この『小説太平洋戦争』は、これまで読んだ他の山岡作品とは、まるっきり濃度とテンションがちがっていた。
なにしろ、明治40年生まれの山岡氏は、従軍記者として戦地に赴き、実際に自分の目で見聞きし、関係者と顔を合わせ、体験したことまで書いているのだ。今後、かの戦争を書く作家がいたとしても、当時の空気を肌で知ったうえで紡がれる作品はもう出てこない。
それだけに濃く、かつ重かった。ただでさえ筆者の読書スピードは遅いのだが、この作品を読むには、ことさら時間がかかった。文章がサラリと喉を通らず、苦労して細かくかみ砕き、やっと飲み下していくといった感じだった。
とくに最初から開戦までがイライラして、一度挫折したぐらいだ。「小説」とわざわざ銘打ってはいるが、エンターテインメント性は極力抑えられ、ほとんどノンフィクションと言っていい。史実をたどりながら、鑿で岩盤に文字を刻むかのような入魂の筆致で書かれている。
それでも、真珠湾からマレー沖海戦、シンガポール、ミッドウエイ、ガダルカナル、ビルマ、ニューギニア戦線、レイテ海戦にサイパンの玉砕、硫黄島、沖縄……そして原爆投下と終戦まで、しんどい思いをしながら読んでいった。
そして、ふと思ったのは、今の若い人たちは日本が好きこのんで戦争を始め、世界の平和を乱したと教えられているのではないだろうか、ということだ。そうだとしたら、可能なかぎり戦争を避けようとしていたことぐらいは、ぜひ知って欲しい。さらに、それでも相手側が積極的に戦争をしたがっているなら、悲しくも開戦は不可避であるということを。
真珠湾攻撃にまで追い込まれた状況を例えていうなら、周囲のいっさいの商店が食料を売ってくれなくなったようなものである。
つまり、「死ね」と言われているのと同じ。人は、国家は、食べなければ生きていけない。
で、仕方ないからパンを盗んだ。そのとたん、「あっ、泥棒だ。お前は罪を犯した」と言って犯罪者の烙印を押されてしまったのだ。ここでいう食べ物を「石油」に置きかえてみれば、そのまんまなのである。
なおかつ「今後、お前だけ重税で、意見具申はいっさい認めないし、我々の言うことにはすべて従うこと」という文書に署名を求められた。インドのパール判事がいみじくも言ったように、「こんなものを突きつけられては、モナコ共和国でも開戦にふみきるしかない」。
いわば、戦うか、奴隷になって調和を守るかの二択で、前者を選んだのだ。
……自分としては右でも左でもなく、ごく普通の感覚のつもりの筆者だが、これ以上は書かずに、小説の本文から一節を引用して今回のしめくくりとする。
『徹底的に戦った民族は、曖昧に革命を行なう民族よりは、はるかに高い再興率を持っている。歴史ははっきりとそれを証明しているのだ。』
(山岡荘八『小説太平洋戦争』ミッドウェー海戦(四)より)
2015.7.30
第百七十二回 夏の街
和歌山県の有田郡に湯浅町という小さな街がある。筆者の母の出身地であり、お盆の帰省時にいつも二泊三日で泊まっていたので、湯浅といえば筆者の中では、「夏」のイメージが強い。
興味のある方は皆無だと思うが、もしお暇なら、「和歌山 湯浅」で検索してみると、熊野古道の宿場でもあった古い町並みをごらんになることができる。
昔ながらの瓦屋根、白い土塀がつづく通り、格子戸の家並み。古きよき日本という言葉が浮かんできそうな情景である。
この町は、醤油でも知られている。詳しいことは知らないが、醤油らしい醤油が日本で初めて作られたのが湯浅だとか、その近くだとか聞く(が、よくわからん)。
もうひとつ、金山寺味噌という名物もある。これは知る人ぞ知る「おかず味噌」で、そのままご飯にのせてオカズにしてもいいし、キュウリやレタスにつけて食べると、格好の酒の肴になる。もともと栄養満点のうえに、野菜とは全般的に相性がいい。
筆者は実家に帰って、これを見つけると嬉しく、手に入る場合はかならずもらってくる。ただ、風変わりな味なので、好みが分かれると思い、あまり誰にでもオススメはしていない。
それはともかく、祖父母の家は築年数の想像もつかない、古い木造建築の二階建てであった。ボロボロで、トイレは今どき水洗ではない。
そのかわり小さいながらも庭があり、盆栽やら何やらの鉢が並べられ、一部が菜園になっていて、キュウリやトマトやヘチマやヒョウタンまで採れた。火鉢(昔の暖房器具)を水槽にして、金魚も飼っていた。
この庭、面積自体はたいしたことないが、うっそうと茂った植物がひしめいているので、子どもの頃は、さながら『水曜スペシャル』取材班のような心持ちで分け入ったものだ。
祖父母も今はこの世にいない。7年前に祖父が倒れ、3年前には祖母も亡くなった。筆者が最後に祖父母の家に泊まったのは、2007年の夏、やはりお盆の時期だった。
昔そうしたように、情緒ある町並みを散策した。Tシャツにセッタ履きの軽装だ。そんな時、ある魚屋さんの店頭に、タコがおかれているのを見かけた。
茹でられたタコが、ザルのような浅い籠に入れられ、無造作におかれていたのだ。
パックなどされていないから、蠅がたかることもあるだろう。こういう売られ方だと、衛生面から、東京では誰も買わないのではないかと思った。そもそも東京では、魚屋さん自体あまり見かけない。魚といえば、スーパーで、パックされた切り身などを買うのが一般的なのだと思う。
だが、この町、湯浅では、こうして昭和の頃のように売られ、お客さん(おそらくはお婆ちゃん)が買うのだ。近海で取れたタコだから、新鮮さでいえば東京のスーパーで売られているものとは比べものにならない。昔のままの売買が、ここにあった。
2007年の夏、むき出しのまま魚屋さんの店頭にポンとおかれている茹でダコを見たとき、筆者は、湯浅に対する言いようのない感慨を覚えた。
それはさびれた街に対する哀切の想いであり、同時に生じた慕情でもあった。
2015.7.30
第百七十一回 肝だめしの夜
古風な夏の風物詩「肝だめし」を経験したことがあるだろうか。筆者は子どもの頃に、二回ある。最初は小学生の時で、お盆の夜、近所の公園でやった。
言いだしたのは、筆者の父だった。
「あの公園には、昔からお盆の夜にオバケが出る。よく光る一つ目で、白くてふわふわしていて、子どもを食らうバケモノだ。行ってみる勇気があるか」
筆者にはイトコが六人いるが、このとき遊びに来ていたのは、学研の回で書いた神戸のまじめな姉妹であった。我々はたちまち興味を示し、肝だめしは実行されることになった。
母と伯母は晩ご飯の片づけをし、伯父は家でテレビを見ているというので、言い出しっぺである筆者の父が、公園まで子ども四人(筆者・妹・イトコ姉妹)を連れていった。
公園の大きさは、学校の運動場ぐらい。木登りできる木と、飛び歩けるキノコ型の足場が幾つも突き出ている砂場と、ブランコと、小型のプールまであって、けっこう広い。
そして奥のほうに、輪切りにした円柱を重ねたようなコンクリートの巨大すべり台があった。円柱は上にいくほど小さく、簡単にいうとバベルの塔を平べったく押しつぶしたような形の構造物である。それがデーンとそびえているので、向こう側は見えない。
肝だめしのルールは単純で、入口から二人組になって公園内を歩き、ミニ「バベルの塔」を反時計回りに一巡して、またスタート地点に戻ってくる。それだけだ。
チーム構成は、妹とイトコ姉、筆者とイトコ妹、という組み合わせになった。
「一つ目のオバケに気をつけてな」
という父の忠告に送られて、まず妹とイトコ姉のコンビがスタートした。
和歌山の夜は暗い。そんなに遅い時刻ではなかったが、公園には自分たちのほかに誰もいなかった。妹&イトコ姉は遠ざかり、やがて例の巨大すべり台の向こうに消えていった。
遠くから悲鳴が聞こえたのは、その時だった。妹たちの声だ。
「オバケが出たな」と父がつぶやき、筆者とイトコ妹は、思いもよらぬ展開に緊張した。
なにかがあったのだ!
すでに悲鳴は消えていたが、妹とイトコ姉のコンビは、それからも戻ってこない……。
そして、第二陣として、筆者とイトコ妹も出発した。オバケなど信じてはいなかったが、ミニ「バベルの塔」に近づくと、いやでも緊張は高まってくる。妹たちの声は途絶えたきり、戻ってこないのだから。
「ほんとに一つ目のオバケがいるのかなあ」
あやしくて暑い、真夏の夜。学研のフロクには興味がないと豪語するイトコ妹も、この時はまだ幼く、いささか弱気になっていたのは無理もない。
だが、本当に現れたのだ。ギラギラと一つの巨眼を光らせた白いふわふわしたオバケが。
父の話はウソではなかった。オバケは「うら~」と木陰から襲いかかってきた。
さすがにビックリして、筆者たちは逃げた。すべり台の片隅で笑って立っている妹たちの姿を横目で認めたが、それでもわざとらしく悲鳴をあげて逃げるしかなかった。頭に懐中電灯をかざし、その上に布団のシーツをかぶった伯父が、まだ追いかけてくるのだから。
2015.7.24
第百七十回 ○○字以内で説明しなさい
夏期講習会の季節である。受験生にとっては大きな山場だが、こんなときになっても、「物語文はどうやって解けばいいのですか」というトンチンカンな質問をしてくる子がいる。ひと言やふた言でぱぱっと説明できないから、毎回の授業で、実際の長文と設問を扱いながら細かに教えているのだ。これは「きいてはいけない質問」であり、これだけで、いかに今までのことが身についていないかがわかってしまう。
ひと言で説明できないから、というのは、設問そのものに対してもいえる。説明文の要旨なり、物語文なら登場人物の心情なりを、「○○字以内で説明しなさい」というアレだ。
小説家の宮本輝におもしろいエピソードがある。
息子さんが家で国語の問題を解いていたところ、なんと、宮本氏の小説『泥の河』からの出題があった。「登場人物の行動理由を200字以内で書き表しなさい」とあるので、作者ならわかるだろうと考え、お父さんにやってもらうことにした。
「200字以内で説明できないから、この小説、書いたんだけどな」と思いながら、宮本氏が解いたところ、点数は意外にも36点。小説を書いた当の作者本人が、登場人物の行動理由を答えて、その点数なのである。
まるで笑い話だが、これはどういうことかというと、問題を解く際に対決する相手は、文章を書いた人(作者)ではなく、「作問者」だということなのだ。よって、出題の意図を読みとって答えないと正解にはならない。
とすると、何のための出題であり、読解なのか。だいたい書き手が言葉を選んで綴った本文を変換し、作問者が設定した文字数でまとめることに、どんな意義があるというのか。
少なくとも作者は、そんな「作業」を求めていない。宮本輝の「200字以内で説明できないから、この小説、書いたんだけどな」という嘆息が、すべてを表している。
小説には、まるごと一冊を通してはじめて伝えられる世界が、論理以外の部分で、「物語というかたち」を通すことでしか表現できない世界が、まちがいなくある。ブルース・リーではないが、「考えるのではなく、感じるもの」なのだ。
いや、物語に限らない。説明文だって、要旨をまとめるだけなら、それは「標語」という形態ですむのである。
受験勉強というのは「試験に合格するための勉強」だから、そのへんはパズルのようなものだと割りきってやるしかない。長文の読解にかぎらず、記号選択問題は本文との徹底した照合によるまちがい探しであり、文法問題などは分類わけの作業みたいなものだ。
以前、国語は苦手だけど国語の授業は好き、という子が、授業後にいつも質問にきて、筆者はそのたびに、40分ほど残ってつき合っていた。毎回、例外なく質問にくるのである。
みていると、たしかに小さなミスの多い子で、国語の成績はふるわないのだが、受験の結果、さいわいにも第一志望校に合格した。
その子は、卒業後の春休み、筆者に手紙をくれた。伝えたいことが、こちらの心に非常によく伝わってくる文面であった。学科の国語は苦手でも、その子の国語力は抜群だと感じ入った次第である。
2015.7.17
第百六十九回 一掛け、二掛け、三掛けて
宣伝がくり返されていたので、ご存じのかたもいらっしゃると思うが、5月下旬からDVDマガジンで『必殺仕事人』の刊行が始まった。隔週刊で、7月16日現在、5巻まで出ている。必殺にかぎらず、どんな長期シリーズにも、やがてはマンネリの危機が訪れる。制作側はそれを打破するため、異色作と銘打って、これまでとは極端にカラーの異なる作りを試るが、いずれにせよ、その後につづくのが「原点回帰」である。
必殺シリーズ第15作『必殺仕事人』は、オカルトにはしった前作『翔べ、必殺うらごろし!』で視聴率が低迷し、原点回帰をこころがけた結果、1年8ヶ月以上もの放送(全84話)というシリーズ中もっとも長く人気を維持した作品となった。
この成功によって、のちに続々と仕事人のシリーズが作られ、現在のSP番組にいたるまで、マニア以外の人にとって「必殺」=「仕事人」というイメージを確立させることになる。
では、原点回帰とはどういうことかというと、シリーズが進むにしたがって付属した数々の試みを一掃することだ。あたかも長い航海でこびりついた船底の貝殻を落とすように……。
必殺シリーズの原点といえば、第一作『必殺仕掛人』。殺し担当はたった二人、鍼医者の梅安による延髄刺しと、浪人侍の西村左内による剣技だ。
『仕事人』にも、奇抜な殺し技は出てこない。中村主水がもちろん刀、浪人の畷左門(伊吹吾郎)も刀で、武器がかぶっている。ただし左門の刀は、知る人ぞ知る剛刀・胴田貫で、剣技も豪快であり、その点が差別化といえばいえる。
もう一人、のちに必殺の主要キャラクターになる錺職人の秀(三田村邦彦)が、この作品で初登場する。武器は、まだかんざしではなく、初期の頃はノミを使っていた。延髄を一突きにする技は最初から変わっていない。
以上のように、殺し技はいたってシンプルである。この点、やはり第一作の『仕掛人』を意識したものと思われる。と言いたいところだが、左門の殺し技が途中から変わるのだ。
奇抜な殺し技が出てこないどころか、両親指で相手の背骨を折り、体を二つにたたんでしまう「腰骨はずし」が、第29話から登場する……らしい(筆者はまだ見ていない)。
この左門の妻・涼を演じる女優さん(小林かおり)は、なにげに薄幸の翳りがあっていいのだが、最終回で命を落としてしまうらしい。これもまだ観ていない。
元締の鹿蔵(中村雁治郎)もいい。第一話で標的となる極悪人兄弟の狼藉を、同心でありながら「相手が強すぎらあ」と見て見ぬふりをする中村主水。その後ろから「いくら強くても、悪い奴は悪い奴」と声をかける小柄な老人が鹿蔵だ。主水を闇の世界へと復帰させる。
もうひとつ面白いのは、仕事人の仲間に入った秀の、血気さかんな若者ぶりである。『仕事人Ⅲ』では、クールな大ベテランとして、ひかる一平に教えを説いていく秀が、この作品では、かけだしの仕事人として葛藤し、傷つき、成長を見守られていく。
オープニングもすぐれている。七五調のナレーションと凝った映像もいいが、バックに流れる平尾昌晃の曲「仕掛けて殺して日が暮れて」がすばらしく、筆者にとって全必殺シリーズ中、もっとも好きなオープニングである。
そのわりに、この『必殺仕事人』を、これまでほとんど観る機会がなかったので、DVDマガジン刊行は大歓迎であり、隔週ごとに書店で買い求めている(そしてそれが当分続く)。
2015.7.9
第百六十八回 学研の付録はスグレモノだった
先日、書店で学研の箱入り模型が売られているのを見た。夏休みの自由研究用だけでなく、大人向けのものもあり、興味を引かれると同時に、子どものころ定期購読していた学研の『科学』と『学習』を思いだした。あれはなにが素晴らしいかって、付録である。とくに『科学』の付録は、子どもにとって毎回オドロキとコーフンにみちみちており、学校から帰って机の上に本誌と付録がおかれているのを見ると、心が躍ったものだった。
たとえば「カブトエビの飼育セット」。小さな水槽つきだったから豪華なものだ。カブトエビというのは、爪ぐらいの大きさの甲殻類で、昔は田んぼなどで見かけた。それの乾燥させて粉末状になった卵が封入されており、水槽に入れた水に溶かしておくと、やがて本当にカブトエビが孵って泳ぎ出すのである。驚くべき「付録」ではないか。
古銭のモデルもあった。永禄銭など数種類の古銭の枠型に石膏を流し込んで固め、付属の絵の具で着色する。緑青まで塗って表すリアルさだが、硬貨偽造にはならないようだ。
鉱石標本にも驚いた。紫水晶や雲母など、カラフルな鉱石がケースに収まっていて、「これは宝石じゃないのか。こんないいものをホントにもらっていいのか」とさえ思った。
カブトムシの模型も作った。電池を入れると、本物のカブトムシと同じ足運びで動くのだ。
ほかにも、ブラキオサウルスの骨格プラモデルなど、小学生のオスガキにとっては垂涎ものの付録である。夢中で作り、完成したものを玄関先に飾ったものだ。
これらによって科学に対する興味が刺激されたことはまちがいない。が、信じられないことに、女の子にとってはそれほどでもないようなのだ。
筆者には、神戸に姉妹のイトコがいる。ものすごく上品で真面目な姉妹である。どのくらい真面目かというと、たとえば小学生の頃、いっしょに本を買いに行っても、筆者が漫画の最新刊を手にしている横で、『聖書物語』を選んでいるくらいである。
その妹のほうが、やはり『科学』と『学習』を定期購読しており、ある年の冬、彼女らの家へ遊びに行った時に、付録をくれることになった。イトコ・妹は付録には興味がなく、手つかずで残しているというのだ。「本誌に夢中だから」というのが、その理由だった。
筆者とは正反対だ。付録のほうが大事だった。とくに勉強中心の『学習』などは、本誌をろくに読みもしなかった。だいたい世の子どもというものは、グリコのキャラメルにしてもビックリマンチョコにしても、オマケが目当てで買うのである。よってイトコ・妹の言い分はにわかに信じがたかったが、物置に積まれている手つかずの付録の箱を見た時、そしてそれらを全部もらった時は、宝の山を掘り当てたかのような感慨に浸ったものである。イトコ・妹は学年がひとつ下なので、付録の中身もかぶっていない。夢ではないかと思った。
ここまで書いて、そういえば学研のテレビCMもやっていた、と思いだしたのだが、それが、
「まだかな、まだかな~。学研の、おばちゃん、まだかな~」
という子ども目線の歌だったのか、それとも、もの悲しいメロディーの
「学研のおばちゃん今日もまた~、笑顔を~運~んでいるだろな」
だったのか、思い出そうとして、しばし迷ってしまった。
答は前者である。後者は「学研」ではなく「ニッセイ」だった。
2015.7.2
第百六十七回 たまには必殺ネタをどうぞ
必殺シリーズ第8作『必殺からくり人』は、中村主水が登場しない「非主水シリーズ」で、この作品で必殺初登場となる山田五十鈴(花乃屋仇吉)がチームを仕切っている。毎回、冒頭に現代のシーンが挿入され、第5話「粗大ゴミは闇夜にどうぞ」ではゴミ問題、第9話「食えなければ江戸へどうぞ」では就職難など、社会問題と関わらせているのが特徴。
メンバーはほかに、藤兵エ(芦屋雁之助)、仕掛の天平(森田健作)、情報担当の仲間に、とんぼという女の子(まだ初々しいジュディ・オング)がいる。彼女が『魅せられて』で日本レコード大賞を受賞し、大ブレイクするのは、このドラマより三年後のことである。
そして、仕掛け枕を販売する「眠らせ屋」の夢屋時次郎(緒形拳)。殺し担当のリーダー格で、仇吉をサポートする強力な助っ人である。藤枝梅安、半兵衛につづいて、必殺で三度目の出演となる緒形拳だが、この「からくり人」では衝撃的な最期を遂げることになる。
また対立する組織の元締として、「曇り」という不気味な名前の人物を、必殺ではおなじみの怪優・須賀不二男が演じている。「曇り」は、からくり人のチームにとって、執拗な圧迫感と凄味をもつ悪役で、最終回「終わりに殺陣をどうぞ」では仇吉と一騎打ちをし、相打ちとなって共に果てることになるほどの強敵である。
だが、特筆すべきは、前述の時次郎(緒形拳)の最期だ。
最終回のひとつ前の第12話「鳩に豆鉄砲をどうぞ」で、時次郎は塔の中に潜み、鉄砲で幕府の要人・鳥居耀藏の暗殺を試みる。
印象的なのは、塔にあがってから標的の一行が現れるまで、待つ時間がやけに長いことである。周辺に鳩が群れつどう塔の中で、時次郎はひたすら待つ。握り飯を食い、水筒の水を飲み、弾丸をいじりながら、決定的瞬間にいたるまでの無為の時をただすごす。
どのみち死は覚悟している。成功したとしても、警護の者たちからは逃れられない。いわば相打ちでの奉行暗殺なのだ。この倦怠感さえともなう待ち時間を、稀代の名優である緒形拳が演じるのである。
やがて、鳥居耀藏の一行が現れる。「妖怪」と呼ばれて恐れられた実在の人物だが、必殺シリーズでは悪役としてたびたび登場する。演じるのは岸田森。怜悧な風貌が合っているのか、彼は他のドラマでも耀藏役を演じており、筆者も鳥居耀藏といえば岸田森の顔を思い出すほどだ。
額に汗の粒を浮かばせ、鉄砲の狙いをつける時次郎。だが引き金を絞ったその瞬間、なんたる偶然か、たまたま弾道を横切った一羽の鳩に弾が命中してしまう。
画面が赤く染まり、鳩の羽が周囲に舞い散る。一行は騒然となって、たちまち耀藏は保護され、時次郎の居場所は発見される。暗殺の失敗を知った時次郎は茫然とし、大量の火薬に点火して、壮絶な自爆を遂げるのだ。
必殺シリーズでは、殺し屋の殉職は珍しくない。ドブ川で数人にめった斬りにされて、ゴミのように息果てる赤井剣之介(必殺仕業人)の最期も『灰とダイヤモンド』のようで衝撃的だったが、この夢屋時次郎の死にざまは、それ以上にショックだった。
今さらながら、緒形拳の演技力、恐るべしである。
2015.6.25
第百六十六回 夏といえば
夏といえば? と訊かれたら、どんなものを連想するだろうか。子どもからは「映画」という答が返ってくる。なるほど、小学生にとって夏というのは、映画を観に連れていってもらえる季節なのだ。
筆者なら、子どものころは月並みに「海」と答えたにちがいない。でも、もう何年も海やプールに行っていない気がする。かき氷やアイスキャンディーも馴染みがないし、当たり前だがカブトムシやクワガタを捕りに行くわけでもなく、祭りにも行っていない。つまり季節感が乏しい。せいぜい思いつくのは「ビール」ぐらいか。
さて、道場の子どもたちにとって「合宿」は大きなイベントだろう。一般部の大人にとっても、道場の合宿は夏の風物詩であるといえる。
合宿というのは、ふだんの日常と離れた(文字どおり物理的に生活圏内から距離をおいた)空間で、ある目的のために、それに専念する環境に身をおくよい機会である。
どんなことをするのか不安だ、知りたい、という人は、先生や先輩に質問しましょう。
このブログでも、第22回と、第70回・71回のところに、2012年と13年の合宿の模様を書いているので、スクロールすれば確認していただける。重複になるので、詳しい内容は、もう書きません。
今年の一般部の合宿は、長野県の茅野でおこなわれるらしい。
茅野といえば信州。7月下旬の暑い季節、例年の合宿先よりも稽古しやすい環境ではないかと思う。体育館が蒸し暑かったり、汗をかきすぎてバテることもないだろう。
スケジュールに関する詳細は知らないが、ちょっと想像してみよう。
宿泊先は、湖のほとりにあるログハウス風のコテージで、稽古場の体育館までは白樺の並木をぬける小径を通っていく。蝉時雨に包まれた体育館の戸を開放すれば、避暑地ならではの涼やかな風が入り、稽古で火照った体を癒してくれる。
宿に戻ると、蓼科山を遠望できる大理石ばりの露天風呂にゆったりとつかり、その後は冷えたビールと、地元でとれた食材を使った美味しい料理を堪能する。
日が暮れれば、広間のバルコニーから湖の対岸の灯と、湖岸の道路に連なる車のヘッドライトを遠望しながら、節度をわきまえたささやかな酒宴の始まりだ。
翌朝はたぶん6時起床。爽やかな高原の冷気に触れてシャキッと目覚める。
早朝稽古は皆で体育館へ移動して、師範による「体の使い方」(これは今年あるかどうか不明)を教わる。帰り道では、白樺の木漏れ日が林道に落ち、葉影は風にそよぎ、のどかな野鳥のさえずりが聞こえる。
ちなみに、蚊はいない。道着のくさい人や前夜の酒が残っている人もいない。窓から猥褻語を叫ぶ人もいない。よってホテルの従業員の態度が翌朝から手の平を返したように冷淡になることもない。何から何まで充実した一泊二日ではないか(以上はあくまでも想像です)。
そういうあんたは行くのか、と言われると、一年でもっとも仕事を休めない時期で、どうしても参加できないのである。代講も立たない。幾分のわびしさを覚えながら答えると、筆者にとって、夏といえば「夏期講習会」なのである。
2015.6.18
第百六十五回 「本当の」強さとは
「困ったときに助けてくれるのが本当の友だちだよ」というように、よく「本当の~」がつけられる言い回しがある。
しかし「本当の」があれば、一方で「ウソの」もあることになる。ウソというのが言いすぎなら「本当ではない」ものでもいい。このちがいは何だろう。
使われ方をみると、前者は本質的というか精神的というか、あるいは抽象的だったり形而上だったり観念的だったりして奥が深そうなのに対し、後者は表面的もしくは即物的な意味で使われていることが多いように思われる。
たとえば、「本当の価値」という言葉。「あいつには○○の本当の価値がわからないんだ」というと、表面ばかり見て内在的な本質を見落としていると言ってるようだ。
「本当の理由」とくれば、これは建前ではない本音であり、それだけに人には打ち明けられない秘密めいた雰囲気がともなう。
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』ではないが、「本当の幸せ」といえば、お金や地位や名誉といったものより、貧しくても精神的に満たされた状態があげられることが多い。
「本当の自分」などという珍妙な言葉もある。どうやら、インドに行けば見つかるらしい。
「強さ」はどうだろう。これも、非常に「本当の」がつけられやすい言葉である。
「本当の強さ」とは耐えることだとか、優しいことだとか、その他諸々、いろんな人が語っているが、やはりメンタルな内容が多く、正直、あまりぴんとくる答には出会わない。まるで空手家が追求している強さが「本当ではない」もののようである。
世の中には不条理な暴力というものがあり、きれいごとではおさまらない現実を知っている大人からみると、上記は噴飯ものの理屈であることが多いのだ。問答無用で家に押し入ってきた強盗に、そういった「本当の強さ」で対処できるだろうか。「話せばわかる」と言って暗殺された人もいる。
では、本当の強さとは何なのか。
組織においては、その長を見ればわかるように「権限」の大きさとしてとらえることもできる。経済的に社員の生殺与奪の権限を握っている社長などは、社内において最強かもしれない。核保有国の国家元首は言うまでもない。「力」=「権力」と言い換えてもいい。
だが、権力もテロという暴力には万全ではない。
筆者が、これまででもっとも納得した強さの定義は、『範馬刃牙』で主人公の父親が語った「条件に左右されぬ力。自らの意志を希望する通りに実現させる力」というものだ。
作者の板垣恵介氏は、強さについて考えぬいてきた人なのだと思う。なるほど、あらゆる条件に当てはまるのではないか。
ふと思ったが、大山総裁は「本当の強さ」について言葉を残されているのだろうか。筆者は寡聞にして知らないのだが……。
「きみぃ、本当の強さとは、空手が強いことだよ」
これぐらい言い切ってくれていたら爽快である。
では、江口師範なら、なんとお答えになるだろう……と思いつつ締めくくる。
2015.6.12
第百六十四回 私だけでしょうか
「~なのは私だけでしょうか」という言い方がある。あまり大真面目な内容(社会問題など)で使われることは比較的少なく、どちらかというとちょっとユーモラスに、日常で見聞きした些事に関して、他者に賛同を求める場合に用いられることが多いのではないかと思う。
筆者も真似して何題かか考えてみる。いくつ同意していただけるだろうか。
小学校の時、音楽の時間に習った「パパからもらったクラリネット」というクラリネットの歌(題名は知らん)で、「こわれて出ない音がある」というから、一つか二つのように思っていたら、「ドとレとミとファとソとラとシの音が~出な~い」とのこと。それじゃ、全部だ。まったく音が出ないということではないか、と思ったのは私だけでしょうか。
筆者は歌詞に対するツッコミが多いようだ。同じく『ドレミの歌』。終わりの「さあ、うーたーいーまーしょ~う」のところで、「今うたったやんけ」と思った小学生は私だけでしょうか。
さあ、これから歌いましょう、という歌詞とは裏腹に、現実ではちょうど歌い終わろうとしていることに矛盾を感じた次第である。
これも歌だが、『瀬戸の花嫁』で、「幼い弟~」のところが、幼い「お父(おとう)」とはいかなるものか、と思ったのは私だけでしょうか(あんただけだ、と言われそうな予感)。
金八先生が「人という字は~」支え合い、助け合って生きている形を表しているのです、と言っていたらしいが、ゴシック体ならともかく、明朝体や教科書体で、一画目(左側)を、二画目(右側)が一方的に支えているように見えるのは私だけでしょうか。つまり、右側が倒れてしまえば、支えを失った左側も必然的に倒壊することになる。
人間関係とはそういうものか。あるいは、支える側と、その上にあぐらをかいてのさばる人間に分かれているという社会の縮図を表しているのか(正しくは、「人」は象形文字です)。
宮沢賢治のどの作品かは忘れたが、ある欲の深い登場人物が、最後に猛毒を飲んで、
「あぷっといって死んでしまいました」
と書かれた箇所を読み、例の「ひでぶっ」や「あべし!」と叫んで息絶える『北斗の拳』の悪者を連想したのは、私だけでしょうか。
最後に『浦島太郎』の歌の三番か四番だったと思うが、竜宮城からもとの村に戻ってきたところで、「戻ってきたら、こはいかに~」の「こはいかに」が「怖い蟹」に聞こえてしまったのは私だけでしょうか。様相の変わり果てた故郷を見て「これは、どうしたことか」と驚きの心情を表した歌詞だが、いかんせんメロディが朗らかすぎて合わないのである。この違和感はたぶん、私だけのものではないと思う。
2015.6.4
第百六十三回 VS女子高生
そういえば、かの『ヤッターマン』で、ボヤッキーが「全国の女子高生の皆さ~ん」というお決まりのセリフを口にしていたが、いったい「じょしこおせー」とは、「女子の高校生」をさすのか、はたまた「女子校の生徒」のことなのか、どっちだろう、と子どもゴコロに考えたものだ。念のためにいうと、むろん前者である。なぜ、こんなことを書いているのかというと、筆者は先日、道ばたで見知らぬ高校生(らしき少女)から、「キモい」と言われたからである。
仕事帰りの夜道だった。筆者が府中から国分寺方面へと向かう幅広の歩道を歩いていると、前方から自転車でやってきた女子高生(推定)が、
「シャツイン、キモい~」
と言って、通りすぎていったのである。
あたりには、ほかに人がいなかったから、筆者をさして言ったことはまちがいない。
シャツインとは、「Shirt」が「IN」していることだ。すなわち、ワイシャツの裾がズボンの中に入っている状態をさす。それを「キモい」とは何事か。仕事帰りなら当然ではないか。どこの世界にズボンからワイシャツの裾を出して歩いている社会人がいるというのだ。
うしろから追いかけていって、
「(そんなことを言う)お前のほうがキモい!」
と言ってやりたかった。
女子高生といえば、これはずいぶん前のことだが、八王子のゲームセンターで二人組に声をかけられた。
筆者はUFOキャッチャーが得意である。箱入りの玩具や大型のぬいぐるみを手に入れたことが何度もある。この時も、移動時間があまったのでゲーセンに入り、UFOキャッチャーでさっそく大型のぬいぐるみを獲得した。さらにクレーンを操作していると、
「ねえ、うまくない?」
と後ろで声がする。二人組の女子高生だった。その二人に100円玉を差し出され、「これであたしたちにも取ってくれませんか」と頼まれたのである。
もちろん断った。100円(つまり一回)で取れるとは限らない。第一こういうものは自分で取るから面白いのだ、と説明したのだが、「失敗してもいいですから」と彼女たちも譲らない。
で、気乗りしないまま100円玉を投入し、十代の子のお小遣いを無駄にするのではないかというプレッシャーを感じながら、食い入るようにクレーンの動きを見守った結果、見事にハズレ。なんだか申し訳ないような気がして、先に取ったぬいぐるみを、その子たちにあげた。
すると二人は、また語尾を上げる特有のイントネーションで、「やさしくない?」と言っていた。どうやら、互いに「~ない?」という補助形容詞を用いた付加疑問形で確認し合うのが、彼女たちの口癖のようであった。
もうひとつ。国分寺の某総合クリニックでのこと。筆者は足の裏の皮がめくれ、気になって診察を受けに行ったのだが、ひとつ前が女子高生だった。
そしたら、お医者さん、診察時間が長いのなんの。こちとら予約して時間どおりに行ったのに、45分も待たされた。ちなみに筆者はその日の最後だった。
そりゃあ、たしかにオッサンの足の裏なんか診察したくない気持ちもわからないではないが、だからといって女子高生に長く時間をかけすぎである。45分も何を事細かにやり取りしていたのだろう。筆者の番になるとすぐ終わったぞ。
以上の例から考えるに、どうやら女子高生とのかかわりは、筆者にとってマイナスに作用するようだ。
念のために言わせてもらうと、足の皮の異状は水虫ではありませんでした(強調!)。角質異常というものなので、もし道場で筆者の足の裏が変だと思ってもご心配なきよう。
(今回、三つエピソードをあげた結果、文字数オーバーです)
2015.5.28
第百六十二回 ヒーローは高いところで苦悩する
ヒーローは高いところで苦悩するものらしい。これは筆者が見たヒーローものの映画・アニメなどの主に映像作品における統計上の観測結果である。
具体的にいうと、『バットマン』のシリーズ、『スパイダーマン』、『デアデビル』など、ハリウッドの作品だと、なぜか枚挙にいとまがない。
ものすごく古い日本のTVアニメでも『デビルマン』や『ミクロイドS』のオープニングやエンディングなどで、そんな場面があった。そんな場面というのは、ヤンマやデビルマンが、高層建築の一部らしき鉄骨に腰かけて、もの淋しげな表情を見せているシーンである。
なぜだろう。これだけ似たようなシチュエーションが共通していると、その理由が興味深くなってくる。
背景は、夕焼けの空であったり、雨の中だったり、都会の夜景であったりする。あまり晴れ渡った昼間、というのは見かけない。
これは情景による心情描写である。表だった華々しい活躍を「動」とすれば、「静」の一面。それをあらわすことによって、ヒーローがただの活劇機械ではなく、一般人と同じように内面的な繊細さをもった存在であることの暗示にもなる。
常人とはことなる特殊能力をもつがゆえの苦悩や葛藤。そこには、ほぼ無償奉仕といっていい自分の活動と、それが世間に本意ではない受け取られかたをすることへの疑問やジレンマもあるだろう。それゆえに、彼らは「自分が守っている都市」を俯瞰して、物思いにふけるのだ。
超人は人外の能力をもつことで、必然的に異端となり、孤独を背負う。
その証拠に、チームで活動する『ガッチャマン』は、各自が生身で(というか、マントで風を切って)空を飛べるのに、鉄骨などに腰かけて黄昏れているような、哀愁と孤独感のただよう場面がない。
余談だが、『ガッチャマン』といえば、「白鳥のジュン」の下着チラリが不必要なまでに多かったのはなぜだろうか。これでもか、というぐらいあった。派手なアクションシーンは言うまでもなく、エンディングで、ただ立っているだけの場面でも短いスカートの裾から白パンがのぞいているのだ。
むろん男性視聴者を意識しての演出だと思うが、筆者が『ガッチャマン』を見ていたのは思春期を迎える前の年齢だったので、少しも嬉しくはなく、むしろその逆で、「アホやな~この女」とか「いちいちパンツ見せんな」と、ジュンをバカにすることしきりであった。
話を元に戻す。ヒーローは高いところで苦悩するということ。
え、元祖アメリカン・ヒーローの『スーパーマン』はどうなのかって?
そういえば……筆者は、ジョン・ウイリアムスがテーマ曲を作曲した最初のやつと、三悪人と対決する続編(冒険編)しか見ていないのだが、その2作に限っていえば、なかったような気がする。
まあ、「あの人」は苦悩や葛藤とは無縁ですから。
2015.5.21
第百六十一回 現役であること
ボクシングの漫画は世にあまたあるのに、空手の漫画が比較的少ないのはなぜだろう?それは、ボクシングのほうがルールが確立しているからだ(と思う、たぶん)。
ルールの異なる団体が乱立し、試合競技としての歴史が浅い空手に比べて、ボクシングはスポーツとして世界共通の厳格なルールが定められている。
ルールは、いわば制約である。その制約の枠組みがしっかりしているほど、ドラマが生まれやすいことはまちがいない。
もっと言うなら、野球やサッカーなどの球技だ。確たるルールのもとでどれほどドラマチックな展開が生じるかはご覧の通りであり、そのぶん漫画などでも、作品として成立しやすいのではないだろうか。
筆者は野球を観戦することがまずないが、サラリーマンになりたての研修期間、一人の先輩に、「好きな球団ぐらいないと、取引先と話ができないぞ」と言われたことがある。
先輩といっても五十代半ばの人だったから、新入社員からみると、かなり年上である。研修の期間に、いろんな人について営業先を回り、仕事ぶりを見て学んでいくのだが、その人からは好きな球団を訊かれ、ないですと答えて、そんな話になったのだ。
まあ、話題を探してくれていたのだろう。それから、その人は、自分の子どもの話を始めた。どこどこの大学に入って、どんな活動をしている、といった内容だ。
筆者は新入社員のブンザイだから、感心したように相づちを打ちながら神妙に受け答えしていたが、内心では「この人は、なんで自分の子どもの話をするのだろう」と思っていた。ありていに言うと「あなたの息子さんのことに興味ないんだけどな」と感じ、もっとハッキリ言うと「この人、カッコ悪いな」と思った。
言っちゃ悪いが、その人は仕事のできない人だった。そのせいなのか、関心が自身の向上ではなく、次の世代に向かっているように見えたのだ。
出世をあきらめていることがカッコ悪いのではない。それならそれで、自分自身が好きで楽しんでいることはないのか、というもどかしさに似た感情を覚えた。
若者の、カッコ悪い大人に対する評価は、狭量で容赦がない。将来の自分の姿として重ね合わせ、それを否定し、排除したがるからだ。当時若者だった筆者もそうだった。 ところでボクシングの漫画には、必ずといっていいほど、老トレーナーが出てくる。かつて華々しく燃えた過去を持ち、今は才能のある若手を発掘して、世界チャンピオンにまで育て上げることに情熱を注ぐという、丹下段平の系譜をひくキャラクターたちだ。
現役を退いたあとで後進の指導にあたるのは、ごく自然なことである。でも、競技者としては引退しても、人生は現役だ。つまり、まだ生きている。それなのに自分以外の者(たとえ我が子であっても)に最大の目標を託す生き方というのは、ちょっとわからない。
我々は、江口師範というお手本を身近に見ている。その影響もあるだろう。また空手には競技ではない面もあるから、生涯にわたって修行はつづいていく(らしい)。
いや、空手以外のすべてのこと、仕事でも遊びでも、自分自身が打ち込んでいないと「面白くない」、「やってられない」と思うんだがな。次の世代なんかに託していられません。
2015.5.15
第百六十回 神戸まつりの季節
そろそろ神戸まつりの季節だろうか。毎年、5月の半ばごろだったと記憶している。筆者は小中学生の4年間を兵庫県の西宮ですごしたので、神戸まつりを見物する機会も何度かあった。サンロードや三宮の大通りをさまざまな山車が通り過ぎてゆくパレードは圧巻であり、また盛りあがった雰囲気も子ども心に新鮮だった。
まず、祭りのような特別なイベントでなくても、和歌山から転校してきた小学生にとって、神戸という街は魅力あふれる大都会だった。
ある日曜日、三宮の楽器屋さんの店頭にステージが設けられ、若い女性のエレクトーン奏者が『ルパン三世のテーマ』を弾いているのを見て、カルチャー・ショックを覚えた。
わざわざ特設のステージが設けられているのだ。そこで、洒落た服装のお姉さんが、いとも軽快に、なじみのあるアニメの曲を弾きこなしている。
日曜日のビル街に流れるエレクトーンの音色。筆者は、「ああ、都会に来たんだなあ」と感じ入ったことを覚えている。
転校したのは4年生のときだったが、和歌山の友だちとは、それからも誕生日にプレゼントを贈ってくれたりする大切な関係だったことはまちがいない。
1・2年生のころ、同じクラスに寄田君という子がいた。
顔は青白く、ちょっと腺病質なところのある子で、うちに遊びに来てトイレに入ると、手を洗った水道の蛇口を、「肘で」閉めようとするのである。いかにも汚いものを扱っているようで、いい気はしなかった。
ある日、寄田君の家に遊びに行くと、彼は艦船のプラモデルを作りかけだった。
「なつぐも、なつぐも」と、しきりに言っている。その船は海上自衛隊の護衛艦で「なつぐも」というらしい。宇宙戦艦ヤマトが大ブームだったから、筆者も戦艦大和のプラモデルは当然のように作っていたが……。
そう、まずは「大和」や「武蔵」だろう。それがなけりゃ「長門」や「信濃」だろう。空母でも「赤城」や「瑞鶴」など、いくらでもあるだろうに……。
数ある艦船の中から、なにを好きこのんで、わざわざ「海上自衛隊の護衛艦」などというマニアックなものをあえて選んだのか、その心理はうかがい知れなかった。
筆者はこの寄田君がちょっと苦手で、転校してからは交友が途絶えていた。4年生の時点で同じクラスではなかったので、引っ越し先も教えていなかったと思う。
さて、転校して最初の神戸まつりは、家族で見に行った。神戸(阪神地区)にきたのだから、神戸まつりぐらい見ておこうというノリだったのだと思う。
華やかなパレードを見送る人混みの中で、目をむいてこちらを指さし、横にいる親の服の袖を必死に引っ張っている少年がいた。
寄田君だった。筆者に会うつもりで神戸に来てくれたという。連絡先もわからないのに、そこは子どもである。阪神に引っ越したのだから、とにかく神戸。この時期だから神戸まつり。そんな感じだったのかもしれない。
ところが、雑踏の中でばったり出会った。こんな偶然もあるのである。
2015.5.9
第百五十九回 『泥の河』を観なかった二人
筆者が中学二年の初夏、ちょうど今時分のころである。「○○ちゃん(筆者のあだ名)、タダ券あるんやけど、映画見に行けへん?」と言って、辻本が映画のチケットを持ってきた。
タダで映画が観られる。もちろん「行く」と即答した。
辻本というのは、2年生になって同じクラスになり、筆者が転校するまで一番親しくしていた友だちである。
さて、肝心の映画だが、SFかアクションか、はたまたホラーか、どんな面白そうな映画だろうと思ったら、『泥の河』という聞いたことのない日本映画だった。
しかも、白黒である。いかにも地味で、文芸作品の映画化という感じ(事実その通りだが)で、中学生男子の好みではなかったが、タダで誘われている立場としては贅沢は言えない。実際、映画を見に行けるので喜んでいた。
次の日曜日に辻本と神戸の三宮に出た。当時(震災前)の三宮の駅構内はドーム型になっていて、神戸の映画館で上映している作品の予告編をエンドレスで流していた。
『泥の河』は、アンコール上映であるらしく、予告編はなかった。モノクロなのは古いせいではなく、わざとレトロな雰囲気を出すためで、アンコール上映といっても公開されたのは最近であるらしい。
そのころ、6月6日6時に生まれた悪魔の子ダミアンをめぐるオカルト映画の完結編が上映中で、筆者としては、そちらのほうに関心があった。
辻本も同じ気持ちだったのだろう。こぢんまりとした映画館に来て、『泥の河』のポスターや立看板を見ているうちに、「この券を売ろう」と言いだした。売ってべつの映画を観よう、と言うのだ。
賛成である。大人の料金より100円安くして売れば買ってくれる。自分たちも、買う人も、お互いにトクをすることになる。というわけで我々、急きょダフ屋もどきに変身。
「カップルに売ろう」と辻本は言った。「なぜなら、男は、いっしょにいる女の前では、カッコつけようとするからだ」というのが、彼なりの理由だった。もとより一枚ずつ交渉するより、二枚いっぺんに持ちかけるほうが手間も省ける。
で、都合いいことに、ちょうどやってきた若いカップルに声をかけた。
チケットには「非売品」と印刷されている。そのせいか、男性のほうは気乗りしないようだったが、女性のほうが我々を見て「ねえ、買ってあげようよ」と言ってくれた。
結局、買ってくれた。それから、筆者と辻本は意気揚々と例のダミアンの3作目を見に行ったのだが、これがまれに見る超駄作で、結論から言って大失敗。
知っている人には説明不要だが、『泥の河』は宮本輝の小説を原作にしている。筆者はその後、大学生のときにビデオ・レンタルでこの映画を観た。終戦まもない大阪を舞台に、少年たちのつかの間の交流を描き、かなり泣かせる映画だった。原作も三回は読み返した。
中2のときに見ていれば、また感想もちがっていたかもしれないが、少なくともあの666完結編より感動したことはまちがいない。運命には素直にしたがったほうがいいということだ。
2015.4.30
第百五十八回 望郷の旅
サブタイトルは必殺シリーズ第三作『助け人走る』の主題歌と同じだが、同作について書くわけではない。筆者は『助け人』は一回も見たことがないからだ。そのくせ主題歌は知っている。必殺では『風の旅人』もそうだが、ふるさとを恋う歌が目立つ。
明治や大正に作られた短歌にも、東京にいて望郷の思いをうたった歌は多いが、筆者はその気持ちがわからなかった。生まれた土地への愛着を感じるどころか、若いころはむしろ蹴立てて離れてきたようなところがあった。
筆者の出身地は、和歌山市である。
だいたい和歌山の出身者は、和歌山にこだわりすぎるように思える。
大相撲の力士だと、栃乃和歌や和歌乃山の四股名、演歌歌手の坂本冬美は『紀ノ川』、作家だと、中上健次の『枯木灘』は言うまでもなく、有吉佐和子はやはり『紀ノ川』に『有田川』、津本陽や神坂次郎など時代小説の書き手でも和歌山の人物を取りあげている。
中上は紀州の風土を特異なものとしてとらえ、土地の呪縛とまで語っている。
紀州は本当に特異なのだろうか。そんな感じはする。でも、自分の故郷だからそう感じているのかもしれない。ほかの故郷を知らないし、客観視できないので答は出せない。ただ自分としては、その後に住んだ西宮と比べると、やはり紀州のほうがアクが強いと感じる。
筆者には故郷に対する愛憎のようなものがあって、ずっと紀州から離れて暮らしてきた。
正月に帰省するようになったのは、五年前からである。
東京出身の人には、こういう気持ちがわからないだろうか。
ふたたび帰省するようになったのは、年齢的に角が取れたこともあるだろう。でも、自分の土台を作った風土への関心も否定できない。
筆者は小学四年生で故郷を離れているから、同窓会などの連絡は届かない。帰省したときに電話帳をみると、小学生時代の友だちの名前が載っているのを発見する。もし会うとしたら、自分からその連絡先に電話をかけるしかないだろう。
その後も転校が続いたので、中学でも高校でも、同窓会の連絡が来ることはないはずだ。別によいが、子どものころの友だちと縁が切れているというのは、何となく物足りない。
それが関係しているのか、子どものころのあだ名で呼ばれてもイヤではないのだ。
筆者は小学生のころ、友だちに「○○ちゃん」と「ちゃん」づけで呼ばれていた。
これは中学でも高校でもつづいて、大人になってからも変わらず、ごく親しい人に限って今でも(道場の仲間・先生や先輩にも)そう呼ばれている。
いい年をして「ちゃん」づけだって? と思われるかもしれないが、北島三郎だって「サブちゃん」なのだ。子どものころの呼び名がつづいていることは悪い気がしない。
さて、自分はいつか故郷に帰るのだろうか。そんなことをたまに考える。
引っ越しをくり返しているし、今住んでいるのは賃貸のマンションだが、いつか終の棲家として故郷に居を構えるのだろうか。東京でのつき合いもあり、空手も今の環境でしか考えられないし……。これも、まだ答は出せないでいる。
2015.4.23
第百五十七回 三原村に死す その2
「み、水……」 と、杖をつきながらヨロヨロ歩く。二十一世紀の日本で、まさかこんなことになるとは。前夜に四合、朝食で三合の飯を平らげ、急激に体重を増やしたあげく見舞われた食あたり。
一晩に九回の下痢と嘔吐に加えて、水分を供給できないことで脱水症状に陥っていた。
歩きたくないが、歩かないわけにいかない。その晩テントを張ったのは遍路道から外れたキャンプ場跡の広場だったので、人が通らないのだ。衰弱した体に鞭打って歩かないと、この山中で人知れず死んでしまう。『北斗の拳』ふうに言うなら「死あるのみ」である。
東京なら、ほんのちょっと歩けばいたるところにジュースの自動販売機を見かけるが、ここ三原村の13キロの道中には、まったくない。
途中、農家のおばさんが庭の植木にホースで水をまいているのを見かけ、たまらずに水を所望した。ホースから手に受けて飲ませてもらえればそれでよかったのだが、おばさんは、山からくんできた湧き水を冷やしていると言って、ペットボトルを持ってきてくれた。このときの感謝と、飲んだ水の美味しさは筆舌に尽くしがたい。
やがて忘れもしない「たけうち商店」にたどりつく。なんということのない普通の雑貨屋だが、飲み物を入手できない遍路道においては、オアシス以外のなにものでもなかった。
アイスを食ったが、そんな冷たいもの、弱りきった胃が受け付けるはずもない。でも渇きが癒せないので、そこから先は自販機に出会うたびにジュースを飲み、そして戻した。汚い話で恐縮だが、バニラアイスを食えば白の、コーラを飲めば黒の、Cooオレンジを飲めばオレンジ色の、というように、七色のゲロを吐きながら歩いた。下痢も治まっていないので、山中に捨てられたような崩れかけの廃屋に入って、塀の裏側でするしかなかった。
そうこうしているうちに、ひと気のない山道から道路に出た。生まれて初めてのヒッチハイク。トラック野郎のおじさんが「乗んな」と言って、次のお寺まで乗せてくれた。
その日も腹が治っていないので野宿なんかしていられない。すぐにトイレに駆け込めるように、ビジネスホテルを探して泊った。睡眠不足でもあり、衰弱しきっていて本当は歩ける状態じゃないのだが、この日は結局、三原村を中心に16キロ歩いたことになる。
その翌日、観自在寺というお寺に参った。小雨が降っていた。体調は回復していない。
山門のわきにある椅子に座って、ぼーっとしていた。
しめやかな雨の降る春四月。見知らぬ土地のお寺の山門わきで無為にすごす時間。
静かなお寺だった。限りなく無音。雨の音ぐらいしかしない。今まで先を急いであくせくと歩いてきたような気がした。一人きりで体を休めていると落ち着き、気がつくと一時間半もそうしていた。
車遍路のおばさんに話しかけられ、体をこわしていることを話すと薬をくれた。正露丸を持っているので断ったが「正露丸なんかよりよく効くから」と言われ、いただいた。
またビジネスホテルに泊る。聞いたことのないファミレスが街道沿いにあり、入って雑炊を注文。どのメニューも東京より二百円ばかり安かった。
雑炊ひとつが、40分かかっても食べきれない。二日ぶりの食事だった
2015.4.16
第百五十六回 三原村に死す
水木しげるの『日本妖怪大全』に「ひだる神」という項目がある。餓鬼と同じもので、旅先でこの妖怪に取り憑かれると、空腹でだるくなり、歩けなくなってしまうという。旅が徒歩だった時代、行き倒れる旅人も絶えなかったに違いない。筆者がお遍路で四国を歩いたときも、そういった石仏群をあちこちに見かけた。1200年ほどの年月のあいだ、四国路のいたるところで、飢えて倒れ、野垂れ死んだ人は数知れない。
お遍路では、道ばたで弁当を開くときなど、箸でほんのひとつまみのご飯を、かたわらの野辺においておくのが作法である。それによって餓死者の魂を鎮めるというのだ。
筆者の行程は基本的に野宿だったが、ひどく疲れていて、ちゃんとした食べ物が恋しくなった時には、安い旅館に泊まることもあった。
たとえば、足摺岬。四国の西南のはしっこ。ここまでの道のりが、お遍路の中でもっとも長く、その名も、昔から旅人たちが足を摺ってたどりつくと言われれたことに由来している。
筆者はこのとき、ありえないほど空腹だった。連日の野宿で、風呂に入れるだけでもありがたく、開放感もあった。腹がペコペコだったうえに、ちゃんとした料理に今度いつありつけるかわからないので、食い意地も張っていた。で、お膳を部屋にもってきてもらったのだが、それが美味しくて、お櫃の中のご飯を全部たいらげてしまったのである。
およそ四合だろうか。国分寺南口の「スタ丼」の大盛りで三合だから、あれより多いことになる。我ながら異常な量である。道中で「ひだる神」に取り憑かれていたのかもしれない。
食い過ぎは翌日の歩行にテキメン影響した。体が重く、足が進まないのだ。
高知の足摺岬から愛媛に向かう道は二通りあり、筆者は山中に入って、三原村という村を通過していくコースを選んだ。
お遍路を勧めた友人からは、三原村には十キロぐらい飲み物を買える店がないから、水を十分用意して、途中で休まず一気に踏破したほうがいい、とアドバイスされていた。
でも、足が重く、体調も悪くて、予定よりも時間がかかってしまった。
歩きだから、地図を見て、その日に野宿するポイントを考える。このままだと、三原村で夕暮れを迎えるだろう。だが、村の途中にキャンプ場がある。そこにテントを張れば、少なくとも水は得られる。水さえあれば何とかなる。そう思って三原村へ向かった。
……なかった。キャンプ場。
地図は五年前から改訂されておらず、その間にキャンプ場は閉鎖されていたのだ。
最悪にも、水なしの夜を過ごすことになった。もっと最悪なことに、食あたりである。昼に食べた弁当が傷んでいたらしい。体調が悪かったわけだ。
その夜、一、二時間ごとに起きた。テントから出て、吐き、下痢をした。ノートの記録によると、それを一晩に九回、くり返している。もちろん眠れるもんじゃない。
異郷の山の中でひとりぼっち。携帯の電波も通じず、誰の助けも呼べない。しかも食あたり。氏村、ピーンチ!
下痢と嘔吐で脱水症状だが、水はない。気温が十度以上さがっていて、テントの中でガタガタ震えた。よりによって悪い条件が一夜に重なってしまった。
2015.4.10
第百五十五回 神童たちの黄昏
もう十年以上前のことである。筆者の同僚に、裁判官を目指して司法浪人をしている青年がいた。家の方向が同じだから、何度かいっしょに帰ったことがあるが、不思議だと思ったのは、電車の中で彼が口にする内容だ。わずか二駅のあいだに、いつも同じことを話す。TOEICかTOFELか忘れたが、とにかく英語力を測定する試験で高得点を取っているらしく、その点数を大声で執拗に聞かせるのだ。
前に聞いた、もうわかったよ、と内心、辟易していたが、ある時ふと気づいた。
彼はどうやら筆者だけではなく、「周囲のほかの乗客」にも聞かせるために話しているようなのである。
TO…の点数が、よほど自慢なのだろう。地元では「神童」と呼ばれていたことも聞いた。
筆者の高校の同級生にも、幼いころ「神童と呼ばれた多く」の一人がいた。
彼はときどき理解しがたい言動を見せた。たとえば、何かのコンクールで自分が落とされてほかの者が入選したりすると、机に筆箱を叩きつけて怒っているのだ。
筆者は絵や音楽で入選したことがないが、作文や標語のコンクールでたまたま選ばれたりすると、彼に「俺のほうが、お前より才能あるのに!」と、はっきり言われたので驚いた。
たしかに筆者は国語の成績がよかったわけではないが……それを根拠に、堂々と見下すのである。だいたい、たかが作文や標語のコンクールで、才能うんぬんは大げさすぎる。なぜそこまでヒステリックに熱くなれるのか、理解できなかった。
彼は「誰かがプレゼントをくれると、それを目の前で壊してみたくなる」とも言っていた(面白い分析ができる言葉である)。また、幼いころに神童とたたえられて、次に取った行動は「自己否定だった」と話したこともあった。
神童といっても、彼の出身町は人口4500あまり、最寄り駅はJRの普通列車しかとまらない無人駅という、南紀のド田舎でのことである。それが何のステイタスにもならないことはわかっていても、幼いころに刷り込まれた「神童」の束縛から逃れることは難しかったようだ。
自分は他者よりすぐれている、という自意識は、蜜の味がするにちがいない。
誰だって進んで否定したくはないだろう。だが、現実に目をやれば、それですまないことぐらい、よほどのバカでないかぎりわかってくるはずだ。
世界が広がるとともに、自分以上の能力にゴマンと出会い、越えられない壁にもぶつかる。そんな時「こんなはずじゃないんだがな」と思っても、「自分はすごい」という評価が間違いだったと認める勇気は、なかなか出せないのだろう。
大人が「褒めてのばす」のもいい。だが、「失うものを持たない強み」と反対の重荷を背負って、幼少期に人生の最盛期を迎えた結果、大人になって電車の中で見知らぬ乗客に「俺ってすごいんだぞ」という情報を発信しつづけるなんて、悲劇としか言いようがない。
過剰に褒められた子は、やはり勘違いしてしまう。無理もないことで、これは大人の罪である。
高校時代の同級生が言った「自己否定」の内容が具体的にどんなものだったかは知らないが、いき過ぎた賞賛に、本能的な危機感を覚えていたのではないか、とさえ思う。
2015.4.2
第百五十四回 駆けていった犬
ウサギ、猫……と書いて、今度は犬のネタ。実家に帰っていた期間、筆者が走っていた時のことだ。
夏の朝の市街地で、野良犬が民家の外のゴミ袋をあさっていた。
食べ残しの生ゴミは野良犬にとって格好の餌になるが、ビニールが噛み破られると、ゴミが散乱する。よって、野良犬のほうでも、見つかると駆逐される立場にあることはわかっているらしく、いかにも卑屈な様子でゴミあさりをしていた。
もっとも、筆者には、犬を驚かせる意図などまったくない。走るのが目的だから、彼らの朝食に介入するつもりもなかった。
その犬は夢中だったせいか、筆者の接近に気づかなかった。
間近になって、すぐ脇を筆者が通ろうした時、初めて気づいて、仰天したらしい。磁力で弾かれたように、パッと大きく跳ねのいた。
そして……。偶然としか言いようがないが、それを見計らったようなタイミングで車がそばを通りすぎ、跳ねのいた犬は、その車の側面にぶつかったのだ。
ケガをするほどの当たりではなかったが、犬にとっては二重の驚きだったのだろう。まず筆者の接近に驚き、逃げたところ車に接触。
これ以上は何も起こらないのだが、驚きが冷めやらず、また事態を整理するだけの頭がないので、もう何が何だかわからない、という感じで、慌てふためいて、ひたすらまっすぐ走りだした。
百メートル以上あるだろうか、遠くまで見通せる直線道路である。そこを、犬は遙か彼方まで、果てしなく駆けてゆくのだった。その混乱ぶりがおかしかった。
もうひとつ。これは東京でのこと。筆者が前に住んでいたマンションまで、道場から歩いて帰っていた時のことだった。
後ろから、太り気味の男性が、鼻歌を歌いながらスキップしてやってきた。
スーツを着た大人がスキップするのを、筆者はこの時初めて見た。
ちょっと、おかしな男性かと思われる。ずっとスキップして、筆者を追いこしたところで、普通に歩き始めた。
(ここでやめるな、ここで)
どうせなら、どんどん先へ行って欲しい。
そしたら、その人、曲がり角で、犬を連れた婦人とはち合わせしたのである。
うわっと子どものように悲鳴を発し、飛び上がるほどの驚きぶりを見せると、そのまま一目散に駆けだした。
もう、驚きは過ぎたはずなのに、彼はとまらない。果てしない彼方まで、ずっと走っていくのだった。
……以上、二つの事例には、何の関連もない。
ただ、どちらにも「犬」が関わっていることと、「果てしなく駆けていった」ことだけが共通している。
2015.3.27
第百五十三回 猫と遊ぶ
俳句の季語に「猫の恋」というのがある。季節は春。ちょうど今頃の、ようするに猫の発情期を表したもので、かしましく鳴くことからつけられたものだろう。
前々回も書いたが、猫という動物は、見ていてとても面白い。
筆者が大学生のころ住んでいたアパートの周辺には、猫がたくさんいた。
雪が降った翌日である。アパートの塀には三センチほど雪が積もっていて、見ると、その上を猫が歩いていく。足の裏(肉球)が積雪に当たるので冷たいらしく、そろ~りそろ~り、と一歩ずつ脚を慎重にあげながら歩いているのが面白くて、思わず手をのばしたら、パニクって脚を滑らせそうになって逃げた。
これも同じ時期。銭湯の帰りの夜道。修繕中のアパートの下に、猫が丸くなっているのを見つけた。
筆者は、その猫に向かってダッシュした。
なんで? と訊かれると困る。理由はない。単なるおふざけである。断っておくと、この時は連れといっしょだった。一人では、さすがにしない。
いきなり突進されて、猫は動転したのだろう。逃げた先は、前でも後ろでもなかった。
「上」だった。つまり走ってくる人間(筆者)と反対側がアパートの塀だったので、その塀の上にジャンプしたのだ。
そして狭い塀の幅を走り出した。すぐ先が曲がり角だ。L字型にアパートを取り囲む塀で、猫はその曲がり角を猛スピードで曲がった。
修繕中のアパートだったことはすでに触れたが、どうやら塀の上に作業の道具が置かれっぱなしになっていたらしい。
ガンガラガッシャーン、パリーン!
まともにぶつかったものとみえる。何が置いてあったのかは暗くて見えなかったが、こちらも思わぬ展開に、その場から早々に立ち去った。
前々回に書いた、筆者のアパートにやってくる猫には、暇な時にヘッドホンで音楽を聴かせたことがあった。
これも理由はない。しいて言うなら、反応を見たいという実験的試みである。
ちなみに、聴かせた曲は、ワーグナーの『ワルキューレの騎行』。ショルティ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるもの。かの『地獄の黙示録』で、米軍のヘリの襲撃シーンに使われた曲だといえばおわかりだろうか。
結果といえば、予想通り、猫は嫌がってさっさと逃げてしまった。猫でなくても嫌だったかもしれない。
もう一度断っておくと、これらの行動は、今現在のものではなく、いずれも筆者が二十歳前だった時のことである(強調)。
さらに断っておくと、これを動物虐待だと受け取らないで欲しい。
筆者は、猫と遊びたかったのだ。
2015.3.20
第百五十二回 春の乱
1995年3月の朝、寝坊して9時前に起きた筆者が、午後出社するという電話を会社に入れると(最低のサラリーマンだ)、同じ職場の先輩女子社員に「電車は何線を使ってるんだっけ」ときかれた。妙なことを聞くもんだ、と思いながら路線名を答えたら、「今日、地下鉄で事故があったから。それじゃないんだね」という。それから、メシを食いながらテレビのニュースを見ていると、なにやら緊迫した雰囲気で地下鉄の事件が報道されている。どのチャンネルもそのニュースばかり。どうやら大事件であるらしい。
でも、そのわりに、何があったのか全容がつかめなかった。特定の駅や区間で脱線があったとかいう内容ではなく、これまでにない質の事件のようで薄気味悪かった。
3月20日の地下鉄サリン事件である。
筆者はこの時期、ある企業の広報室という部署に所属していた。
広報では、社内報を作るといった内部向けの仕事のほか、新商品が出た時に流すテレビCMも担当するので、そのCMを作る広告代理店が二社、出入りしていた。
いつも仕事の打ち合わせをしているわけではなく、世間話が大半なのだが、その日、片方の代理店の人と立ち話をしていると、当然ながら朝の地下鉄事件の話題になった。
むろん、まだ犯人はわかっていない。「誰がやったんでしょうねえ」という感じでしゃべっていた。その時、代理店の彼が言ったのだ。 「オウム真理教の犯行というウワサもありますよ」
断っておくが、事件が発生した当日、夕方の会話である。
教団の幹部が逮捕されたのは翌月のことだった。広告代理店の情報収集力とはこれほどのものか、と後になって感嘆した
。 もうひとつ。筆者は大槻ケンヂ氏の著作をたまに読む。『筋肉少女帯』のヴォーカルとしての彼よりも、著述家としての大槻氏のほうが好きである。で、『くるぐる使い』という本を持っているのだが、その巻末に、糸井重里との対談が載っている。
話題は、超常現象・オカルト・超能力などにかかわるおかしな人々で、大槻ケンヂはそういうネタが好きなのだ。
筆者はむろん信じていない。のだが……。
自称・超能力者たちのトンデモ言動が面白おかしく羅列された後、糸井氏が「その人たちが一様に一九九五年が大変だって言ってて」と話しているのだ。
後になってみると、たしかに阪神大震災、地下鉄サリン事件、警視庁長官狙撃事件。そして駅の異臭騒ぎやら郵便物の爆発やら、これまでにない騒動が頻発し、一年中オウムの不穏な話題に引っかき回されたのは周知の通りである。
ちなみに、その対談は『広告批評』という雑誌の94年2・3月号に収録されたものであり、筆者が持っている『くるぐる使い』ハードカバーの初版発行も94年11月なのだ。
衆目を集めるために不安をあおるというのはよくある手であり、偶然にすぎないのだが、若かった筆者が一抹の薄気味悪さを感じたのも事実である。
2015.3.13
第百五十一回 訪ねてきた猫
その時、筆者は大学一年生。和歌山から東京に出てきて、ボロアパートの部屋で一人暮らしを始めたころだった。朝、布団の中でまどろんでいると、手に毛皮のような感触があった。
ん? なんだ、これは。こんなものを昨夜近くにおいて寝ただろうか。まったく心当たりはない。見て確認する前に、意地でも思い出そうとしたが、どう考えてもわからなかった。
で、その毛皮を押してみた。すると、「ミャ」という声が。
跳ね起きて見ると、猫がとなりで気持ちよさそうに寝ているのだった。
その猫には見覚えがあった。
雨が降る夜、部屋の縁側(裏側)で雨宿りしているのを見かけ、サッシを開けてみたが、泰然として逃げるそぶりもない。
トラ猫で、面白いことに、額に三日月形の傷があった。猫同士のケンカでつけられたのだろう。『じゃりン子チエ』という漫画に出てくる猫の「小鉄」と同じである。三日月の形も、額の真ん中という位置も同じ。
それが面白くて、部屋にあげて缶詰を食べさせてやった。
以来、何度か訪ねてくるようになり、ついには布団にまで忍び込んでくるようになったのである。メスなので「ふしだら」な猫ちゃんだ。部屋は一階だったから、勝手に網戸をあけて入ってきたものと思われる。
そりゃ外の固くて冷たい路上で寝るより、布団で寝る方が心地よいのはわかる。さすが快楽主義者である。可愛いことは可愛いが、野良猫なのでダニがついていないか気になった。
この猫にはいろいろ食べさせた。一番喜んだのは、意外にも魚介類ではなく、乳製品のチーズだった。喜ぶどころか、目の色を変えて飛びついてきた。筆者が立ったまま、スライスチーズをブラブラさせると、ジャンプして一瞬の早業で奪い取ったのだ。
焦ったのはこっちだ。チーズはまだセロファンを外していなかったので、取ってやろうとしたが、猫はチーズを奪われると思ったのか必死で逃げ回り、結局そのままムシャムシャと食べてしまった。
どうなったのだろう。後から腹痛を起こしたのではないか。野良猫だから病院で診てもらうこともなく、その点は心配だった。
昼に訪ねてくることもあった。友人がうちに遊びに来ている時、その猫が現れ、後足立ちになって、「手」で網戸をからりと開け、我々の眼前をトコトコと横切り、ひょいと押し入れの上の段に飛びあがって、布団の上で悠々と寝始めたのだ。
我が家のように、無人の野をゆくように、こっちはまったくシカト。友人も呆気にとられて苦笑していた。
そのころから急に、ほかのいろんな猫が、筆者のアパートを訪ねてくるようになった。
猫は密会をしたり、言葉を交わし合うなどという話もあるが、それが本当なら、「あそこの部屋へ行ったらエサをもらえるぞ」と話していたのかもしれない。でも、そのわりには、ほかの猫とかち合った時、怒って追い返していたけど。
2015.3.6
第百五十回 『仕事人Ⅲ』を再放送して欲しかったのは氏村
必殺シリーズはいつ頃から堕落していったのだろう。すなわち、新しい試みに挑む気概をなくし、守りに入った時期はいつ頃なのだろうか。
必殺ファンで知られる作家の田辺聖子さんは、「仕事人Ⅲ」で、受験生という設定のお坊ちゃんキャラクター西順之助(ひかる一平)なる登場人物が加わった頃に、そういった危惧を抱いたというが、まことにもって慧眼だと思う。
その頃から見始めた筆者などは、『仕事人Ⅲ』は愛着のある作品なのだが、当時は視聴率がピークを迎え、劇場版や特別スペシャルも制作され始めた黄金期であったといえる。
もっとも、それはあくまでも視聴率としての黄金期であって、第一作の『必殺仕掛人』からご覧になっている江口師範からすると、内容の充実度としての黄金期は、やはり前期になるであろう。
ちなみに前期後期というのは、『必殺仕事人』をはさんで分けた見方である。
ここで初めて飾り職人の秀(三田村邦彦)が登場し、女子高生の人気をさらって一気に視聴率が跳ね上がることになる。そして続編の『新仕事人』から『仕事人Ⅲ』、『仕事人Ⅳ』まで、秀と三味線屋の勇次(中条きよし)という、キャラクターや殺し技は対照的だが、二人の美形の仕事人が中村主水とコンビを組むことで、必殺シリーズの人気を不動のものにしていったのである。
この頃(新~Ⅳ)の仕事人は、たとえば「Ⅳ」の24話『秀、空中で戦う』や同じく30話『勇次、投げ縄使いと決闘する』で見られるように、殺陣でも凝るようになった。
勇次と戦う投げ縄使いは、かの倉田保昭である。ご存じ『Gメン75』の香港空手シリーズで、白いズボンのマッチョマンと繰り広げる格闘アクションを楽しみにしてた人は多いだろう。
大山道場時代の師範代でもあった石橋雅史(先輩)もよく必殺シリーズに出演されているが、本格的に空手の修行をした役者さんのアクションは、やはり迫力がちがう。
倉田保昭の出演では、千葉真一が服部半蔵に扮した時代劇『影の軍団』でも、第二話で競演を果たしている。千葉真一のアクション演出に対するこだわりは尋常ではなく、同作では、同じ伊賀の出自ながら、目的を異にするために戦わざるを得なくなっていく同胞として、両者の友情と、ラストでの迫力満点の戦いが印象的だった。
必殺に話を戻すが、娯楽に偏重する時期があったのは、それはそれで楽しかった。筆者はケーブルテレビなどがない時代に、『仕事人Ⅲ』を再放送してくれないかと待ち望んでいたくらいである。が、なまじ人気が出ただけに、その後も同じ路線を踏襲するすることになったのが、衰退の原因であったことはまちがいないとも思う。
読者にとってこんな話題は退屈だろうか。それでも筆者は、このブログが始まってから一年間は必殺のネタを封印してきた。
この3月上旬で、当ブログも4年目に突入する。よくもまあ性懲りもなく3年も書いてきたものである。それも、あと一年でキリのいい200回。大谷先生ふうに言うなら、「五年目がないことを祈りつつ……」。
2015.2.27
第百四十九回 一兎を追う二人
二兎を追う者は一兎をも得ず、ではなく、これは一匹(一羽)のウサギを二人して追いかけた話である。筆者は小学校高学年のころ、西宮のマンションに住んでいて、そこの管理人さんの息子Kとよく遊んでいた。Kの家、つまり管理人さん宅はマンションのすぐ下にある。筆者宅は三階だったから、行き来するのに一分もかからない。めちゃくちゃ近所である。
そのKの家ではウサギを飼っていた。Kのお父さんは設計の仕事をしており、いつも留守だったが、図面などがおかれた仕事場は我々が勝手に入ってはいけない禁断の部屋だった。
ウサギはそれを知っていたのだろう。筆者とKは、よくそのウサギをつかまえようとして追いかけていたのだが、仕事場に逃げこめば安全だと学習していたようである。
ウサギは意外に素早く、後足でバッと床を蹴って、タンスの曲がり角をあっという間に曲がり、おじさんの仕事場へ駆け込んでいく。なかなかつかまえられない。
角を曲がって約30センチほどのところが仕事場の入り口であり、そこには横にスライドするドアがあって、いつも開け放されていた。
「このドアを閉めておいたらどうなるかな」と、ある時、筆者とKは話し合った。
ウサギは猛ダッシュして曲がり角を曲がる。いくら反射神経がよくても、勢いがついているので、止まりきれないのではないか。それとも、瞬時に気づいて方向転換するだろうか。
実験することにした。ドアを閉めておいて、ウサギを追いかけたのだ。
いつもどおりの猛スピードでウサギはタンスの角を曲がった。
瞬間、ゴンッ! と鈍い音がして、まともに激突。ウサギは鼻をひくひくさせていた。何が起こったのか、わけがわからなかったのだろう。もはや無表情で逃げるのを観念しており、我々はようやく「一兎を得た」のである。
このウサギは、のちに不慮の死を遂げてしまう。Kの家では犬も飼っており、死因はマンションの庭でその犬にじゃれつかれてのショック死だった。
春休みで、筆者はその一部始終を三階の手すりから見ていたが、犬にはたぶん悪気はなかったと思う。遊ぶつもりでじゃれついたのを、ウサギは襲われる、食われる、と思いこみ、逃げようとしたが、ショックのあまり小便を漏らして心臓停止。
それから、Kのおばちゃんのやった弔いがすごかった。発泡スチロールの箱で「棺桶」を作り、花と共にウサギの死骸を納めて、夙川という近所の川に流したのだ。
おばちゃんを弁護するなら、この人も悪気はなかった。ちょっと(かなり)ズレているがロマンチストなのである。乙女チックなことが大好きで、この時も少女のノリだった。
が、そんなものが海にまでたどり着くはずもなく、かならず途中で止まるかひっくり返るかしている。大迷惑である。ノリはともかく、やっていることは動物の死骸の不法投棄であり、れっきとした犯罪なのだが、乙女チックなおばちゃんにその自覚はない。「かわいそうなウサちゃん」と瞳をうるうるさせ、お花をいっぱい箱に詰めての、それは〈水葬〉だった。
ちなみに、そのマンションは阪神大震災で倒壊し、Kは二時間ほど生き埋めになったが、幸いにも救出された。「ウサギ追いしあの家」も、今はもうない。
2015.2.20
第百四十八回 キャンディとオスカル
国分寺道場のスガイズムが『エースをねらえ』にはまっているらしい。極真で黒帯を締めている大男が少女マンガに夢中かよ、とツッコミたくなるが、その気持ちはわかる。筆者には妹がいたので(今でもいるが)、子どものころはTVアニメを通して少女マンガに触れる機会が多々あった。サリーやアッコやメグやララベルといった魔法少女ものをはじめ、『アタックNO1』や『花の子ルンルン』や『ときめきトゥナイト』も見ている。
現代の子どもには想像もできないだろうが、昔は「チャンネル争い」というものがあったのだ。兄妹ともなれば、男の子向けと女の子向けの番組で見たいものが異なり、それを同時刻に放送されると争いが生じる。たとえば月曜日の夜7時だと『ガンバの冒険』と『魔女っ子メグちゃん』がかち合い、結果、各週ごとに交替で見るという妥協案が遂行されることになる。よって筆者は小学生のころ、異性が見る番組にも詳しくなっていたのである。
ヨーロッパでも日本のアニメは大人気だが、中でも『キャンディキャンディ』と『ベルサイユのばら』は、「これを日本人が作ったなんて信じられない」と思われているらしい。
女の子モード全開のキャンディと、男装の麗人オスカル。主人公は対照的だ。
が、ともにオープニングが秀逸である。ほとんどの登場人物を無理やり詰めこんだオープニングが多いアニメ作品の中で、『キャンディキャンディ』はあくまでも主人公だけ。ほかのキャラクターをいっさい出さず、キャンディの一人舞台で、ファッションショーのように次々と衣装を替えていく。あきらかに、そう意図したつくりである。主題歌も、中盤「ひとりぼっちでいると~」のところで、メロディラインが長調から短調へ大胆に変わるという斬新さ。
ちなみに、アニメの30分番組では、コマーシャルをはさんで挿入される短いカットがあり、たとえば『ルパン三世』第2シリーズだと、ルパンが横から車に飛び乗ろうとして反対側にずっこける「ルパン・ザ・サード」「あい」とか、『機動戦士ガンダム』だと「ダダダン……ダダダダン……シュー」とか(なんのことを言ってるか伝わっているだろうか)、『一休さん』だと「一休! 一休! 一休! は~い、あわてないあわてな~い、ひと休みひと休み」というような、そういうやつが『キャンディ』の場合は、くるくる回る日傘の向こうから「キャンディ! フゥゥ~」といって、キャンディがニコッと笑ってふり向くのである。
お調子者だった筆者は、雨の日に学校でこれのマネをした。廊下で傘(パラソルではなくアンブレイラだが)をくるくる回し、「キャンディ! フゥゥ~」と言ってふり向いた。
かなりウケていた。女子の視聴率はやはり圧倒的だったが、男友だちの中にも笑っているやつがいたから、筆者と同じように女兄妹がいて見ていたのだと思う。
一方、『ベルサイユのばら』は、小学生の頃、面白さがあまりわからなかった。ストーリー以前に、フェンシングでチャンチャンチャンチャーンとやる女が苦手だったこともある。これは『ベルばら』にかぎらず、『リボンの騎士』といい、そしてもちろん『ラ・セーヌの星』もそうだが、なんというか、あの剣戟に「負けそう」な感じがして嫌だったのである。
今見るとやはり素晴らしく、無邪気さゆえに悪意なく周囲をふり回していくマリー・アントワネットのキャラクターが、危なっかしくて面白い。これ以上なく本編に合った主題歌『薔薇は美しく散る』が先日は頭から離れず、一日中「りりしい気分」になっていた氏村である。
2015.2.13
第百四十七回 『少年チャンピオン』がチャンピオンだった頃
前回書いた『エコエコアザラク』が連載されていた頃の『少年チャンピオン』は、水島新司の『ドカベン』がよく巻頭を飾り、鴨川つばめの『マカロニほうれん荘』、山上たつひこの『がきデカ』、そして手塚治虫の『ブラックジャック』といった人気作品が同じ一冊の中に詰めこまれているという豪華さだった。手塚治虫がまだ健在で、『ブラックジャック』の新作が毎週読めたのだから、なんとも贅沢な話である。のちに『ジャンプ』にその座を奪われることになるが、当時は『チャンピオン』が、その名どおり週刊少年漫画雑誌のチャンピオンだった。
その『ブラックジャック』だが、実家にあるのを読み返していると、「よくこれを週刊連載していたものだな」と感じ入る。各話のクオリティの高さ、しかも、ほかにも複数の連載を抱えながら毎週コンスタントにそれを描いていたのだから、おそるべし力量である。
手塚治虫の作品は、しかし子供心にショックを受けることが多かった。小学校の三、四年生のころに読み始めたので、えぐい描写にも慣れていない。
たとえば、コミックの第2巻に「ナダレ」という話がある。ナダレというのはブラックジャックが脳手術した大鹿の名前だが、その鹿が高度な知能をもったばかりに攻撃的になり、山を削りにきた工事人足を殺戮するのである。堂々と立ったナダレの枝分かれした巨大な角に、人足の体が貫かれている場面があり、それが衝撃だった。
まだ日野日出志を読む前だったし、今なら何ほどでもない描写だが、当時は歩いていて本屋さんが見えてきただけで、「ああ、あそこに、あの恐ろしい場面がのっている本があるんだ」と思っていたので、よほど強烈な刺激だったのだろう。
ストーリーの面でも、天才外科医でも治せない人間の心の闇、残酷さや不条理が、子ども向け作品の予定調和的なハッピーエンドに慣れていた感性にとってショッキングだった。それら毒の強さに辟易しながらも読むのをやめられなかったのは、きれい事じゃなくて、現実にはこういう無慈悲なことも起こりえるのだと感じたからだ。
一方、『ふしぎなメルモ』などは性教育的な側面があって、それはそれでキツかった。
これはアニメで見たのだが、人間が、胎児と呼べるその前の段階で、サカナやサンショウウオのような形をしていることを初めて知り、絶句してしまったことを覚えている。
赤いキャンディを一粒食べると10歳若返り、青いキャンディだと10歳年をとる。主人公のメルモはその不思議なキャンディを使って「大人」の世界を体験し、命の秘密を垣間見ていく。
最終回は実際にメルモが大人になっており、赤ちゃんを産むために苦しむ場面があった。これは、いっしょに見ていた妹もショックを受けていた。
ちなみに、妹は後年、長女をわずか15分で出産する。心配は杞憂に終わったといえる。
それにしても、15分とは異例の短時間である。念のためにいうと妹は安産型とは正反対の痩せ型で、子供を三人産んだ今でもその体型は変わっていない。よって、なぜそんなにあっさりと産めたのかわからないのだ。かつては便秘で、毎朝20分もトイレにこもっていたことを思うと、うんこよりも楽々と出産したことになる……(妹はこのブログのことを知らないが、もし今回の内容を読んだら激怒するだろう)。
2015.2.6
第百四十六回 エコエコアザラク
先週送れなかった分とあわせて、今週はこれで3回分の更新になる。「サボリやがったな」というミもフタもないメールが某アジアジから届いたが、そのようにお考えの方は、2回前までスクロールして「いいわけ」の回を読んでほしい。
さて『エコエコアザラク』である。何のことかわからない読者は、きっと若者だと思う。
かつて『少年チャンピオン』に連載されていた古賀新一のホラー漫画だ。ホラーで4年にもおよぶ連載とはそれだけでも驚異的だが、これは黒魔術を題材にした異色の作品で、『エコエコアザラク』というのは、主人公の黒井ミサが唱える呪文なのだ。
人目を引く美少女・黒井ミサは転校をくり返し、その美貌ゆえ不良から強引に言い寄られたり、ほかの女子生徒の嫉妬を招いたりと、常にトラブルに巻き込まれる。そしてそのたびに水晶球やタロットカードを駆使して黒魔術を使い、時には邪魔者を消し、悪を抹殺していく。
そう、平気で人を殺すのだ。冷たい美貌で「ホホホホホ」とあざけるような高笑いを残し、悪党に対してはいっさいの慈悲をかけない。美しさと残酷さを併せ持った一種のアンチ・ヒロイン(?)とでもいうか、彼女のゆくところ学園に次々と死体が転がっていく。
連載が進むにつれてコメディの要素が混じり、ミサの性格もまるくなっていくのだが、筆者は小学生のころにコミックを集めていて、初期の黒井ミサの容赦のなさが好きだった。
そして再読をくり返しているうちに、彼女が使っているタロットカードが欲しくなった。
デザインに惹かれたのだ。大鎌を抱えたガイコツの「死神」や「悪魔」や「吊された男」など、異様な絵柄のカードにどんな意味があるのだろうと思うと、欲しくてたまらなくなった。
だが、どこを探しても売られていない。西洋のもので、日本では手に入らないのかとさえ思った。そういえば黒井ミサは「魔女」なのだ。子供心にもタロットカードに神秘的なイメージを抱き、禁断のアイテムを買おうとしているような気持ちだったので、親にも聞けなかった。
そんなある日の暮れ時である。ついに「これじゃないか」と思うものを見つけたのだ。
薬局の前の自動販売機だった。見たこともない地味な小型の販売機で、箱形の見本が三つ並んでいた。人目を忍ぶようにひっそりと売られていて、いかにも怪しげである。
もしや、これがタロットカードか。黒魔術で使うぐらいだから、やはり公然と販売されるたぐいのものではないのだろう。みると、「正しい家族計画を」と書かれている。
「ははあ、タロットで占って、正しい計画を立てろってことだな」と思った。冗談みたいな話だが、小学生だった筆者は本当にそう考えたのである。
でも、なぜ薬局の前に? それに黒井ミサが使っていたカードは、もっと縦長だったような気がする。ほんとにタロットカードなのか?
さんざん迷った末に、結局、筆者は「それ」を買わなかった。タロットカードだという確信がないまま、やがて熱がさめてしまったのだ。
買わなくてよかった。もし、あのとき買っていたら……。
箱を開けて「?????」となり、さらには親に問い詰められたに違いない。
ちなみに、タロットカードは大人になってから購入し、今でもどこかにあるはずである。
2015.2.4
第百四十五回 決戦は日曜日
2月1日といえば、東京や神奈川といった首都圏の中学入試本番。小学6年生たちが、これまで勉強してきた成果を発揮せんと、決死の覚悟で第一志望校の受験に臨む日である。それが今年は日曜日に当たっている。ドリカムのヒット曲に『決戦は金曜日』というのがあったが、決戦は日曜日なのだ。
受験業界では、2月1日が日曜日と重なることを、「サンデーショック」と呼ぶ。
どういうことかというと、ミッション系の学校(主に女子校)が、キリスト教では日曜日が安息日であり、礼拝をするため、入試を行わないのである。そういう学校はけっこう多い。
これによって、本来なら1日にミッション系を受験するはずだった子たちが、そうでない学校に流れ込む。当然、混乱が生じ、例年どおりの併願の予測が立てにくくなる。
もっとも、そうでなくても入試は毎年ドラマチックで、とんでもないことが起こる。
そして筆者はいつも思うのだ。本番で力を発揮できる子と、そうでない子の、資質のちがいは何だろうか、と。
このブログでは、今年の事例はもちろん、近年の出来事にも触れないことにしているので、ずっと過去の話になるが……。
こんなことがあった。双子の姉妹が同じ学校を受験したのである。
双子といっても二卵性で、外見も個性もまったく似ていない姉妹だったが、共通しているのは、二人とも素直で明るく、気のやさしい子だったこと。学力も同じぐらいで、同じクラスに在籍し、そして第一志望校も同じ。二人そろって同じ学校に通うことを目指していた。
この姉妹を大変な試練が見舞うことになる。
2月1日の受験で、妹だけが合格したのである。
運命の皮肉としか言いようがない。考えてもみてほしい。二人は同じ家に住んでいるのだ。
妹は喜びたかっただろう。第一志望校に一発合格したのだから。本来なら、その日は晩ごはんの席で大祝賀会が開かれるところだ。でも、お姉ちゃんが不合格なので、大々的に喜ぶわけにはいかない。両親だって気をつかう。
姉は大泣きしたと思う。同じ学校を受けて妹だけ受かり、自分は落ちた。家の中で喜びを抑えきれない妹の様子を見ている。第一志望なので妹の受験は早くも終了だ。自分は翌日も母といっしょに、真冬の早朝、厳寒の中を受験に行く。妹は家に残っている。
そして姉は二回目も不合格だった……。
12歳の少女にとって、こんな過酷な修羅場があるだろうか。地獄を見たといっても過言ではないだろう。
3度目の受験で、お姉ちゃんは合格した。
よくぞ、と筆者は思った。よくぞあきらめずに受験した、エライぞ、と思った。
悲嘆にくれて3度目の受験を放棄していたら(そんな子もいるのだ)、彼女はその後、劣等感を味わい、卑屈になっていたかもしれない。勇気を出して最後のチャンスをつかみ、その結果、4月から妹といっしょに第一志望校に通うことになったのだ。
今年は6年ぶりのサンデーショック。筆者は、また泣いた。毎年のことだけど。
2015.2.3
第百四十四回 いいわけ
いきなりだった。キーやマウスの操作中ですらなかった。パチン! と音がしたかと思うと、それっきり。もうまったく動かない。電源すら入らない。再起不能である。
何のことかって、突如、パソコンが壊れたのだ。
このブログを毎週木曜日に提出すると触れておきながら、今回、金曜日になっても土曜日になっても更新されなかった理由(いいわけ)がそれである。
パソコンに詳しい知人の話では、原因は「電源」ではないか、とのことだった。経年劣化もあるだろう。もう5年3ヶ月も使っていたので、そろそろ買い換えなきゃいけないとは考えていたのだが、いくら寿命でも、なんだかおかしいな、という前兆すらなく、パツンと鳴って、はい、すべてオシマイというのでは、対処のたてようがない。
さすが聞いたこともない三流メーカー。デスクトップのやつで、買った当初から動作がスムーズにいかず、音がうるさいのでカバーを取り外して使っていたぐらいである。今だったら仕事で使う道具に投資を惜しまないけど、当時は安さにつられて買ったのだ、粗悪品を。
このように、事故は突然起きる。悔やんでも仕方ないので、どうすればいいかを考えるしかない。
ネットから切り離された期間は一週間に満たなかったが、パソコンがないと、ホント、どうしようもなかった。メールもできず、仕事にも大いに影響する。スケジュール管理もパソコンでしているので、勝手が狂うことしきりだった。
それでも筆者の場合、使うのは文書作成とメールとインターネットぐらいで、エクセルとかグラフィックデザインとか、ゲームとか何だかんだといった機能は必要ない。投資は惜しまないといっても、必要最低限のものさえ入っていればいいので、余計な機能がゴテゴテと盛り込まれて値が張るようなものはいらないのである。
詳細は伏せるが、幸いにもネット環境は整い、こうして再びブログを書いている。消失したかに見えたデータは、ハードディスクが壊れたわけではないので、コピーできるコード型の装置を買ってきて復活させることができた。これが何より幸いだった。
それにしても我々現代人が、いかにパソコンに依存した日常を送っているかということである。かつて「2000年問題」が騒がれ、また彗星の超接近によって全世界のコンピュータのデータが消失するという仮説が囁かれたのも、依存しているがゆえの脅威であった。中国の軍隊が電脳ハッカー集団に力を入れているように、相手国のコンピュータを攪乱させることは、この上なく有効な軍事的活動でもある。
便利な道具だから依存するのは仕方ないが、せめて面倒がらず、こまめにバックアップをとる手間は省くべきではないと改めて認識した次第。
まあ、このブログを待ってくれている人がいるとは思わないから、更新できなかったことに謝罪するというのもおこがましい話だが、自分で決めたことが果たせなかったのは確かなので、2回分はアップしようと思う。
まずは、この「いいわけ」の回がひとつ。明日また追加分を送ることにします。
2015.1.22
第百四十三回 グラップラー刃牙
国分寺道場生のあだ名ではなく、板垣恵介先生の人気格闘マンガのことである。筆者はマンガ好きだが、連載雑誌には手を出さず、もっぱら単行本化されたコミックを買って一日一話ずつ読んでいく、ということを、4年ほど前から始めている。
本家ブログで戸谷先生がお書きになっていた『グラップラー刃牙』、続編の『バキ』もその例に倣ってコツコツ読んできたのだが、あまりに面白くて、一気に読んでしまいたい衝動を抑えるのに苦労した。そして去年、とうとう第三部『範馬刃牙』を最後まで読み終えた。
刃牙シリーズの魅力を一言でいうと、「驚き」だと思う。この作品には、常に驚きがある。読者はその驚きの波に乗せられて次々にページを繰っていく。
もう、めくるめく展開なのである。超人たちのとんでもない戦い、奇抜なアイデアが、これでもかというほど、惜しげもなく読者の前でくり広げられる。
登場するキャラクターたちは、みんな型破りで濃密である。個性が強すぎて、各自を主人公にしたスピンオフ作品まで派生するほどに。
セリフも凝っている。たとえば空手家の愚地独歩と柔術の渋川剛気の対戦で、相手の力を利用する柔術に対し、愚地独歩が静止して構える場面がある。このままだと戦いは硬直し、渋川剛気から仕掛けなければストーリーは進まない。ここで、
「おぬしの技とワシの技、どっちが上でも構わんと言うには、この渋川」
と、選手の中で最高齢の渋川剛気が、突進しながら言うのである。「若すぎるッ」
なんという上手いセリフだろう。みずから仕掛ける必然的理由と同時に、渋川剛気の人物造形まで合わせてやってのけている。
格闘の科学的な解説にはときに無理もある。まず、どんなタフネスでも生身の人体である以上、これだけの打撃を喰らうと続行不可能だというダメージが完全に無視されている。だが、作者が格闘技の実践者である以上、それを確信犯でやっていることはまちがいない。
マンガに必要なことを、作者は知りつくしているのだろう。読者が求めているのは登場人物の生きざまである。よって破天荒なまでのダイナミズムを優先させ、常識など平気でシカトする。科学的な裏づけにこだわりすぎると、物語から躍動的な展開が失われるのだ。小説でも、SFが廃れていった原因がそれである。
作者の筆さばきは驚くほど自由だ。マンガという媒体が持つ特性が最大限に活かされ、これまでに見たことのない表現方法まで開拓されている。漫画家になりたい人は、このシリーズを読むことで有意義な学習ができるのではないかとさえ思う。
設定で面白いと思うのは、主人公の刃牙が戦う理由である。ほかの登場人物たちが地上最強を求めているのに対し、刃牙だけは「父親に勝つこと」を目的に精進する。
父親にさえ勝てればいいのだが、その父親が地上最強の生物なので、自分も最強を目指さなければならないのである。
TVアニメ版のオープニングでは、こんなナレーションがあった。
『男なら、一生に一度は誰でも夢見る地上最強の男』
地上最強か。……筆者は夢見たことがないんだけどなあ。
2015.1.15
第百四十二回 20年……。
1995年1月17日。すでに社会人になっていた筆者は、職場におかれたテレビの映像を見て、衝撃のあまり言葉を失った。神戸の街が燃えている! ビルが崩れている!
映しだされているのは見知らぬ土地ではなかった。筆者は小学4年から中2まで兵庫県の西宮市で過ごしている。クリスマスには神戸の三宮で食事をするのが恒例だったし、新年には西宮の戎神社や神戸の生田神社にも参詣した記憶がある。その生田神社の鳥居が大倒しになり、前年の正月に車で走った阪神高速が崩れているのだ。
95年には実家がまだ西宮にあり、神戸市の垂水区には従姉妹が住んでいた。
実家は7階建てマンションの6階で、ヒビが入ったものの倒壊はまぬがれた。
筆者が帰ることを告げると、来なくていいという。水道が機能しないというのだ。うちの実家は前の晩に使った風呂のお湯を翌日まで抜かずに残しておくのだが、それが幸いして、トイレの水を流すのは風呂の残り湯を用いたらしい。
さらに、筆者が小学生のころ住んでいたマンションの管理人さん一家が、行く場所をなくして避難してきており、これ以上は一人でも少ない方がいいと言うのだった。
ちなみに、その小学生時代のマンションは、一階が吹き抜けの駐車場だったせいか倒壊し、幼なじみが二時間ほど生き埋めになって救出された。後で写真を見てゾッとしたものだ。
神戸にいるイトコ姉妹の姉のほうは、エレクトーンの先生をしている。そこの生徒さんの家では、グランドピアノが階段をふさいでしまい、階下に降りられなくなった。脱出するためには、やむを得ずノコギリでグランドピアノの脚を切って下に落とさねばならず、切りながら涙が出たそうだ。
筆者が帰省したのは、その年の夏だったが、マンションの前を通っている阪急電車の高架が、ぽきりと折れていたのには驚いた。倒れた阪神高速といい、ありえない光景だった。
ちなみに、当時首相だった村山富市は、自衛隊の出動命令を即断できなかった。「前例がないから」というのが、その理由である。「前例がない事態」が起こっているというのにだ。
そんなヘタレが最初にやったことは、財界人との朝食会だったらしい。
国民が大惨事に見舞われているときに、財界人の機嫌を取りながら、どんな顔をして飯を食っていたのだろう。たいした内閣総理大臣である。
この時、世界中のマスコミが阪神地方に駆けつけたが、なぜ暴動が起きないのかと驚いていた。それどころか炊き出しまでして助け合っている。かくして日本は『国民は一流、政治家は二流』と言われた。が、中には食糧不足につけ込んで、焼きそばを2千円で売りに来た輩もいたらしく、そいつはヤクザに駆逐されていたそうだ。
筆者は某企業の広報室に勤務していた。広報室には各種の新聞がそなえられており、メンバーの仕事は、まず朝イチで、それぞれが担当する新聞の記事に目を通すことだった。
筆者は東京で何もできないまま、毎日更新される震災死亡者の蘭を熟読した。小学生、中学生だったころの友だちの名前が載っていないか、毎日探していた……。
あれから20年たつが、神戸在住の伯母は今でも忘れられない悪夢だと語っている。
2015.1.8
第百四十一回 1200年!
大晦日には久しぶりにテレビを見た。紅白歌合戦。本家ブログで小沢先生がお書きになっていたボクシングの天笠尚の試合も観たかったので、たまにチャンネルを変えながら。天笠選手はデビュー10年目、35試合目だという。それで初めて世界王者への挑戦権が回ってきたのだから、厳しい世界だと思う。その稀有のチャンスを逃さないため、ただでさえ苦しい減量を、さらに階級を落として挑んだのだろう。
話を戻すと、筆者は紅白の後にやる『ゆく年くる年』の雰囲気が好きである。田舎のお寺の背景が星ひとつ見えない真っ暗な闇で、除夜の鐘が鳴って、いかにも厳か。初詣の人波の中に、たまにヤンキーの姿が散見されるのも、なんだかおかしい。
その『ゆく年くる年』によると、なんでも今年は弘法大師(空海)が高野山に金剛峯寺を開いて1200年目に当たるそうだ。
1200年とは、またえらい歴史である。若い人にはピンとこないかもしれないが、人間30歳をこすと、100年がたいした年数だとは思えなくなってくる。日本史をふり返っても、江戸時代なんかは、「わりと最近」という気がする。10年があっという間なので、その10倍もそれほど遠いとは感じないのである。
でも、さすがに1000年は遠い。ましてや1200年ほど前に亡くなった空海の遺志が、現在でも連綿と受け継がれているというのがすごい。遺志と書いたが、真言宗を信じる人にとっては、空海は亡くなっていないのである。知っている人は知っているが、空海は自身の再来を予言している。そうして現在でも、この酷寒の中、紀州の山の中で僧侶の方々がストイックな修行に励んでいるのだ。
このブログでたびたび触れたが、筆者は和歌山の出身である。高野山(金剛峯寺)は和歌山県伊都郡というところにあって、車で行くと和歌山市からは実質的にそれほどかからない。
実質的に、というのは、ひとたび山中に入るや、感覚的には別世界の様相を呈しているように思えるからだ。
標高がおよそ1000メートルの山中ということもあるだろう。紀州では雪が珍しいが、冬の高野山は例外。夏でもひんやりとしている。でも、そのせいだけでもないと思う。
筆者には霊感がなく、また仏教徒でもない無宗教の身である。それでも、異様な空気を感じた。しんしんと張りつめた、まさに荘厳としか言いようのない結界。
今までの人生で、こんな雰囲気を持つ空間を、筆者はほかに知らない。
悪い意味ではない。突き抜けるように澄みきった霊気なのだ。
高木に囲まれ、武田信玄、伊達政宗……とそうそうたる戦国武将たちの名が記された墓標を眺めながら参道をゆき、奥の院にたどりつく。
その地下には、今でも即身仏となった空海(ようするにミイラ)が安置されている。お遍路をして四国を回ったことのある筆者は、空海という人類史上における桁外れの超人に最接近したことで、襟を正してしまう。
筆者が参ったのは過去に2回、8月と5月だった。今度は一度、厳寒の雪深い高野山を訪れたいものである。